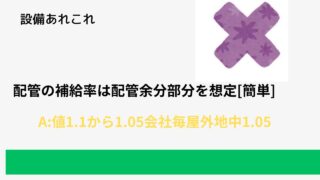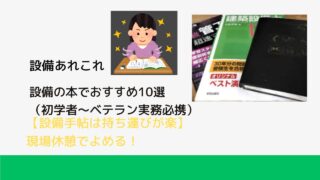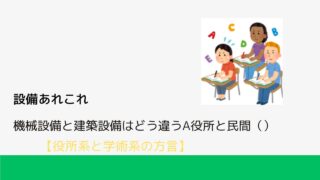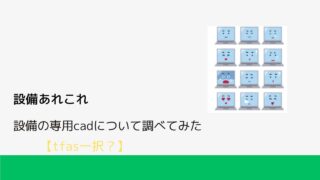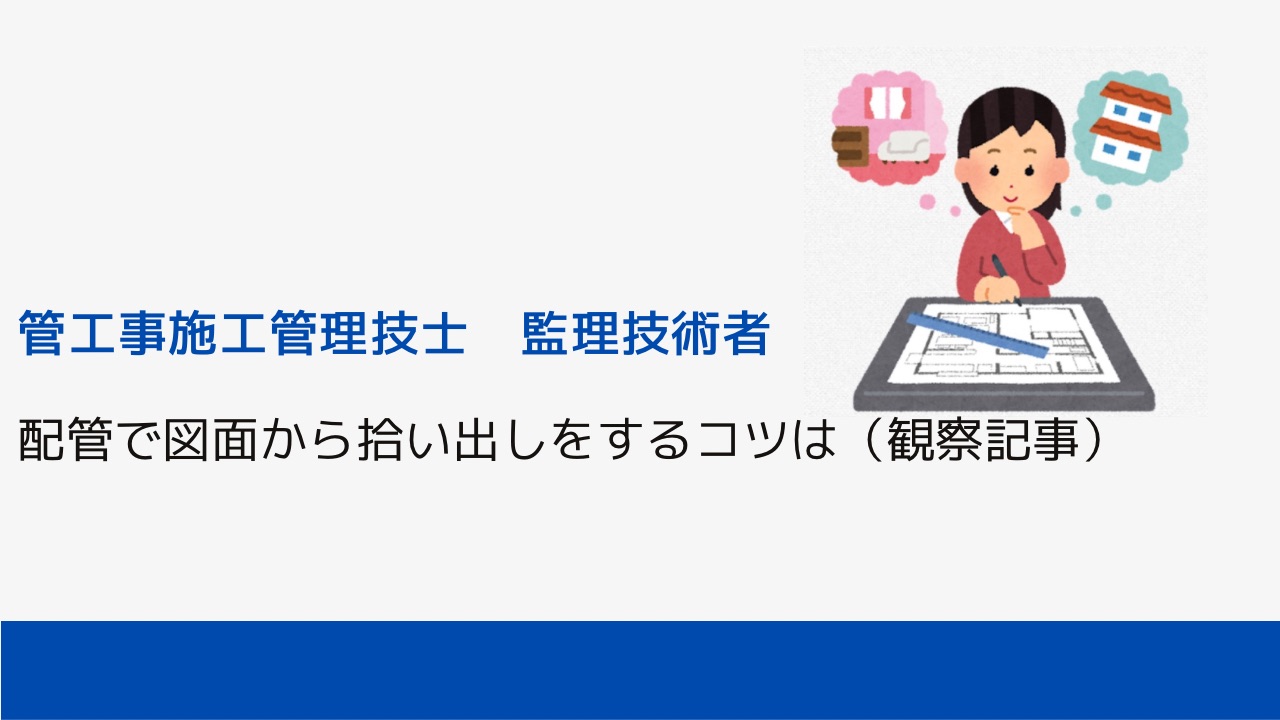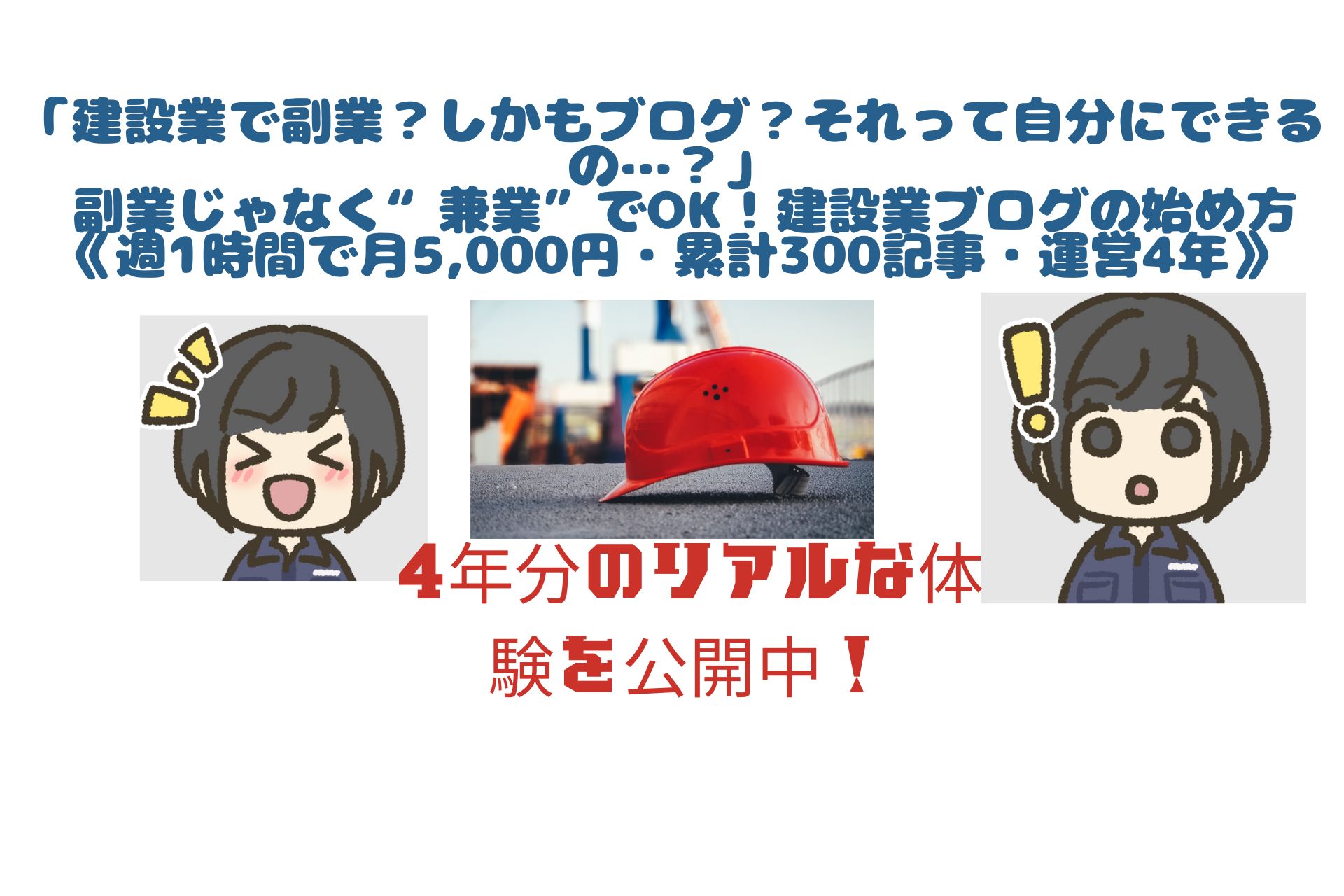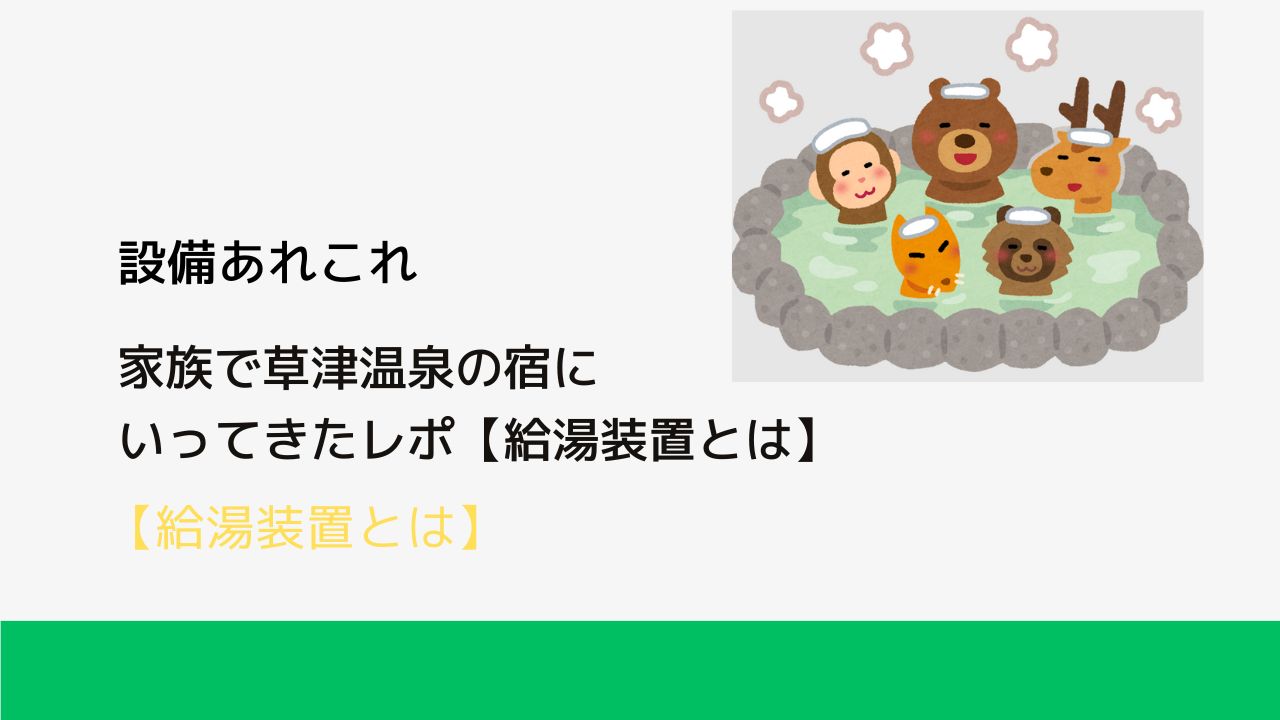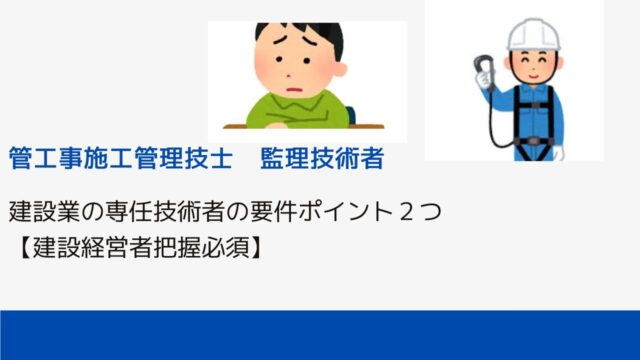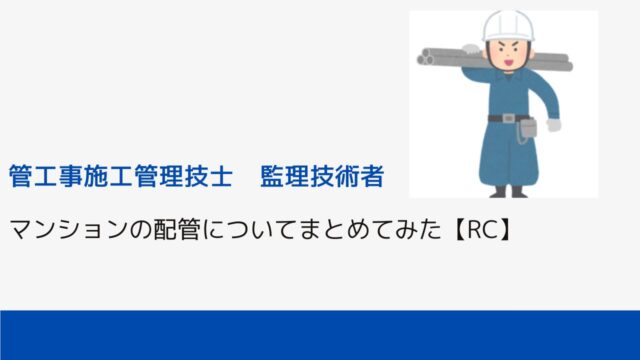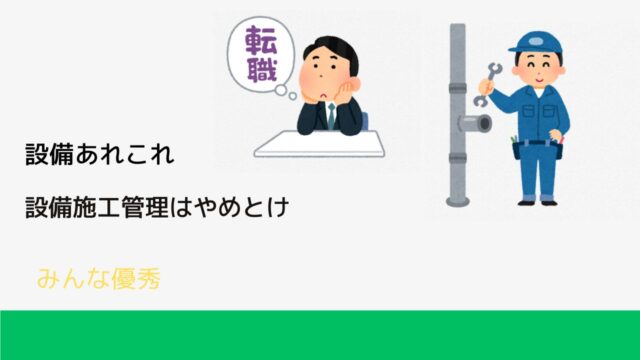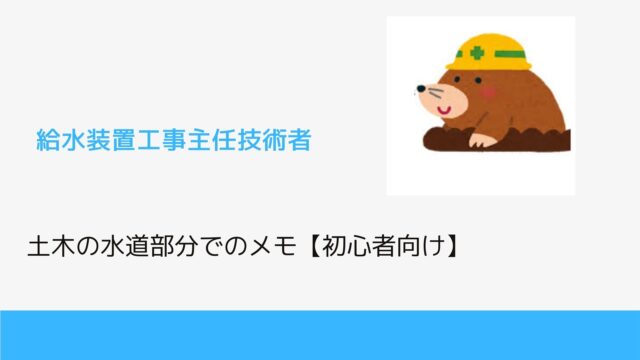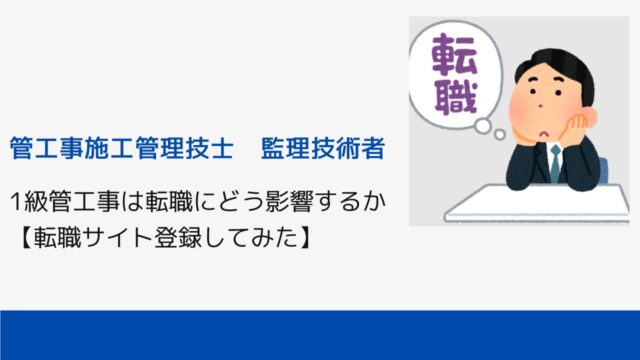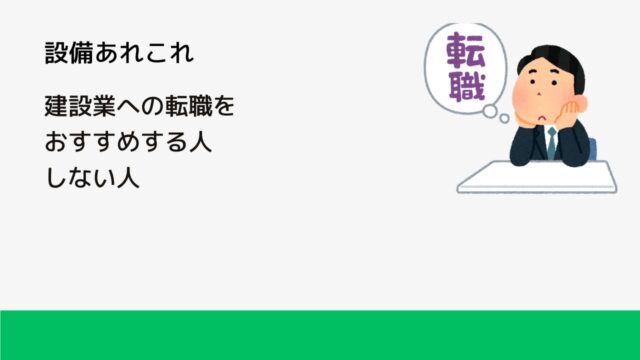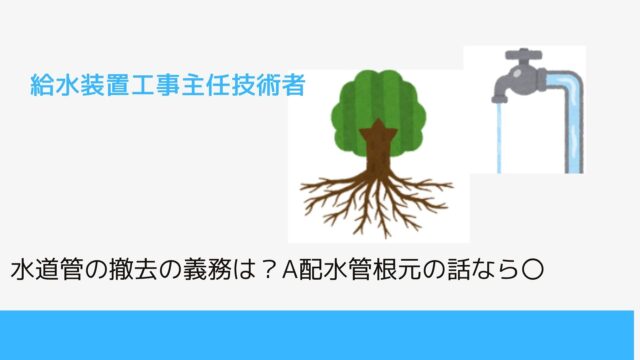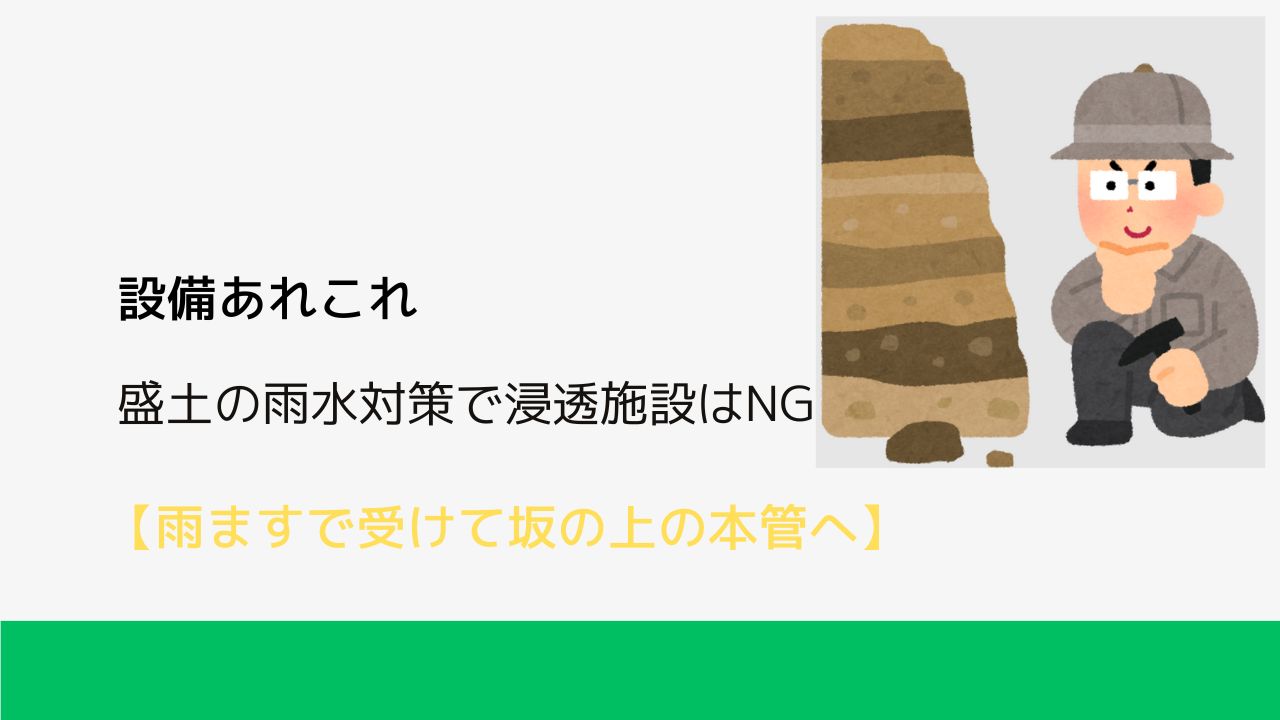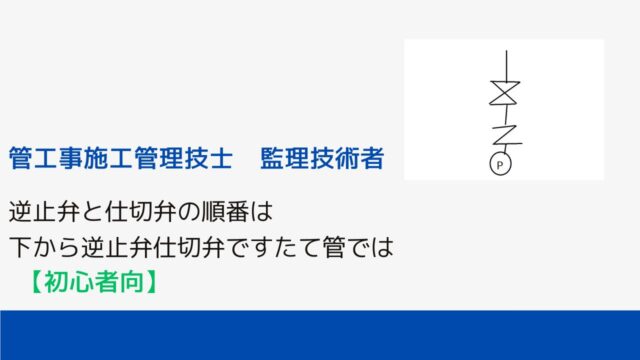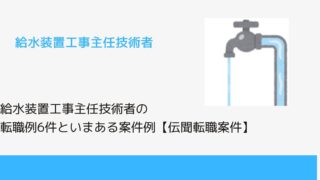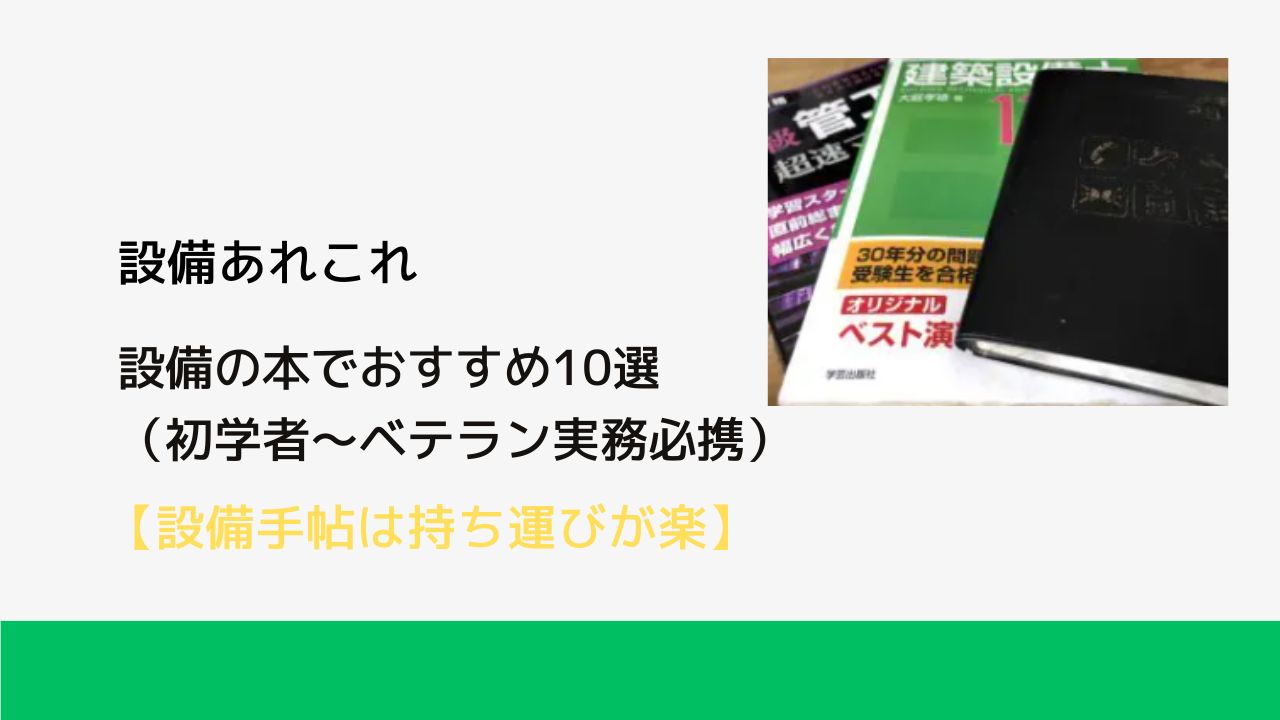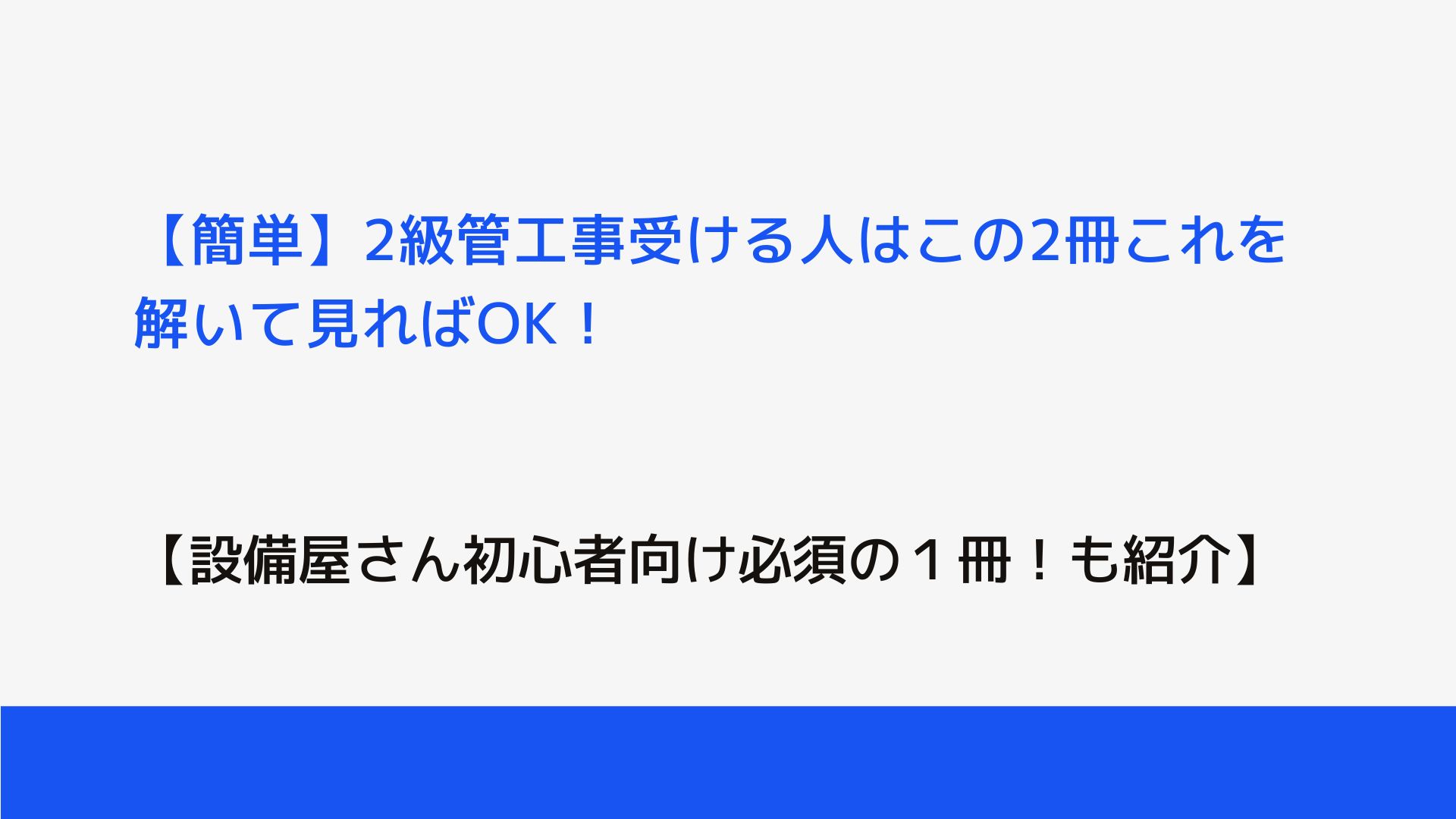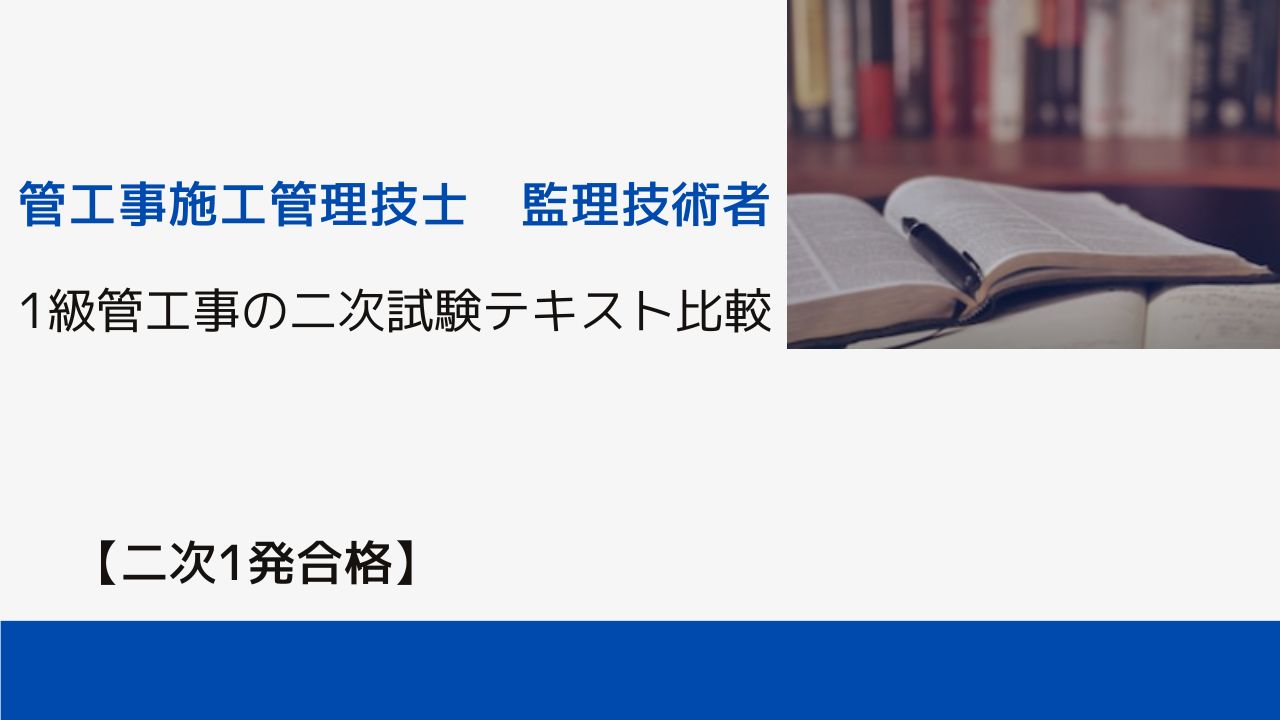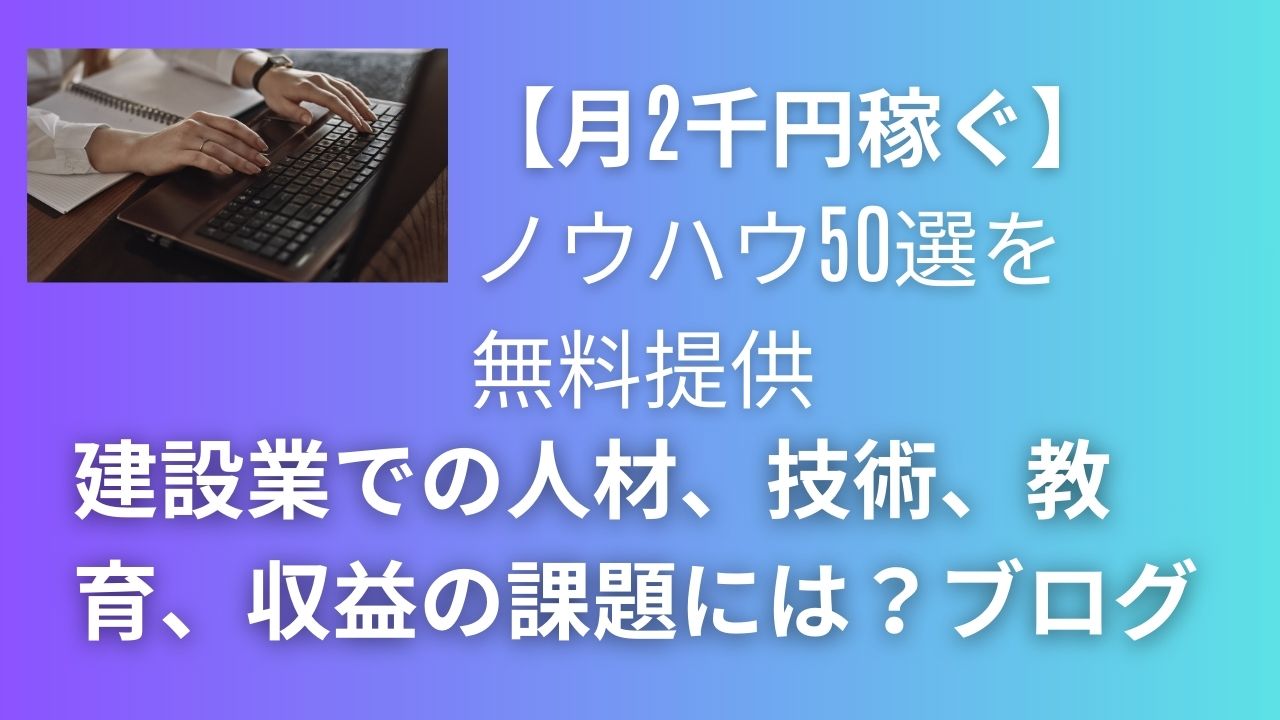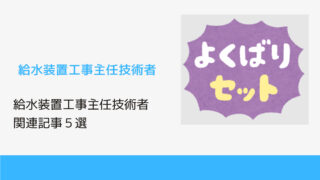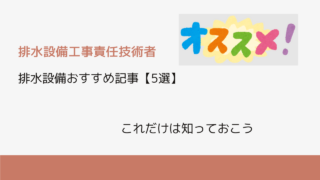私は書類作成や役所まわりが主な業務なので、正直なところ現場で拾い出しをすることはできません。
施工管理については、2人とも、あるいは3人とも、どうやって現場を回していくか日々試行錯誤しています。
そのうち1人は外注化しているので、正直言って拾い出し詳細にはほとんど関わっていないこともある様子
残りの木造中心の社内施工管理さんは、
図面と材料カタログを見ながら頭を抱えて、必死に考えています。
-
一番安いルート
-
一番効果的なルート
-
一番施工上支障のないルート
- 部材として存在するか
取り合い、収まり、それぞれの条件をもとに、図面とにらめっこしながら、材料の拾い出しを頑張ってます。
ここはもう「地味だけど本気で重要な作業」って感じです。
スタイルの良し悪しじゃなくて、
「拾い出しのコツって?」と聞かれても、
私は外から見てるだけだから、はっきり言うのは難しい。
ただ見ていて思うのは、
現場のリアルって、単に配管ルート引いて拾えばOK、なんて甘いもんじゃない。
たとえば──
適切な背関係、そのエリアごとの下水道行政のうるささ、
検査の有無や、行政の関与具合、現場の状況、MCSの排水形状…。
外流し、給湯器の排水、エアコンのドレン──
それが分流なのか合流なのか、処理方法はエリアごとに違うし、
単独浸透?オーバーに繋げてOK?NG?
一つブロックが違えば、行政の対応も処理の仕方も全然変わる。
だから、役所との連携は欠かせないし、
もちろん──見積もり部門との連携も必須。
ただね、ここでちょっと毒をひとさじ。
見積もり担当が「金しか見てない」タイプだと、ほんとしんどい。
「安く上げりゃええんやろ?」みたいなノリで拾った材料で、
現場がどうやって納めるんだって話になるわけ。
現場側としては、金額のバランスも見なきゃいけないけど、
実際に施工できなきゃ全部パーになるわけで。
その辺を理解してくれないと、話が噛み合わない。
材料がその日までに届くか?
施工性は大丈夫か?
他業者との取り合いに影響出ないか?
そもそもそのルート、本当に通るのか?
建築や設計が明日施工でも図面を送ってこないとかザラ
それを一つひとつ現場目線で確認して、ようやく形にしていくんだよね。
なのに机上で「ここ削ろう」「こっちのルートのほうが安いやろ」って、
安易に削ってくる見積もり担当、ほんと勘弁してほしい。
拾い出しに限らず、ルートが変われば材料が変わるのは当たり前。
建物の構造で、配管の可否がまるで変わってくる。
一生懸命考えて、汗かいて拾い出しても、
現場で「これは無理です」って職人さんに言われることもある。
それでも、そこから再検討して納めていくわけ。
建築との連携、構造との整合性、
「どこが通るか?」「構造上問題はないか?」
後で「ここ構造NGだから全部やり直して」なんて言われたら、誰が責任取るの?って話。
外構の施工ができなかった場合の処理ルート、
初期段階からかなりの検討が求められるし、
それは単に「設備だけわかってりゃいい」って話じゃない。
基礎からどれだけ深さを取るか、
仕上がりが未定な中で、適当な逆勾配で配管なんて当然NG。
だからこそ、慎重に検討するし、材料の選定も含めてしっかりやってる。
結局のところ──
「コツ」って言葉で片づけるのは簡単だけど、実際は経験と想像力。
現場の空気を知らずに「金でしか判断しない」見積もりと違って、
現場管理はリアルな判断力と責任感の連続です。
横で見ていても、ほんと頭が下がる思いだよ。
見積もり担当がザックリと「このくらいっしょ?」で数字を出して、
現場がその通りにやらされる構図って、ホント地獄。
見積もりと仕込み(実際の施工準備)は、まるで別次元ってこと、
もっと多くの人に伝わってほしいなと思います。
拾い出しどころか、配管ルートの初期検討で
建築側に助言してるのがこっちっていう、ねじれた構図が生まれる。
それでも、こっちは文句も言わずに(たまには言うけど)、
見積もり部門との連携、行政との交渉、施工班との調整を地道にこなしてる。
見積もり担当はといえば、相変わらず金額しか見てない。
「これ、ちょっと高くない?削れない?」とか言ってくるけど、
その“ちょっと削った”せいで、現場がどんだけリカバリーしてるか知らんのかいと。
設備だけじゃなくて建築にも精通してるからこそ、拾えるものがある。
でもそれって、努力してきたからできるんであって、
適当に拾って「現場でなんとかして」なんてのとは訳が違う。
全体を見て、建築側との調整も見積もり部門の暴走(?)もにらみつつ、
「配管職人さんが現場で苦労しないように」って願いながら拾い出ししてる。
で、ここで知っておいてほしいのが、
**「配管技能士」**っていう国家資格。
厚生労働省が所管してる技能検定制度の一つで、
都道府県単位で試験が実施されてるんだけど、
この資格、技能だけじゃなくて、施工図面の理解や法令知識まで問われるの。
だから実は、
「現場の拾い出し、よくわからん…」ってなってる若手監督や職人さんにも、
めちゃくちゃ学びになる制度なのよ。
が拾い出ししてるときも、
この技能士的な視点──「どう通すか」「どう納めるか」「法的にOKか」っていうのが
ベースにあるから、現場の無駄をどれだけ減らしてるかって話。
でもそれを知らずに、
「適当に見積もっといて!あとは現場でどうにかなるっしょ!」とか言ってくる
金しか見てない某見積もり担当さん(誰とは言わないけど)、
一回技能士試験受けてみたらどうですかって、ね。
現場って、そんな「とりあえず」で回るもんじゃないのよ。
一つのバルブが高い理由、勾配がどうしてそこじゃないといけないか、
それ全部、拾い出しの段階で見えてないと、配管屋さんが地獄を見る。
だからは、
代理人の立場でも、現場がスムーズにいくように頭を使って、
公的な情報も、技能制度も、できる限りみんなに広めたいって思ってるの。
苦労する職人さんが一人でも減るように。
「拾い出しなんて簡単っしょ」って思ってる人、
それは単なる数量カウントだと思ってるんだろうけど、
それ、違うから。
拾い出しは未来を読む作業。現場の温度と流れを見通す力。
そしてその技術力を、国や都道府県の制度が支えてくれてる。
だったら、使わない手はないわよね。
手順で解説してみた
配管拾い出しの手順と重要ポイント:設備施工のプロフェッショナルガイド
配管工事を成功させるためには、正確な「拾い出し」作業が不可欠です。この記事では、配管拾い出しの基本的な手順からプロフェッショナルが押さえるべきポイントまで、実践的なノウハウをご紹介します。
配管拾い出し手順
1. 図面の入手と確認
- 設計図面(建築図・設備図・構造図)をすべて入手する
- 特に設備図がない場合は、建築図から必要情報を読み取る
- 配置図も含め、すべての関連図面を確保する
- 図面の縮尺や寸法を確認し、実際の施工との整合性を確認する
2. 現場確認の実施
- 実際の現場状況と図面との相違点を確認する
- 配管ルートの障害物や干渉物を特定する
- 現場の寸法を実測し、図面との整合性を確保する
- 施工条件(狭小地、アクセス制限など)を把握する
3. 建築担当者とのコミュニケーション
- 壁内・床下の配管スペースについて確認する
- 配管の出口位置(壁から出すか床から出すか)を明確にする
- 仕上げ材の厚みと衛生器具の取り合いを確認する
- 建築工程との調整を行い、配管施工のタイミングを決定する
4. 材料の選定と発注準備
- 材料カタログを参照し、最適な配管材料を選定する
- 材料屋に在庫状況や納期を確認する
- 代替材料のオプションも検討しておく
- 数量を正確に算出し、余裕分も含めて準備する
5. 建築構造に合わせた計画立案
- 木造建築、鉄骨建築、RC建築それぞれの特性を理解する
- 構造体への影響を最小限に抑える配管ルートを計画する
- スリーブ位置や貫通部の処理方法を検討する
- 各構造特有の施工上の注意点を把握する
6. 外構設備計画の確認
- 基礎との関係性を明確にする
- 配管の引き込み・引き出し位置を確定する
- 外構工事担当者と施工順序や取り合いを協議する
- 埋設深さや保護方法を決定する
7. 衛生器具位置の正確な把握
- 器具の取付寸法を確認する
- 給排水接続位置と高さを明確にする
- 仕上げ面を基準とした配管位置を計算する
- 設備図がない場合は、建築図から推測し確認する
8. 専門用語の理解と活用
- 設備、建築、構造それぞれの専門用語を理解する
- 関係者とのコミュニケーションに適切な用語を使用する
- 図面表記や略語の意味を正確に把握する
- 業界標準の呼称や単位を適切に使用する
配管拾い出し作業は、プロジェクト全体の成功を左右する重要なプロセスです。図面の理解から現場確認、関係者とのコミュニケーション、適切な材料選定まで、多くの要素が絡み合います。特に設備図がない木造住宅などの現場では、建築図からの読み取りと現場確認がより重要になります。
日々の業務の中でカタログや図面に親しみ、様々な建築構造に対する理解を深めることが、配管拾い出しのスキルアップにつながります。また、建築担当者や外構工事担当者との円滑なコミュニケーションを心がけ、プロジェクト全体の流れを把握することも大切です。
適切な配管拾い出しによって、後工程でのやり直しが減り、コスト削減と工期短縮につながります。本記事の手順を参考に、より効率的で精度の高い配管拾い出しを実現してください。
メーカーカタログはスマホで無料でみれますし、
下のリンクの設備関連本で
べからず集とか
建築の小さい本買っとくと勉強になって
やりとり楽ですよー
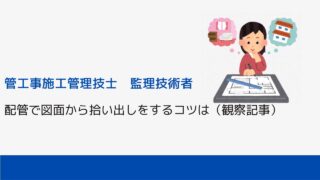
関連記事です