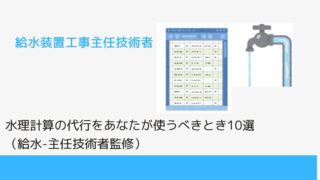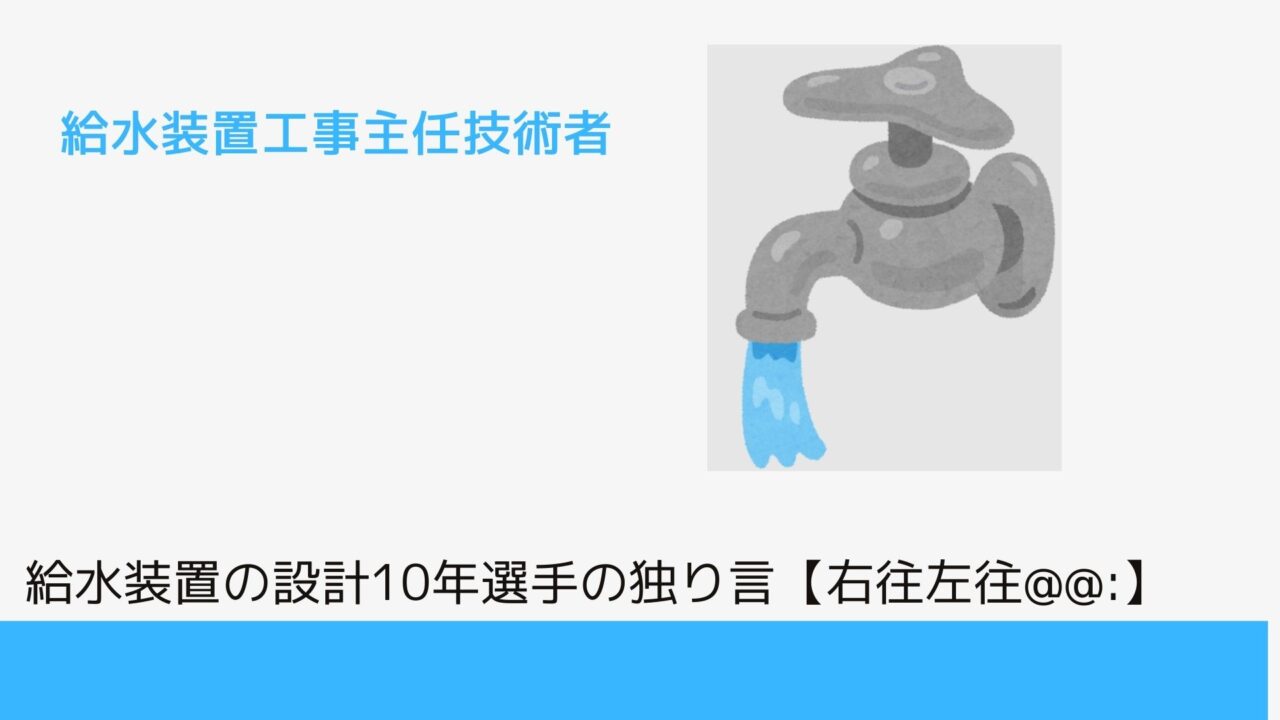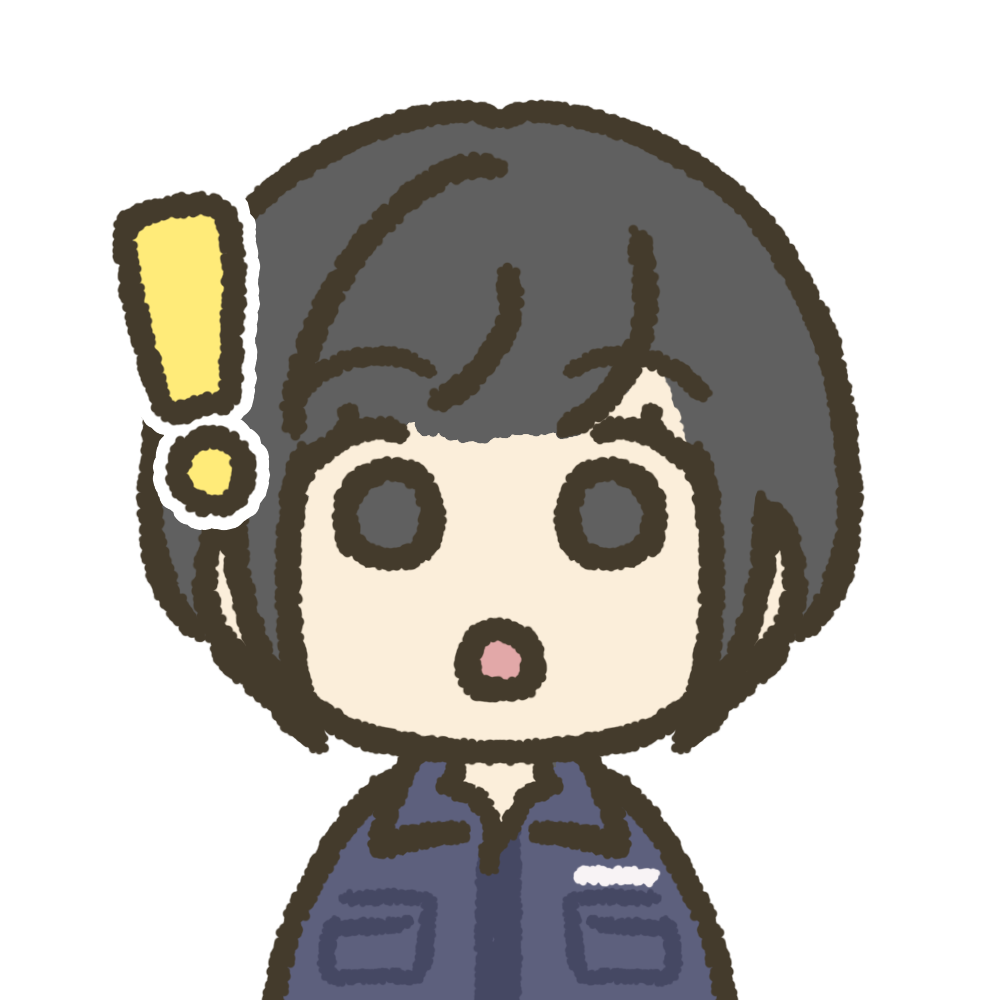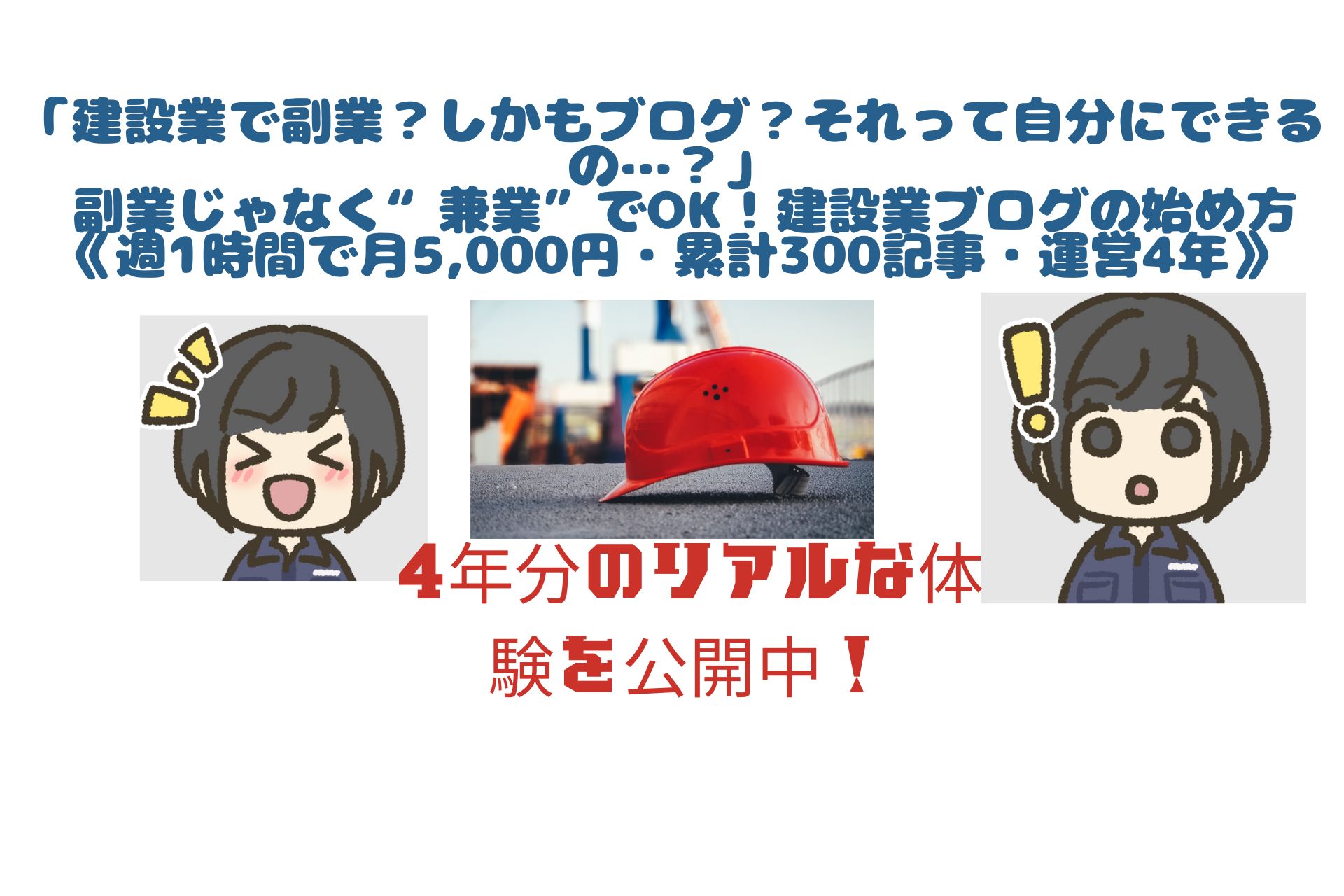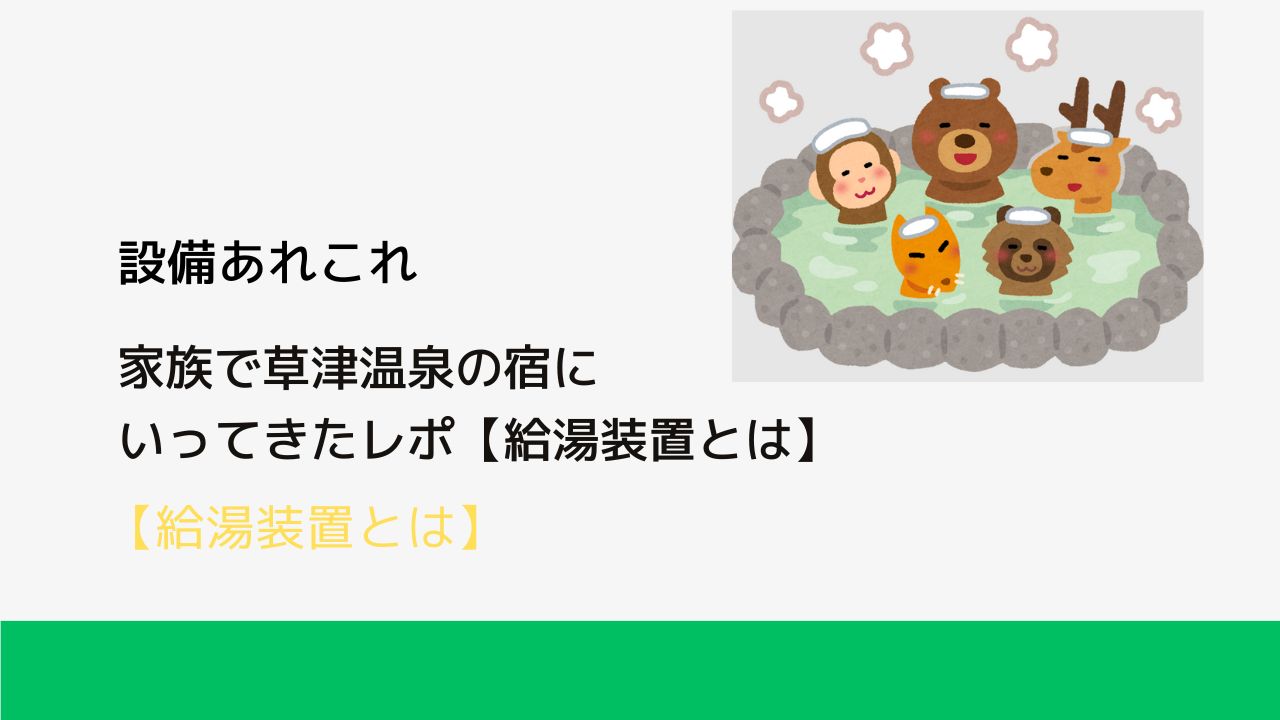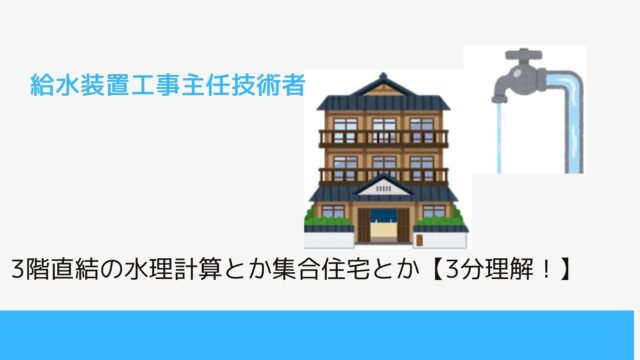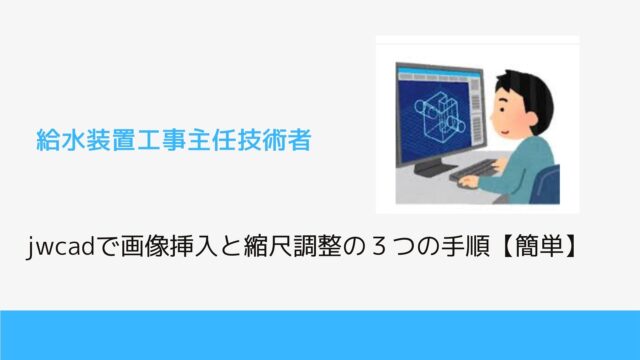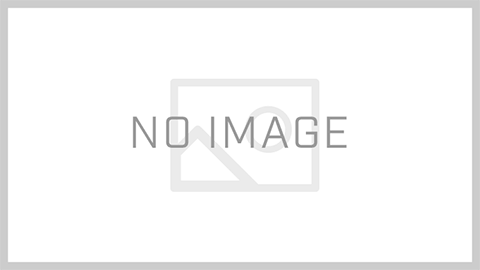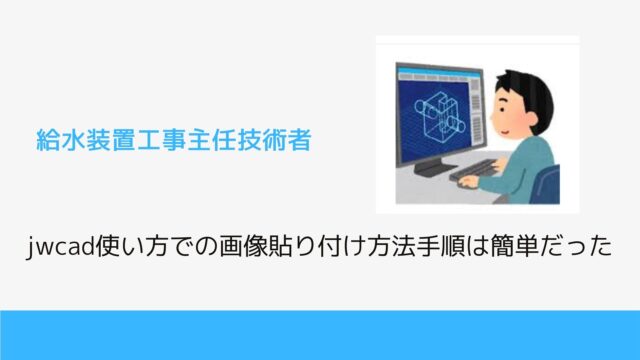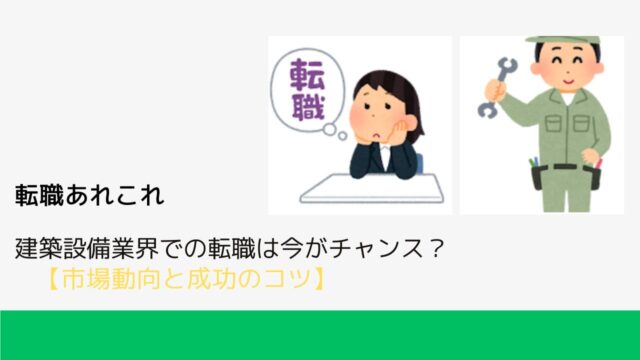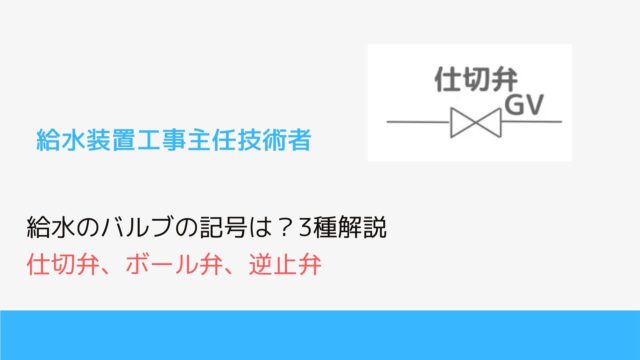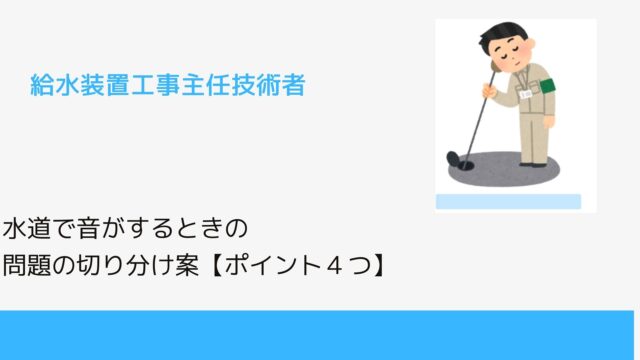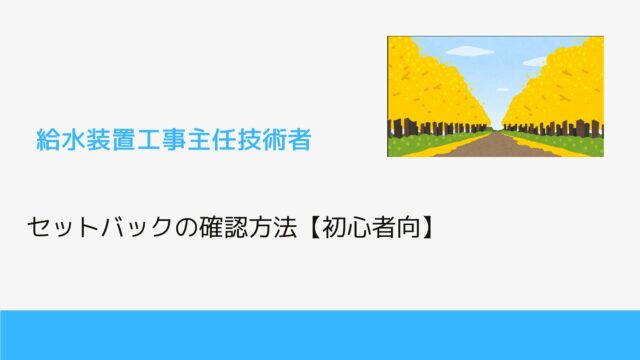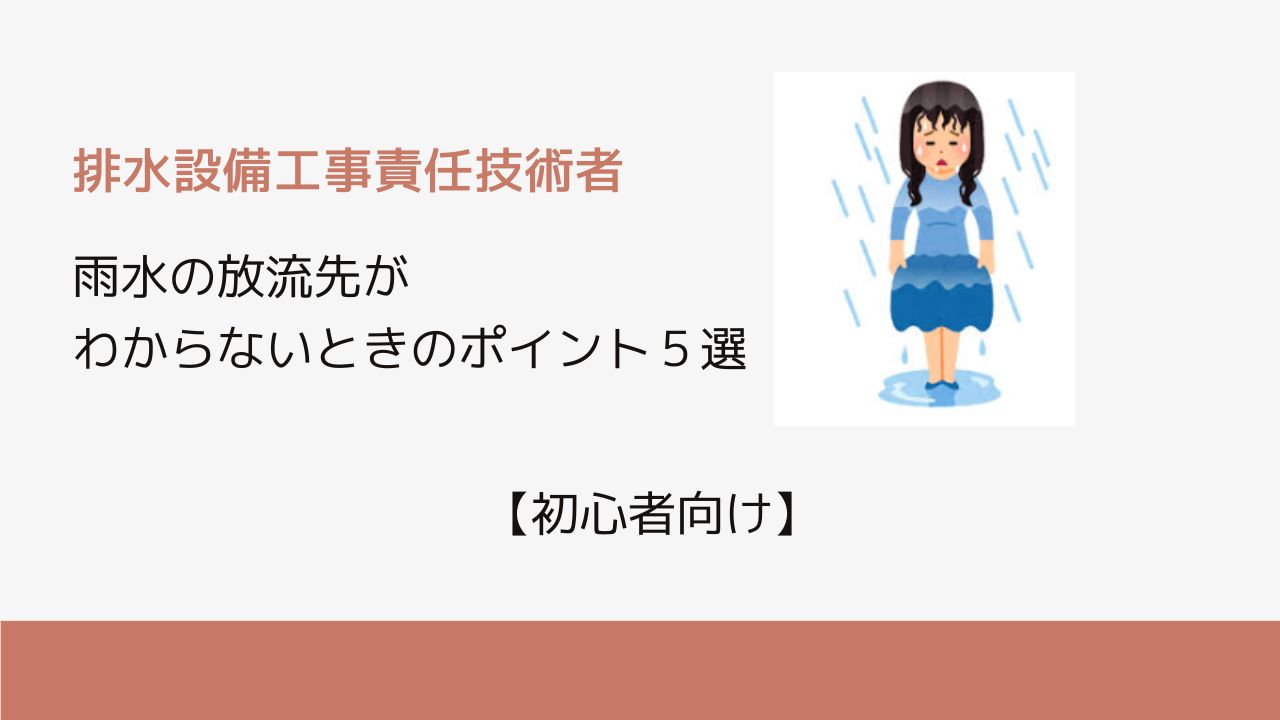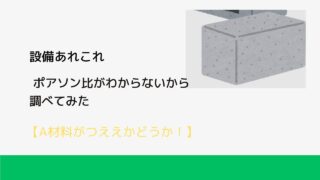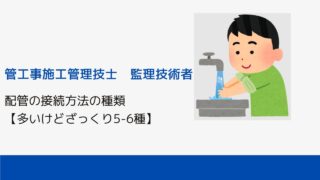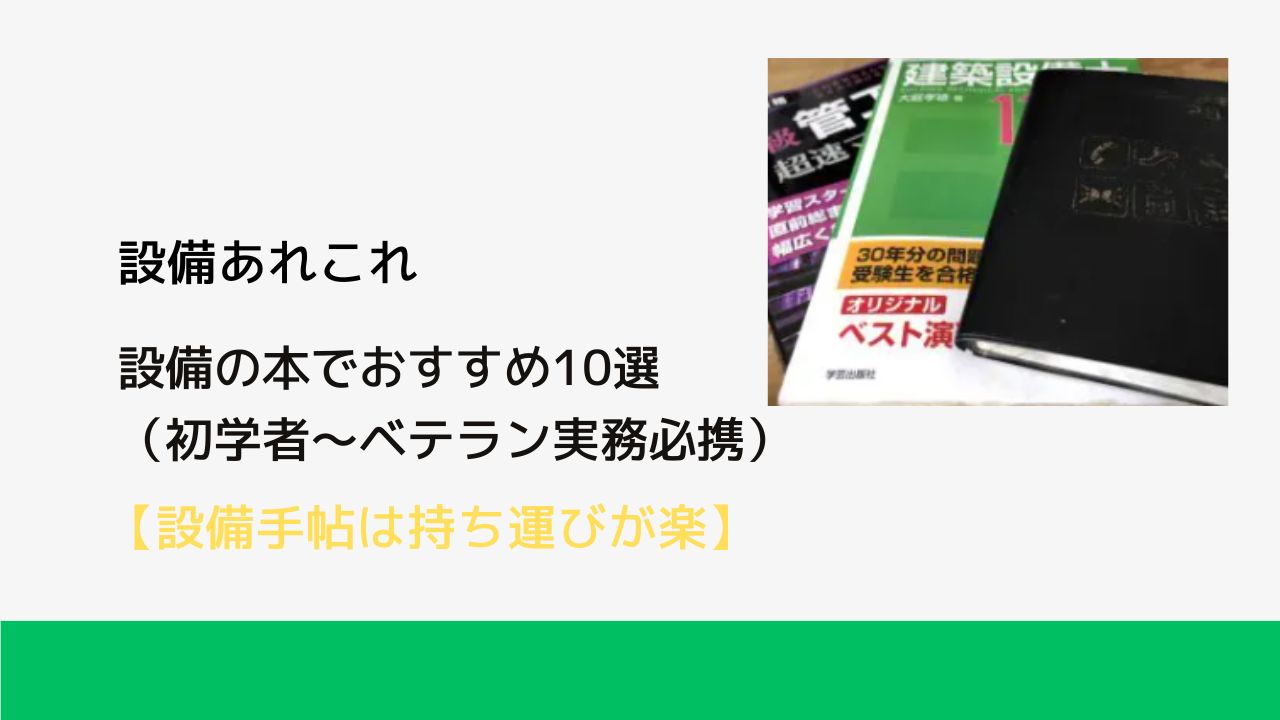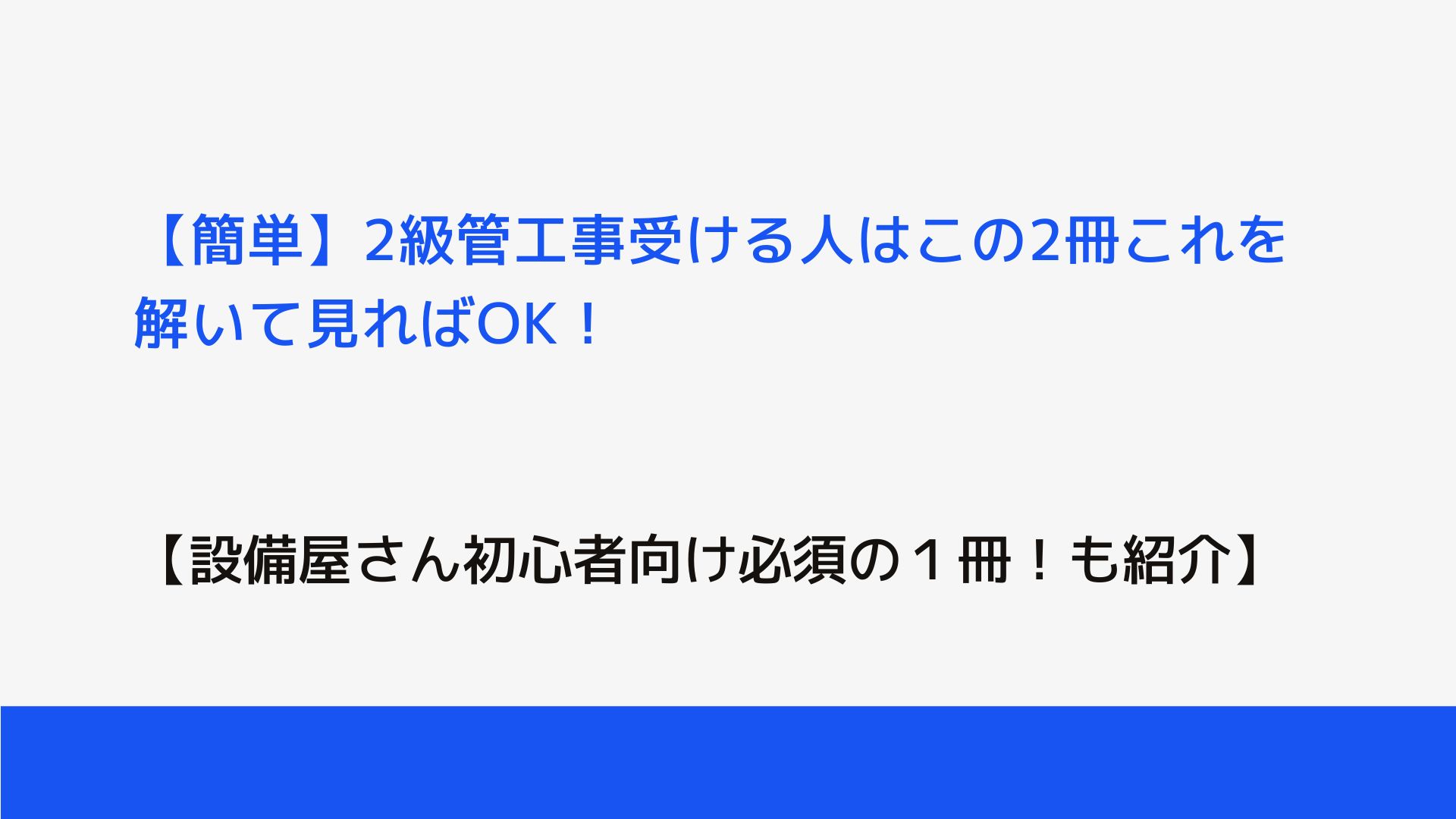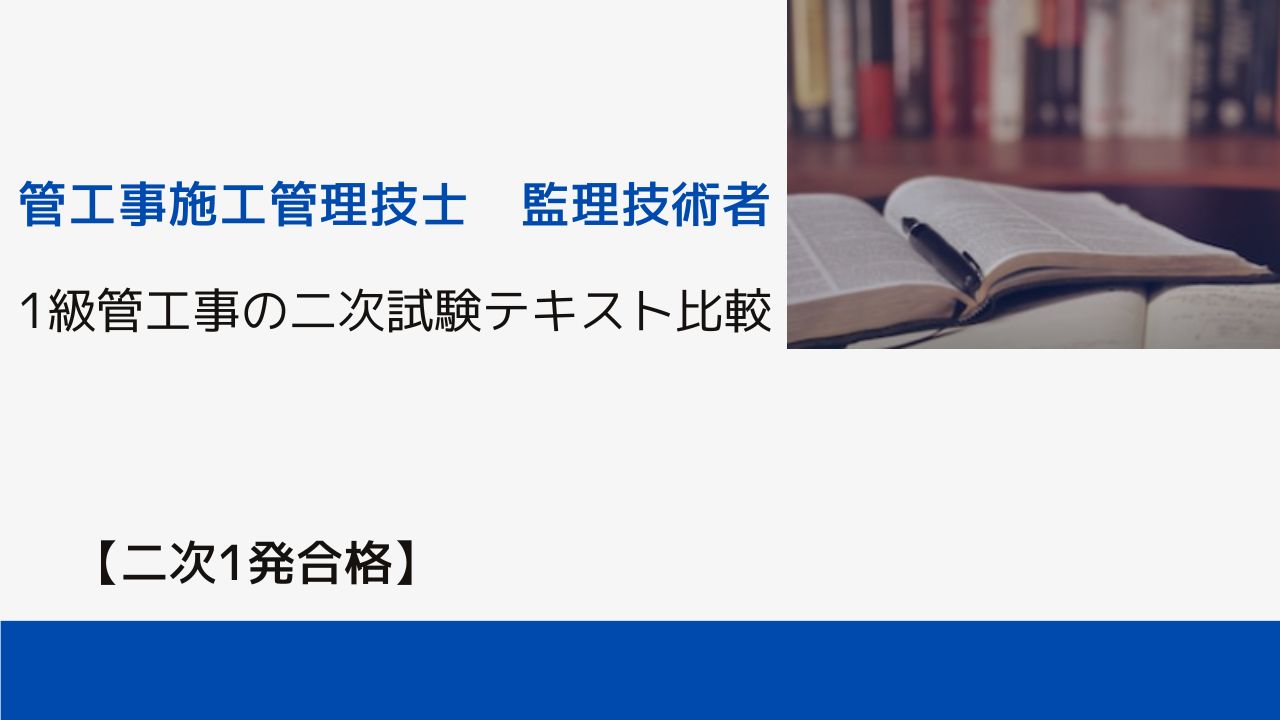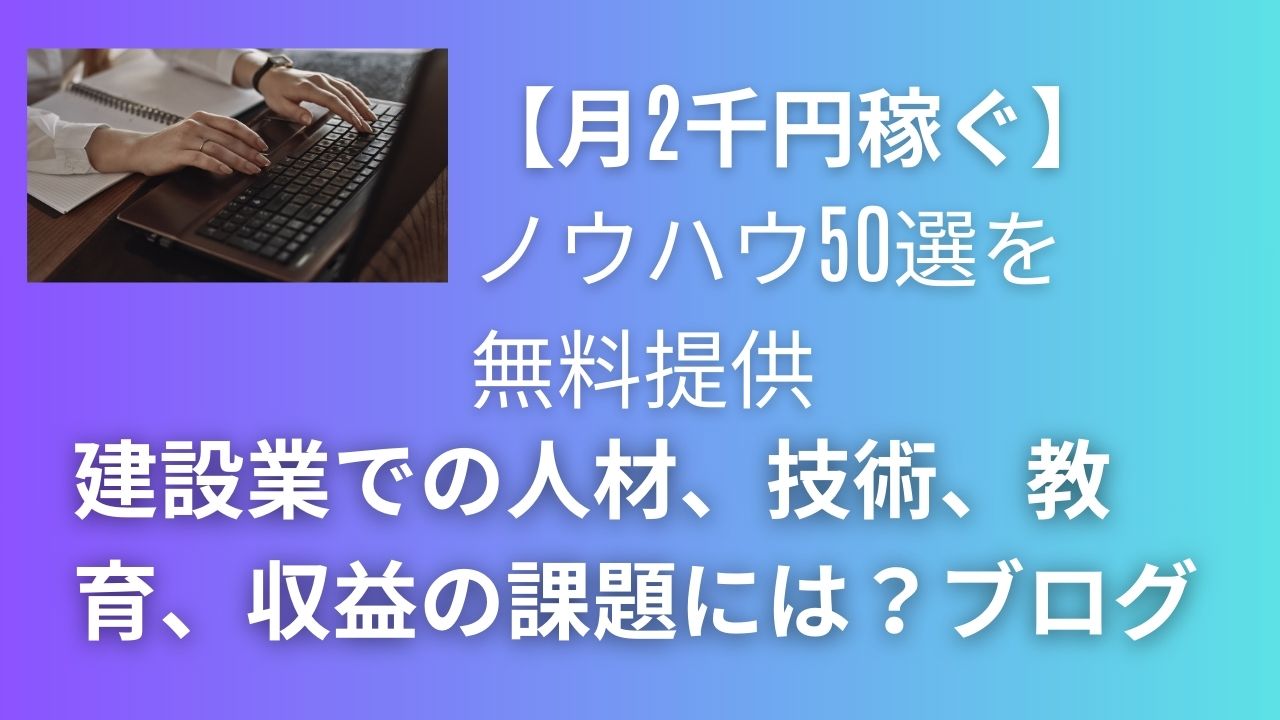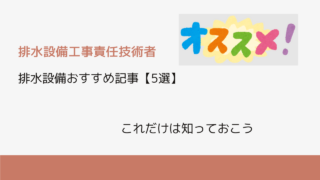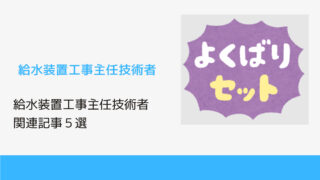という方向けへの記事となります。
はじめに結論
この記事では
- 水道局の人の設計を眺めてただけの人の意見が聞ける
- まあまあ指摘されたことがまとめて聞ける
なんか似た突っ込み受けるなーというポイントがわかる
本記事の内容
- 考え方は4つだけ水質水圧水量維持管理
- 水道事業者毎のメータ材質と工法出庫ルール
- 公費自費範囲と出来ないこと出来ることの把握
考え方は4つだけ水質水圧水量維持管理
- 水質
- 水圧
- 水量
- 維持管理
上の4つです、そのうち3つは教科書通り、1つは持論というかだいたいそれ!
という部分です。
水質確保の確認
上の4つのうち3つは
教科書通りなんですが、
指定給水装置工事事業者とまで
往生なネーミングなので
へんちくりんな図面は持ってこない
のでそこまで気にしないでもなんですが、
配管付きあたりに器具なしでバルブ止め
だと
滞留水(停滞水、死水)が発生
するので水質の観点から
ダメですよ、器具つけましょうね
とかですかねー。
- 水道局→水道事業者
- そのエリアで指定を受けている水道者→指定給水装置事業者
となります。
指定給水装置工事事業者には指定給水装置工事主任技術者が1人いますので役所向けの工事には大体地場の水道屋さんの出番があります
よく店舗とか、
C工事だから!とか
うちは関係ない!
とかあるんですが、
そういう方にはやさしく
うーんまだ強いな、
蛇口ないと申請受けれないんですよね
で、なんでやねん!な人には
水質確保の観点からお受けしていないんですよね
とか、それでもだめなら
給水装置工事主任技術者の方かその指定給水装置工事事業者の水道屋さんにご相談ください
と、かわして逃げちゃうか、ガチ返答で
末端給水用具の設置は法律で決められているからです
とガチ返答するかですが、まあその手の人は理解がないか
お勉強不足の水道屋さんか、利だしに命をかけているひとなので
優しくしてあげてください(内心スルーでおっけ)
と指定事業者でない
- 施工管理さん
- 設計屋さん
- 不動産屋さん
- オーナーさん
- 建築さん
なとにはやさしく教えてあげましょう
県とか国の施設の人には立ち上がって笑顔で対応しましょう
→役所縦割りめんどくさい対応が多いようですから、早めに火種は消すことです
市民の方からのお電話対応もそうですが
市議とはなしたんだが!とか市議様からお電話です!
なども役所あるあるなので、上役と連絡と報告をしながら
対応するといいでしょう、(知りませんが)
関連記事になります。
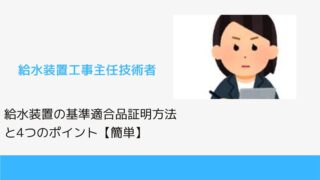
- 耐圧
- 逆流
- 浸出
など難しい言葉が多いですが
ベースは水質の確保だと考えたら
多少は楽かと思います。
- 配管が高圧力により壊れて異物が入ってしまうこと予防→耐圧
- 配管がガソリンなどで汚染されることを予防→浸出
- 配管内の水が逆流して汚染されてしまうことを予防→逆流防止
- 配管がウォーターハンマーにより壊れて汚染されてしまうことを予防→水撃防止
となります。
まあ、いきなり全部理解するのは厳しいですが
〇〇の観点から水質を確保できない恐れがあるため
となります。
- 高層階での長い横引き水撃→配管ルート変更、水撃防止器具
- ガソリンスタンドでの樹脂管などの使用による浸出→管種、ルートの変更
- 受水槽方式から変更後の配管の逆流→逆止弁
- 負圧による(多層階)逆流→逆止弁、給排気弁
- 不特定多数が使用する工事現場での逆流→逆止弁
- 不特定多数が使用する公園などでの逆流→逆止弁
- 配水管近隣水圧が高いエリアでの耐圧→減圧弁
- 増圧低層階での水圧が高いエリアでの耐圧→減圧弁
- 指摘事項レベルで話題に出たら会社で周知する(主任技術者へ)
- 申請時必須レベルは社内主任技術者に確認の上再度申請図を出しなおします
というときはあります。
絶対全部やれ!なにがなんでも!
となると、水道屋は利益が出せずに潰れます。
かと言って、なんでもいいやだと、水道局も維持管理に予算をたくさん出すのが当たりまえになります。
利害は双方にありますが、
使用者の視点を忘れずに
という部分です。
なので、双方いや3方で理解の上で、施工の規定が水道事業者にありますから
だいたいそれに従います。
検査員さんによるところも多いので、見解が分かれるときもある
と理解しておくといいでしょう
まあお気楽に
まあ、マニュアルあるんでしょうから、目は通して業者に恨まれない範囲で
御周知事項は逃げ口上で伝えといて、上に書類であれこれ言われない範囲で
頑張り、たとえ言われたとしても、あっそ、そういう仕事だものね、お疲れ
とサクサクこなす。
しかないのでは
水圧の確保
水圧を確保できるか?
当該エリアの水圧は?
当該水道事業者の設計可能水圧は?
設計図における
- 用途
- 世帯数
- 階高
- 給水方式は妥当か
- 水圧確保出来る
- 同時使用を加味した設計になっているか?
- 近隣水圧の協議や調査の確認
- 水量の確認
水量が確保出来ているから
同時に使う時の
水圧も確保される
水量と言わずに言い換えたら
菅の太さ大≒水量大
と考えると楽かもしれません。
同時にたくさんの蛇口で水を使うには太い菅がいる=水量
となります。
んで、実務では
- 用途(住宅か否か)
- 1世帯
- 2世帯
- 3世帯
- 4-9世帯
- それ以上
- 高さ
- 2-3階
- 天井配管か否か
- 4階以上
- 増圧ポンプの有無
- 受水槽の有無
- 住宅ならだいたいこれでいいけど
店舗なら?
医療施設なら?
事務所なら?
と、イレギュラーパターンもあります。
0.17-0.74MPaが配水管の水圧という規定がある
その中で、自分の水道事業者はだいたいなんぼの水圧が確保されているのか?
また、だいたい給水管<配水管の
部署の力関係もあったりするので、
その水道事業者の上の方の言い分、
水道監理技術者資格保有者(何十万も試験に金かかる)受けている人は
漏水の防止という観点だけでものを見ていたりする。
水道屋と水道局は利益相反の関係の部分も多い
- 水道局→引き渡し後の維持管理費用(役所なので予算制限がある)
- 水道屋→引き渡しまでの費用(事業者なので利益出し続けないといけない)
両方とも使う人にとっては大切な部分なので適切な歩み寄りは大切
その実、相手にする水道屋は戸建てだけならいいけど
ガチの大きい建物を建てているゼネコンやその中や外の設計屋たちは
施主からしっかり引っ張ってきつつ、うまく節約もしてますよ!アピを
盛り込んだりしている。
設計というより巧な営業マンだったりする。
それは、施主の次世代への相続関連で、文筆を将来に見据えて
1つの宅地に複数の棟を立てて、各々の建物毎に複数の給水管を引き込む計画だったり、
都心の一等地にどうみても不要な径での引き込みを設計してみたり
ちょっとねー!というものも多いのが現実。
設備設計上は給水管はできるだけ太く配管し、
水量水圧を確保しようとするが、
一部の水道事業者は、責任分界点である、量水器をできるだけ
官民境界直近に設置をするよう設計者に圧力をかける
どうも、その水道屋と配水管屋の綱引きの間に立つことも覚悟しておくといいでしょう。
まあね、そうですね、とダブルスパイのように、こっちでこういいい
あっちでこういいと、適当に合わせておく能力は必須である。