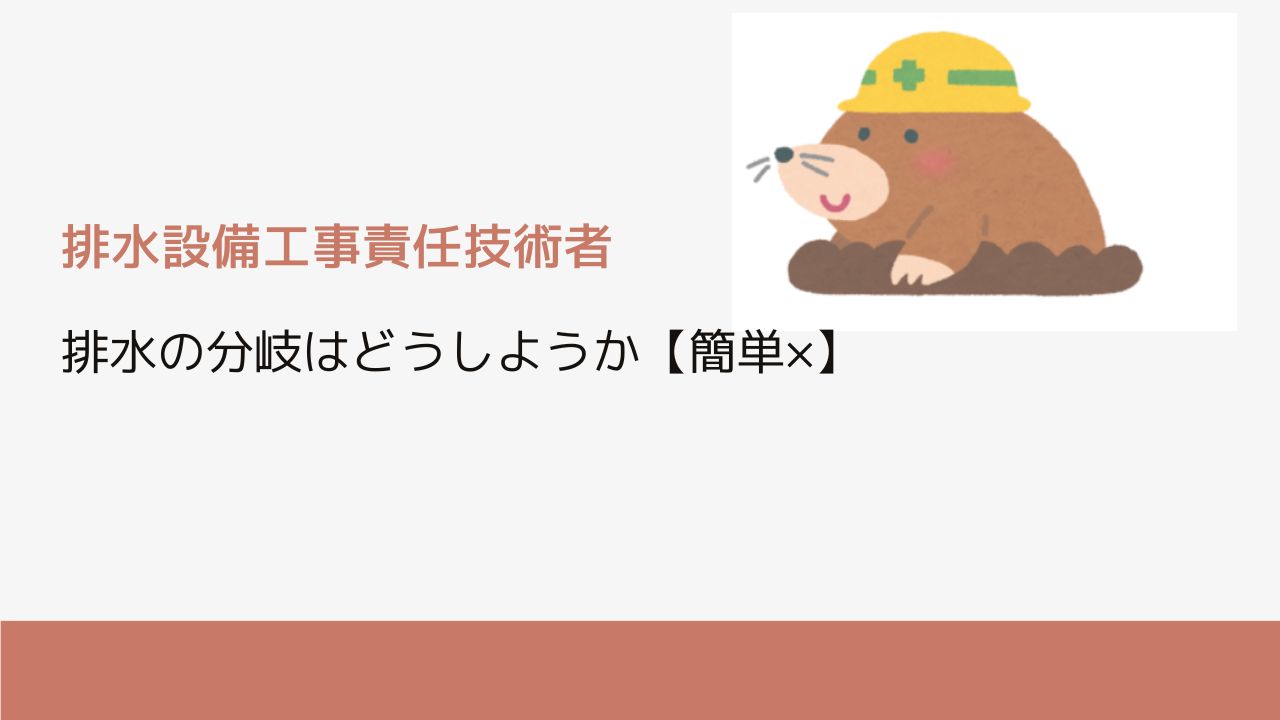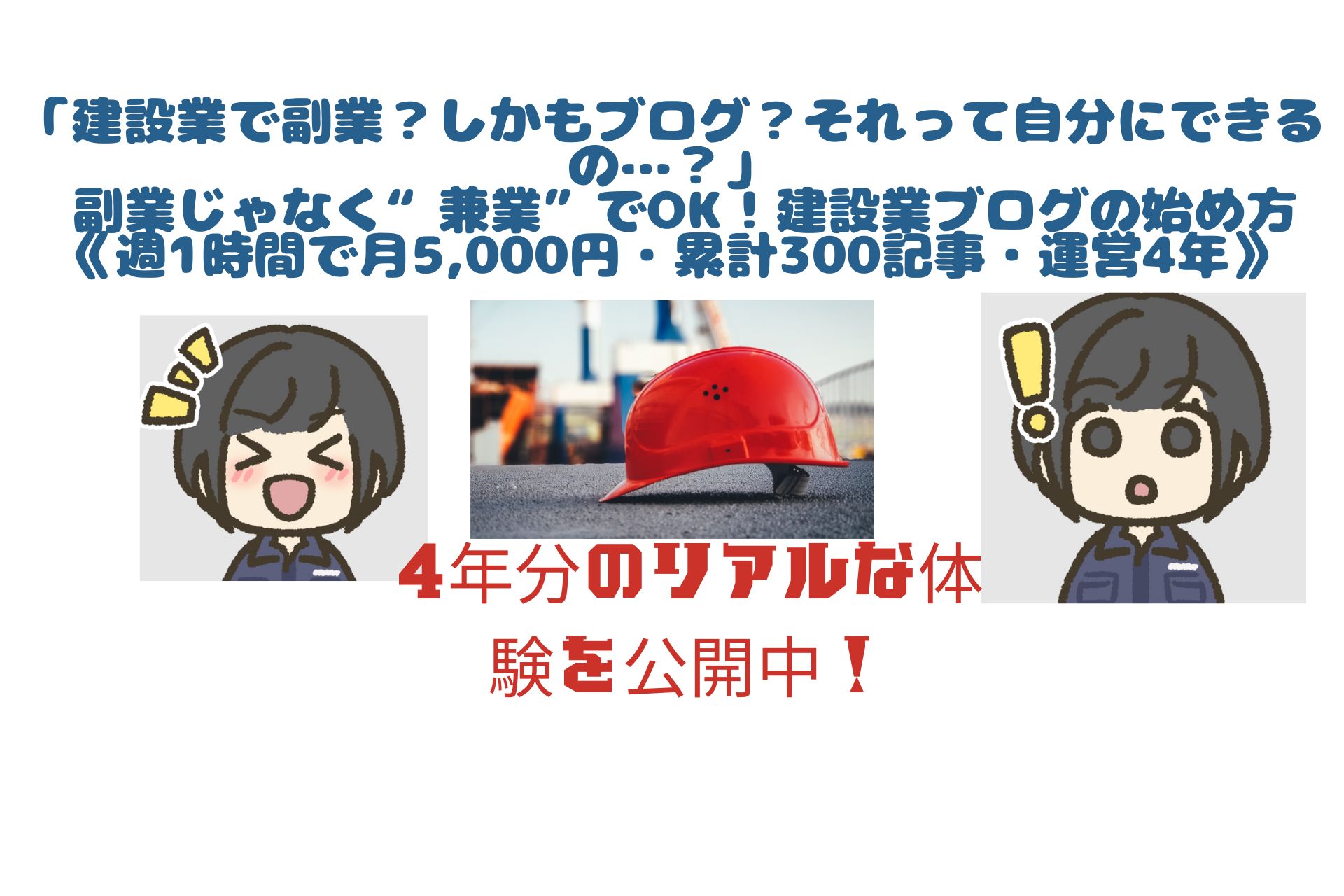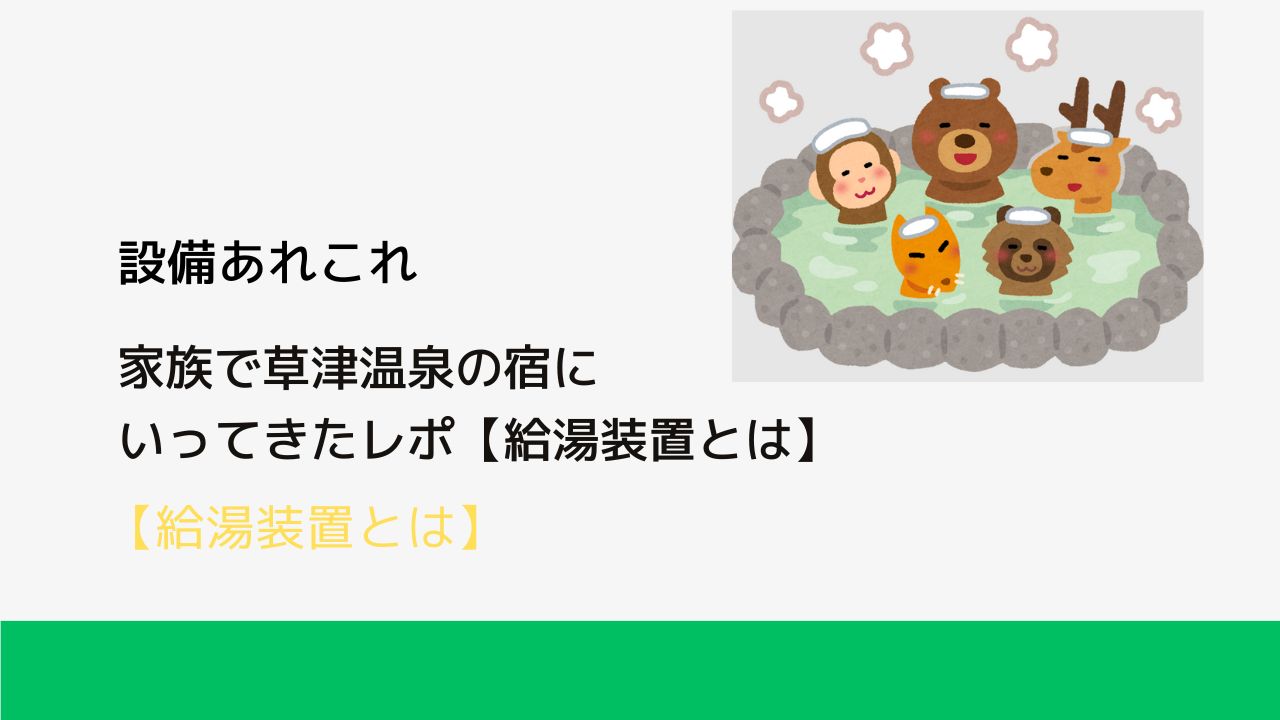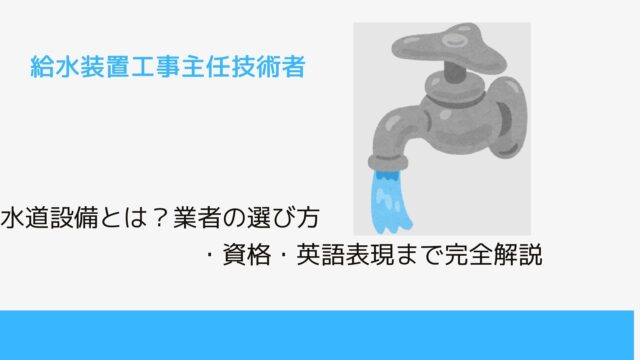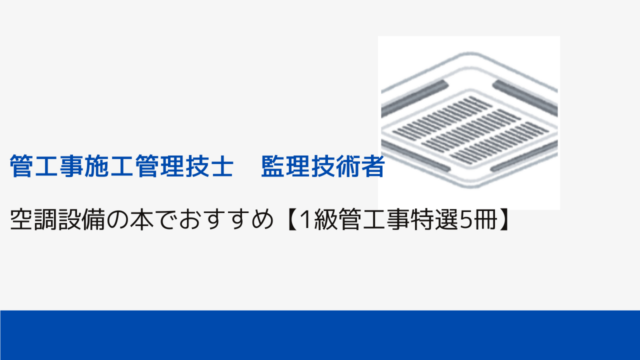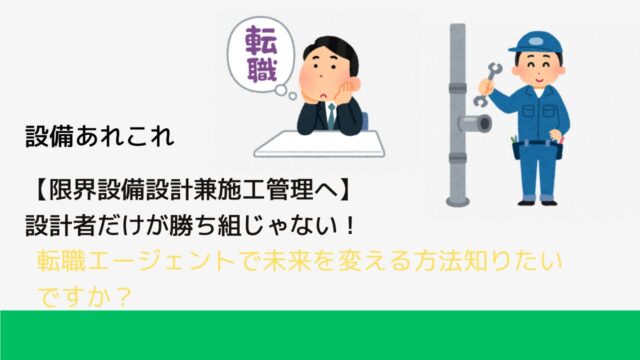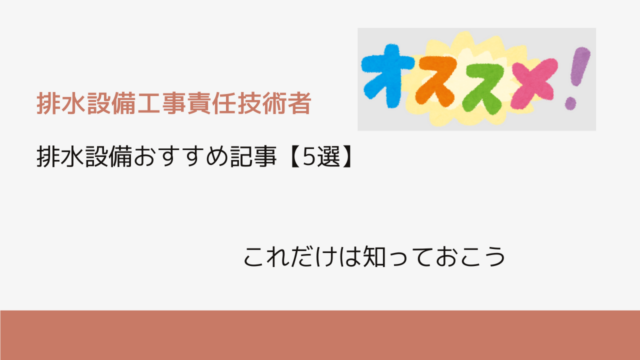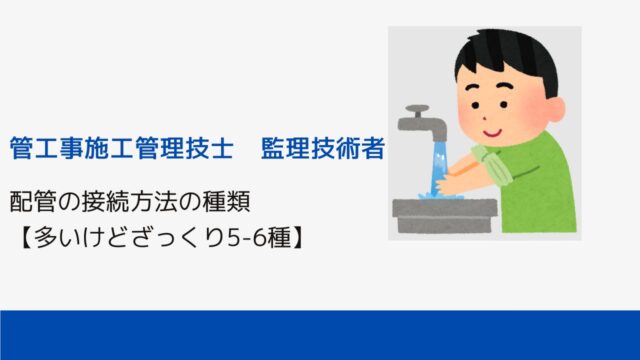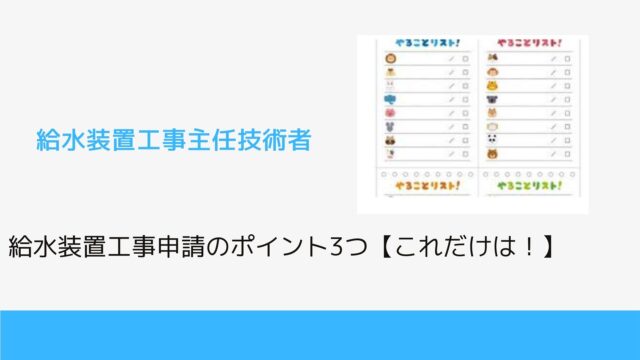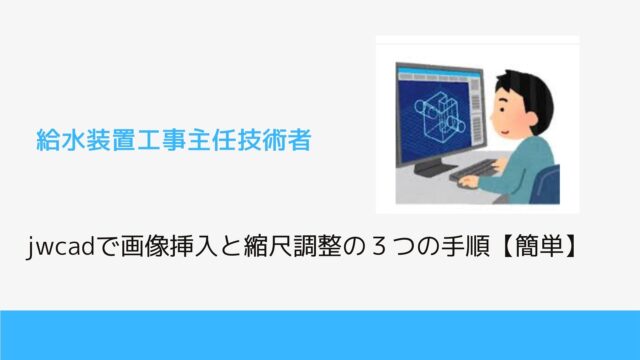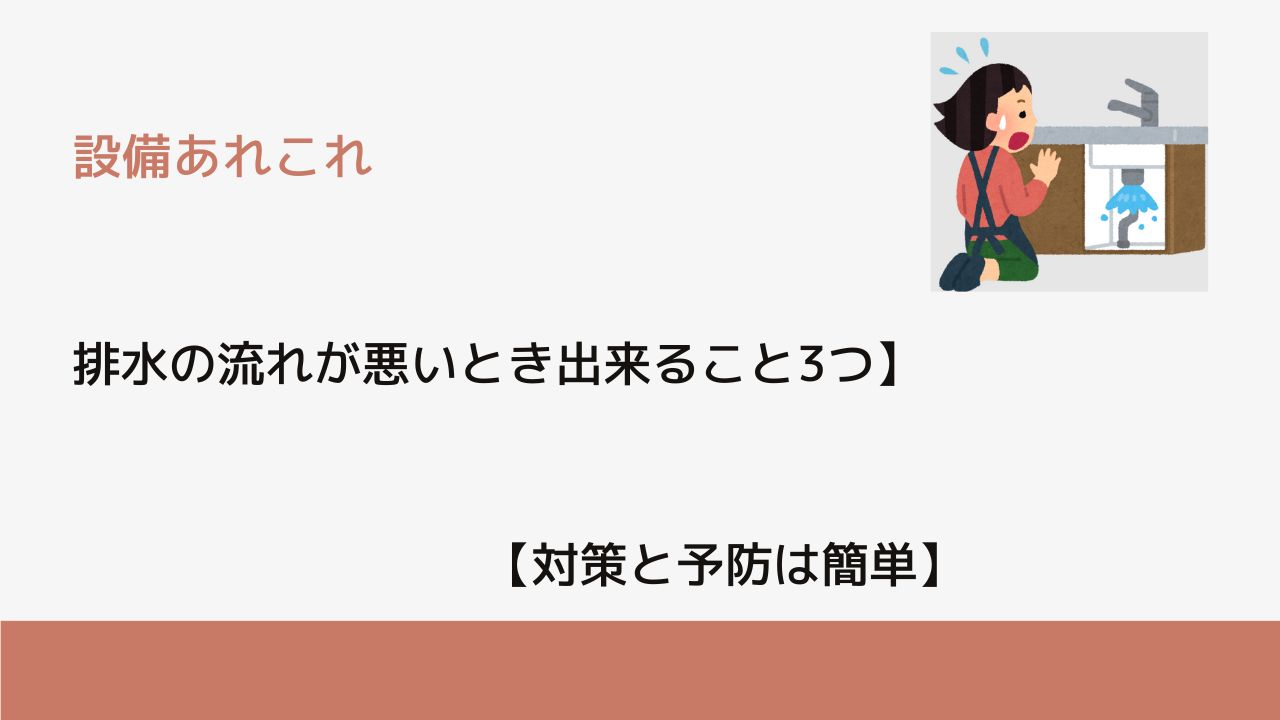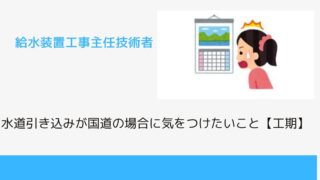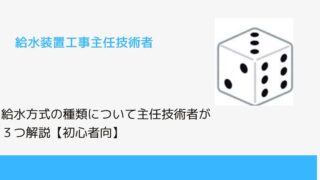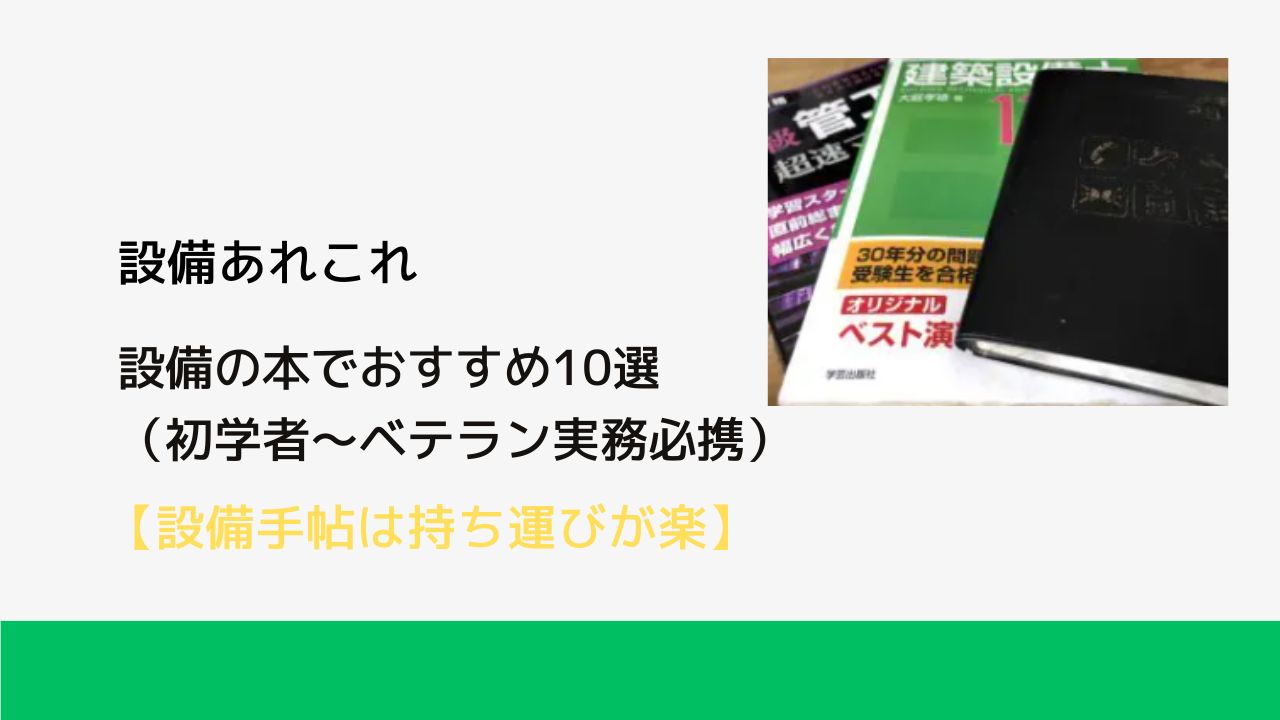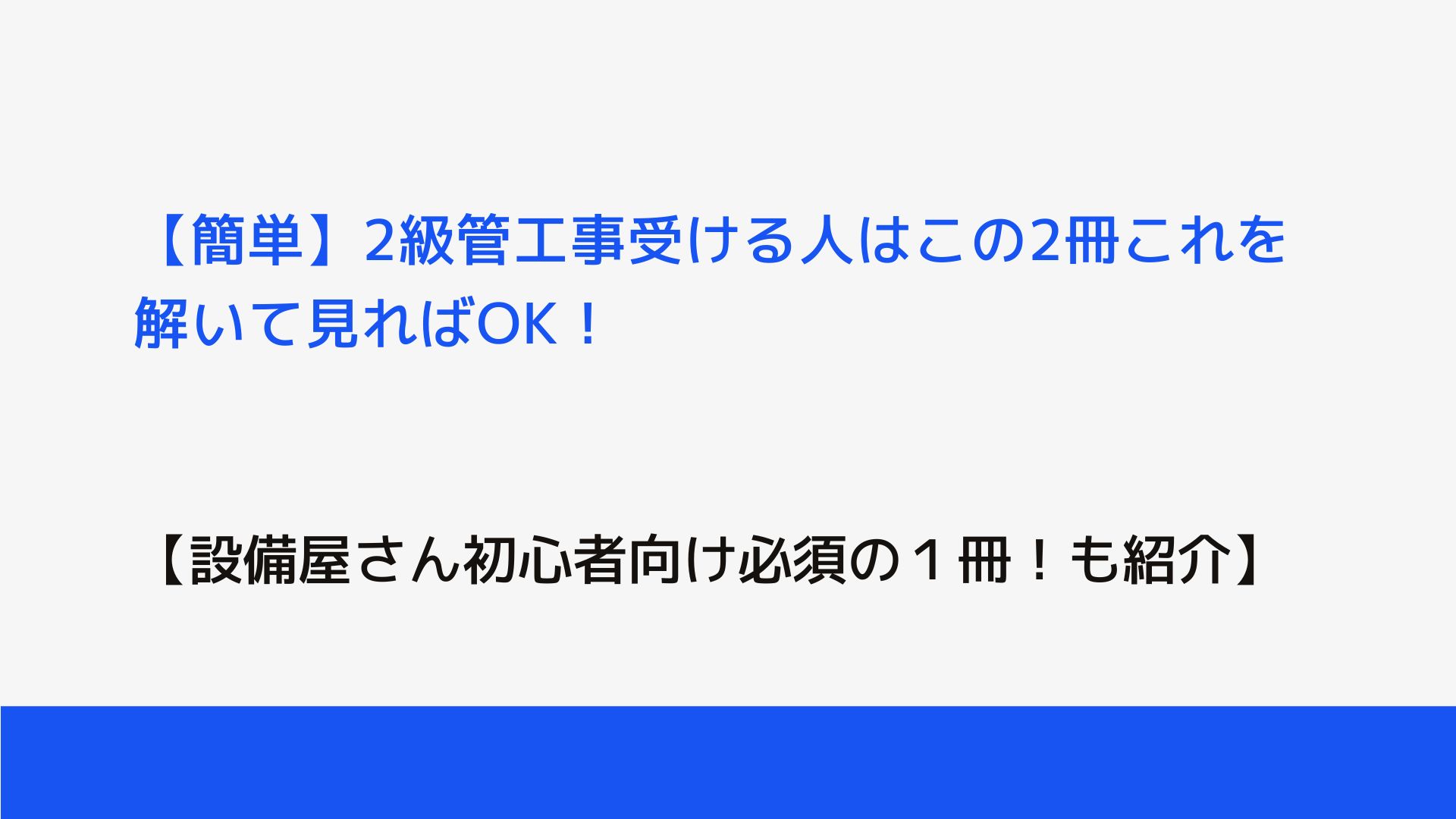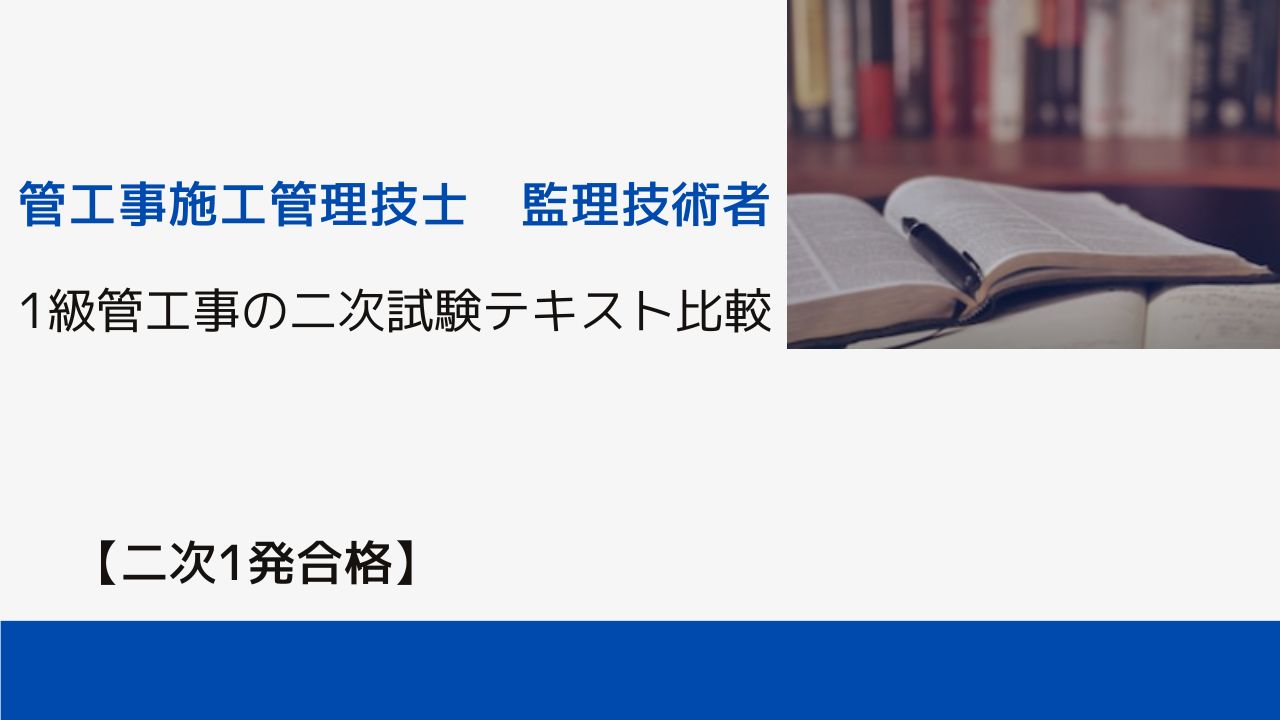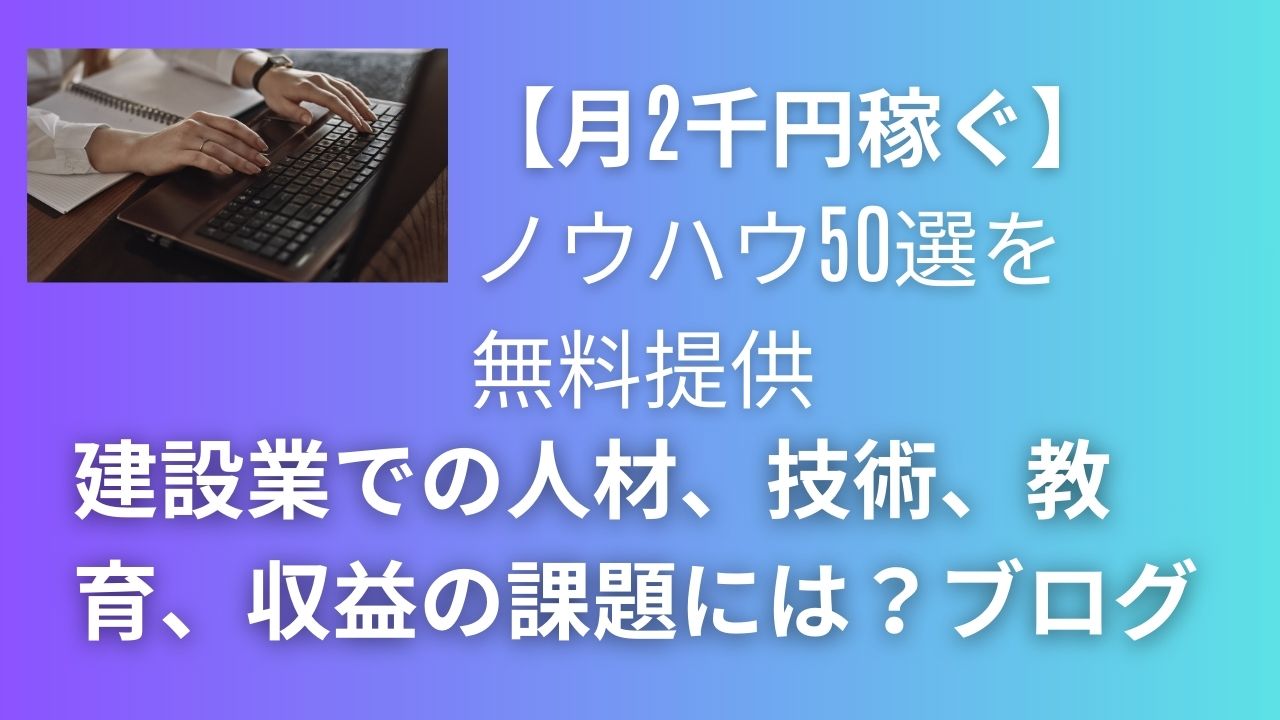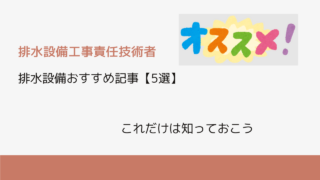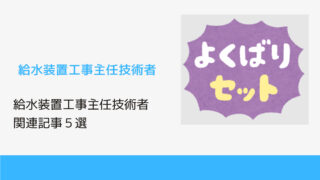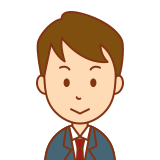
- 自然流下
排水の分岐はどうすればいいのかポイントを解説
 排水の分岐はどうすればいいのかポイントを解説
排水の分岐はどうすればいいのかポイントを解説
- 外回りは基本的にはますで受ける。
- 流下(流れていく方向へむかって)管は太くなってく。
- 近年の日本ではVU管(塩ビの肉薄管)などが主流なので、それに即した塩ビます、継ぎ手が必要になる
- 昔のますは改良ます(コンクリのつみあげたます)が主流(いまでもたくさんある)
- 屋内は通気に注意
- 屋内は勾配とたの建築資材との収まりに注意

排水の分岐の際の注意点
そとまわりのますの選定にはある程度決まりがある
(行政によっては強制)のでよく確認すること。
理由は検査立ち会いで是正を指示されると
余分な費用が発生し、もしくは行政から誓約書などを求められ、お施主さまも施工も建築もだれも喜ばないから。
具体的にどうすればいいのかという部分
・事前に下水道管理者に相談する
・相談前に質問のポイントをまとめる
・相談前に建物の外交計画図と配管スケッチを作成しておく
などです。
排水の分岐の部分のルール
排水の分岐の部分のルール
土中埋設で、会合(2つ以上の管が交わる部分)、屈曲(まがる部分)にはますをいれましょう、
理由はいれないと「管つなぎ」といい、メンテナンス性の悪い
施工と判断され是正となる行政もあるからです。
それ以前のメンテナンス性の低さは問題ですが、
具体的にはつまったらどうすんの?という部分です。
ますをいれると施工は大変です、収まりを考える手間、
立ち上がりのますのあたま(掃除口)の高さの調整(レベル
が出ているかどうかで手数は増える)、部材も増えますので
工賃も部材代もあがります。
しかし、現場是正のリスクや、つまりによる、
毎回のつまり直しの手間をのちのち考えたら必要になる
施工なのかもしれませんね。