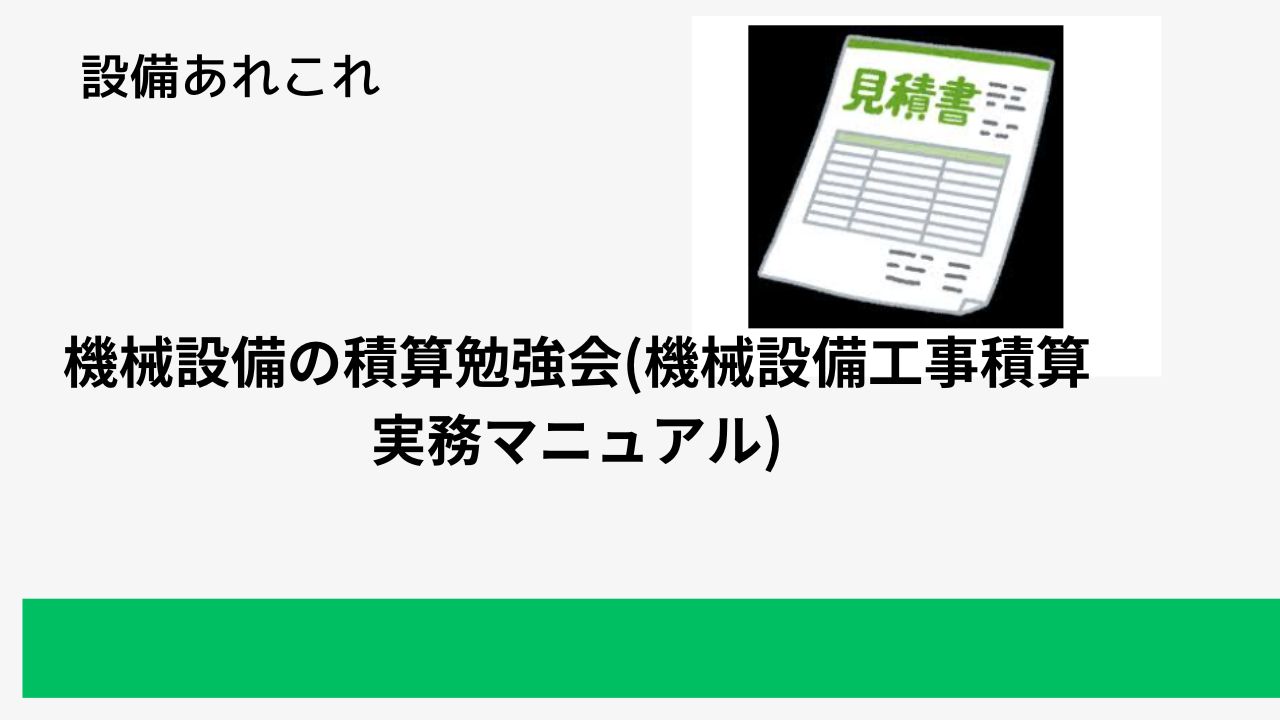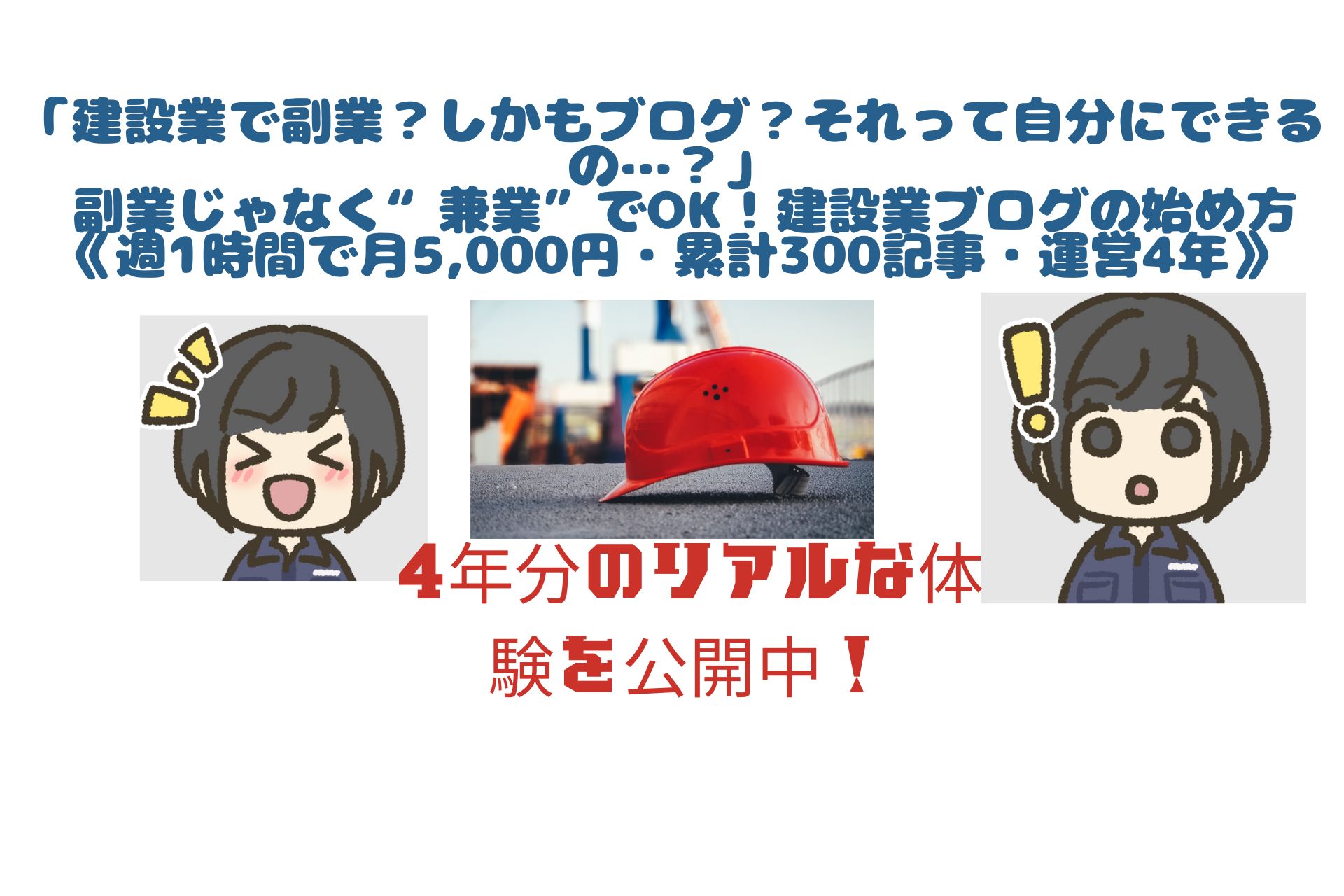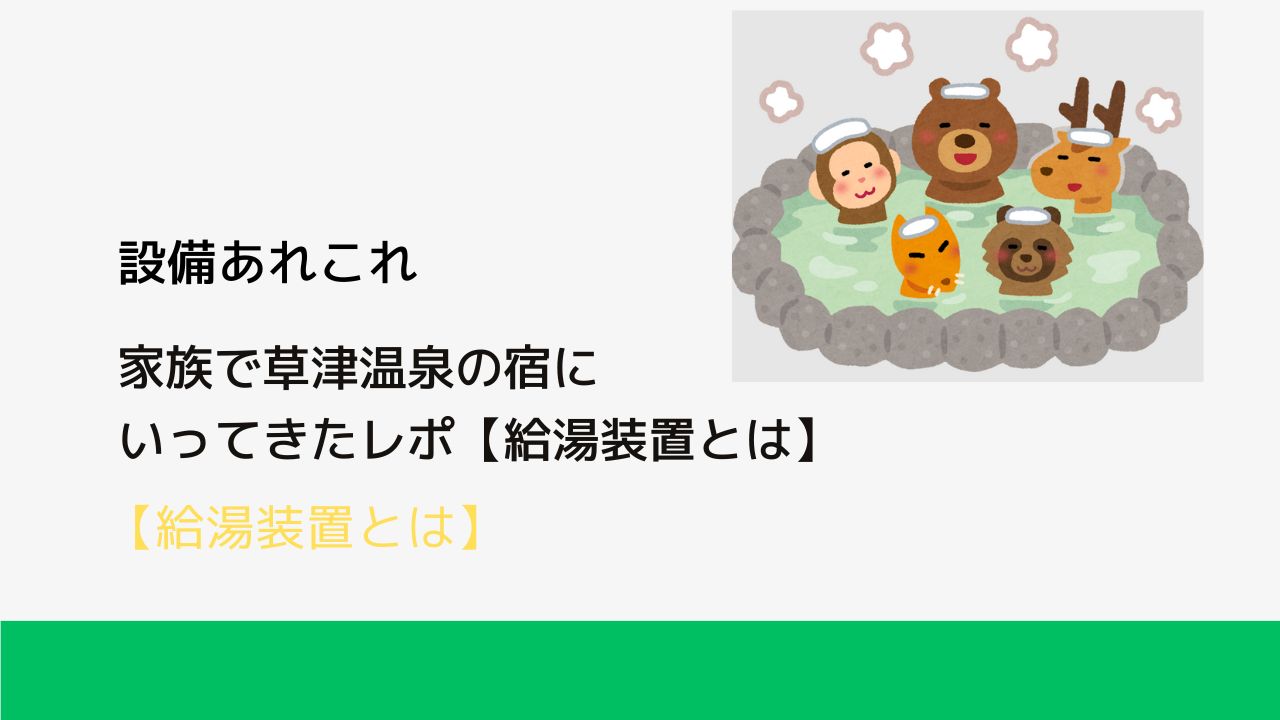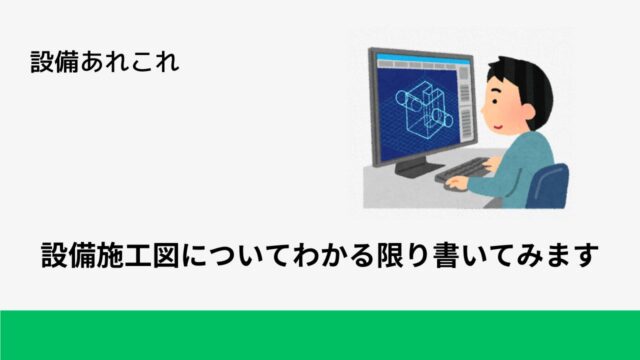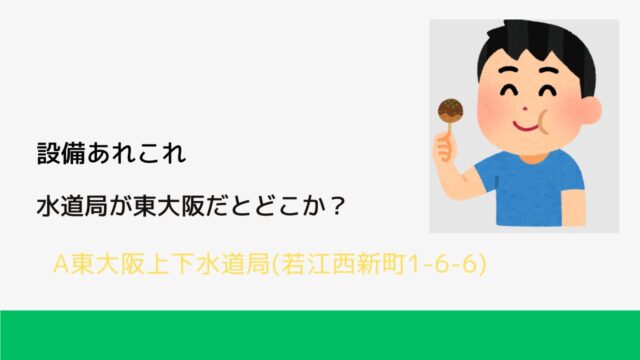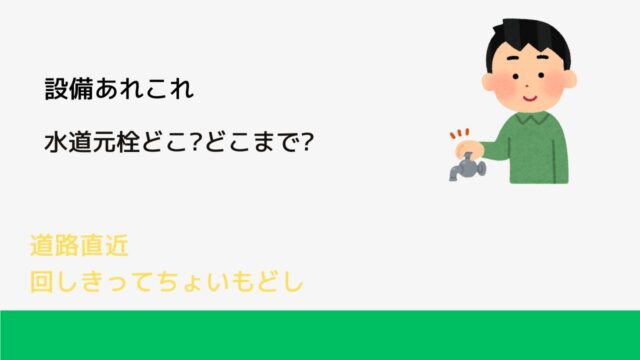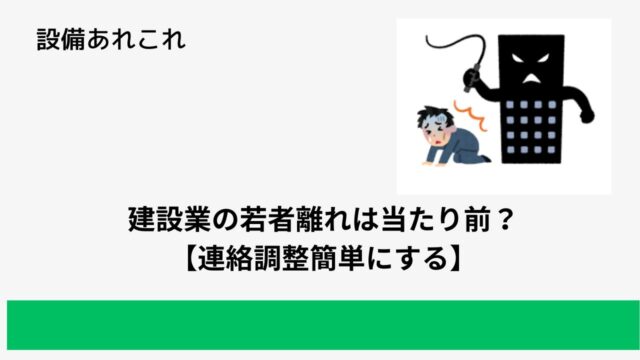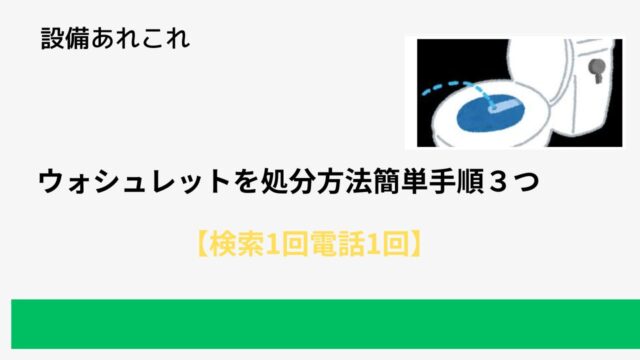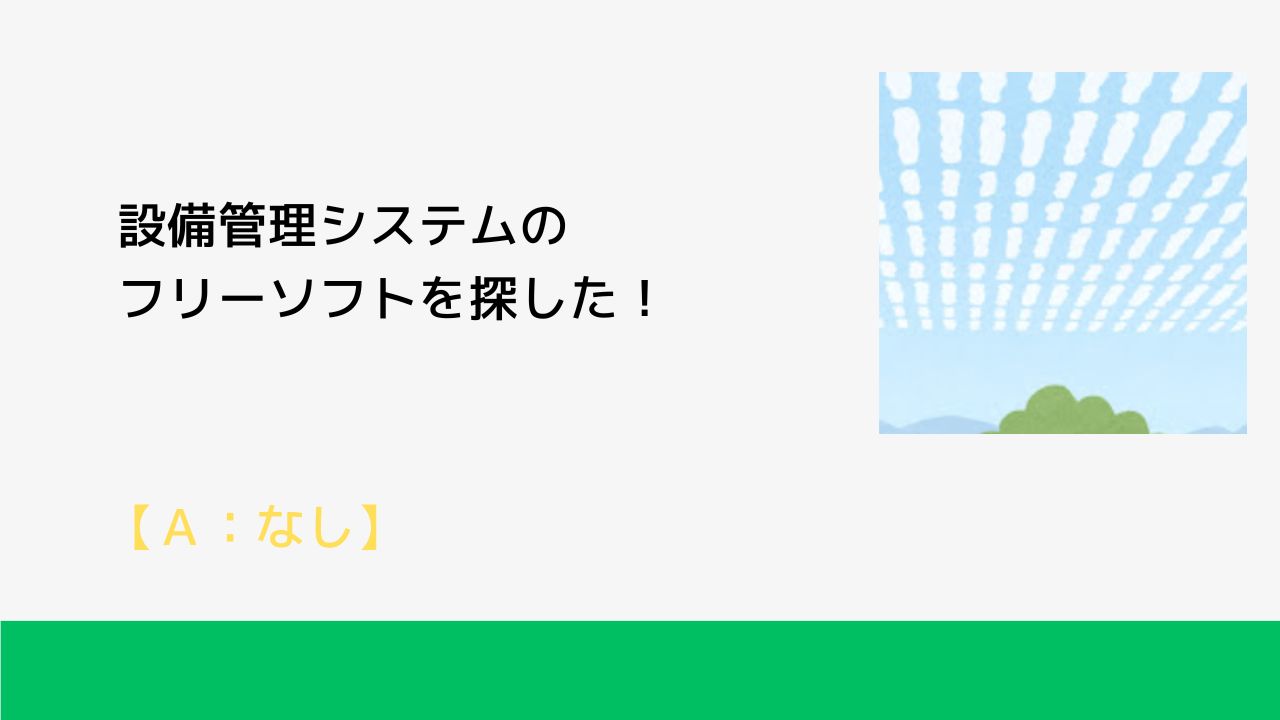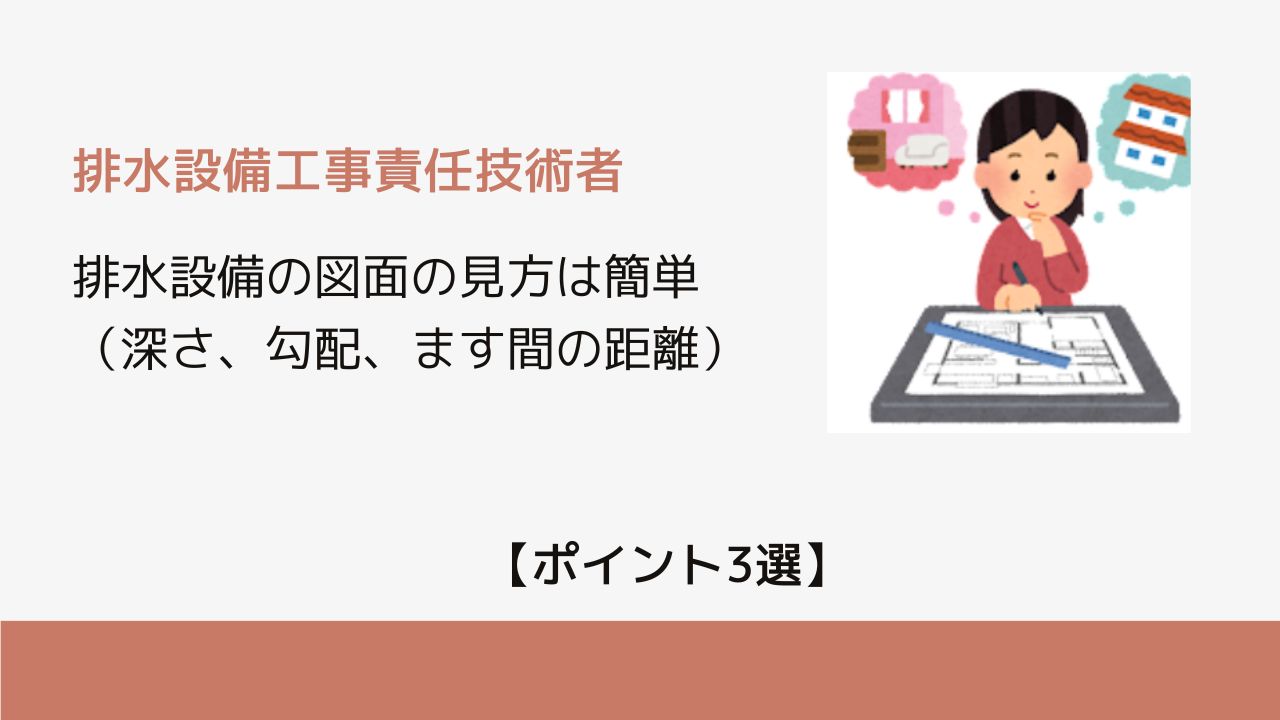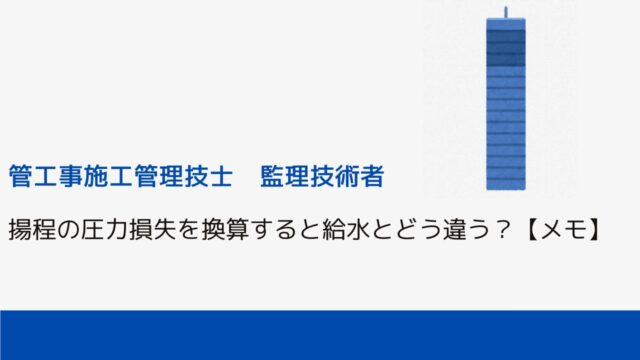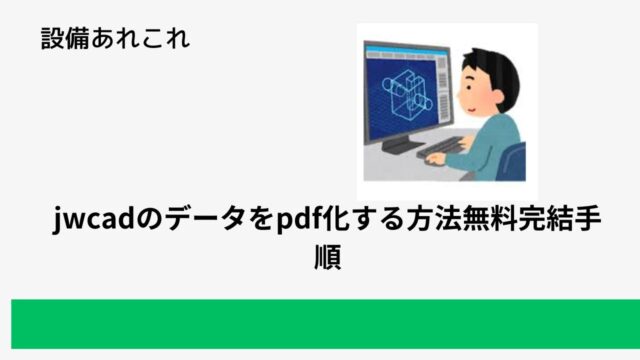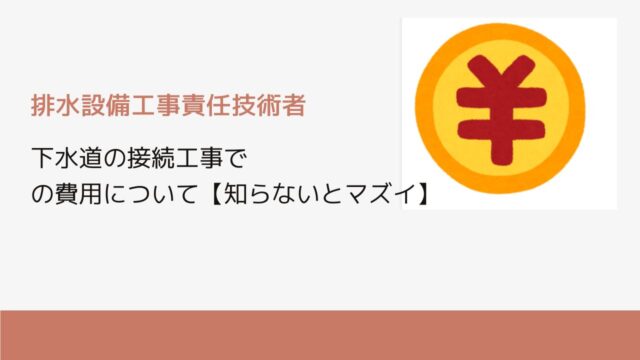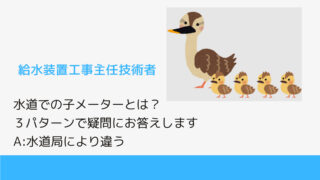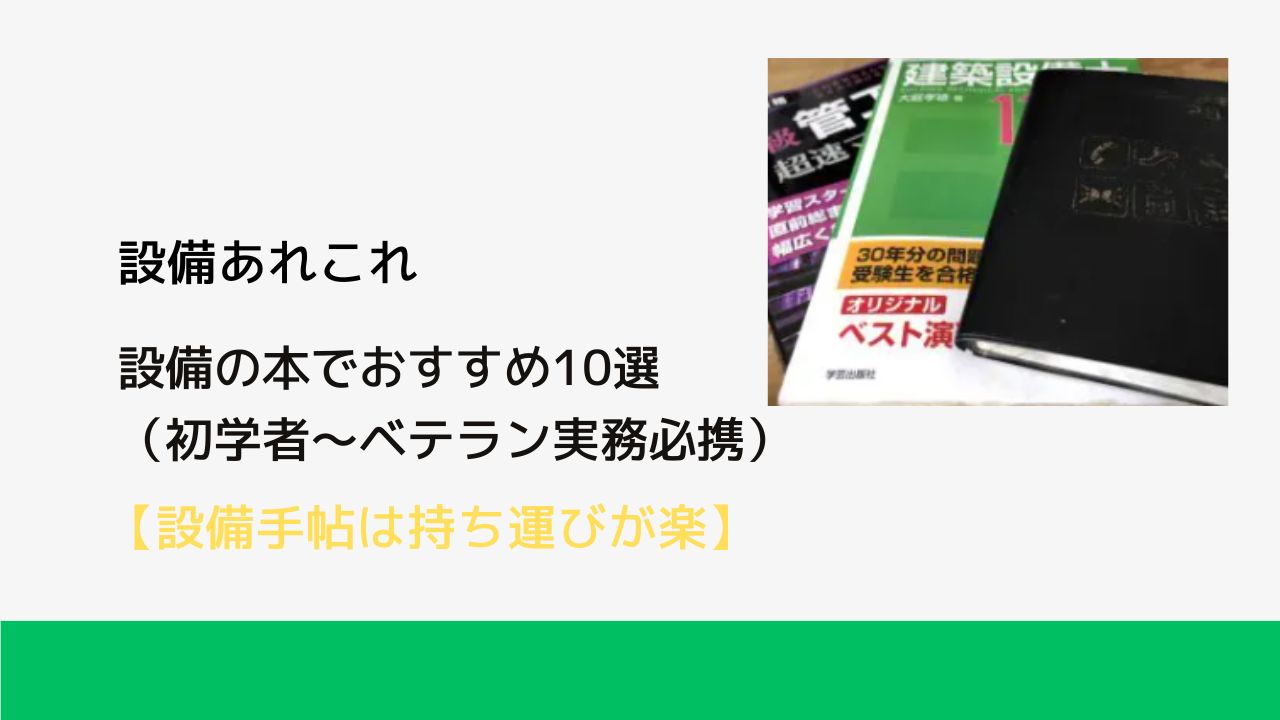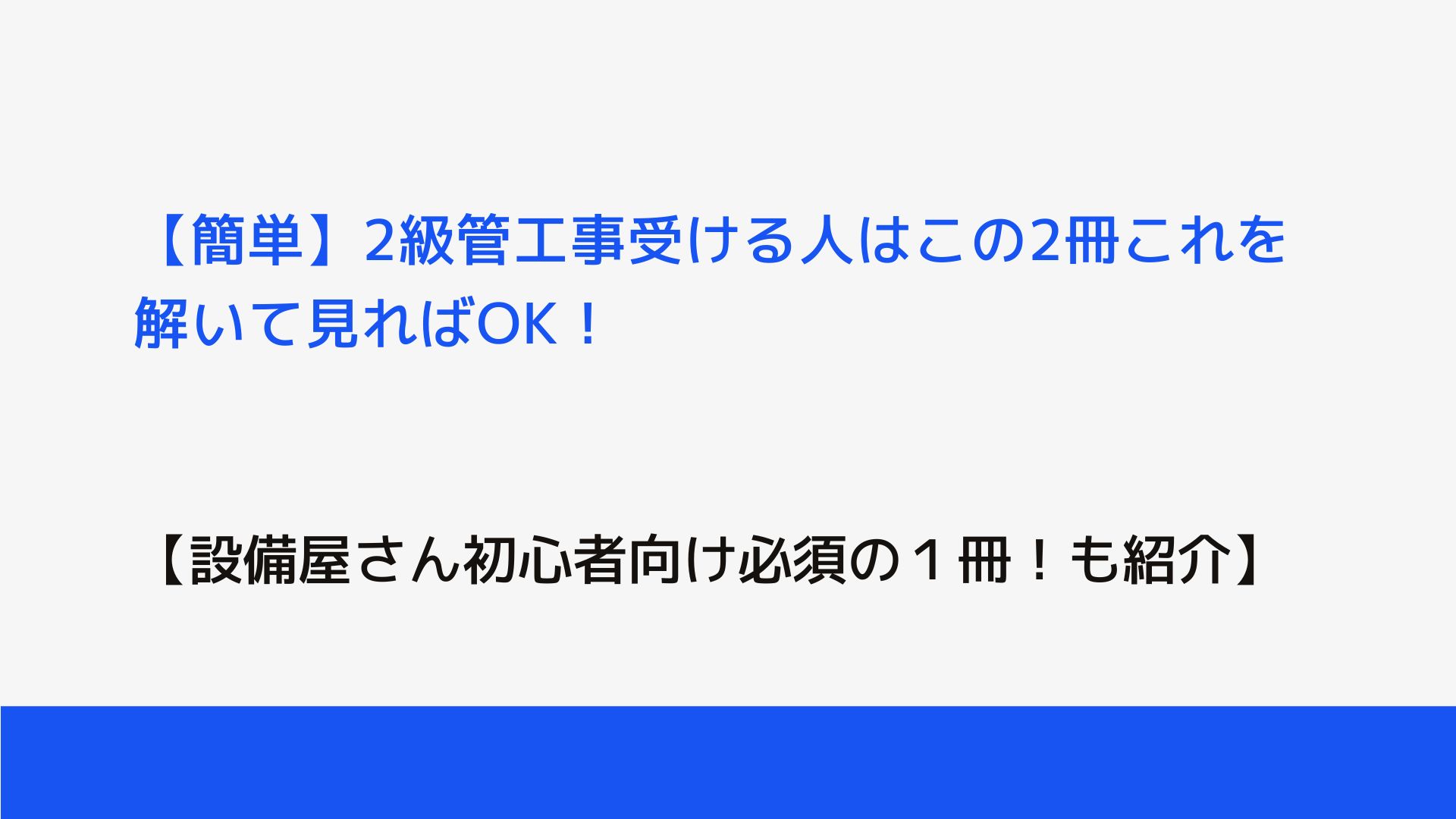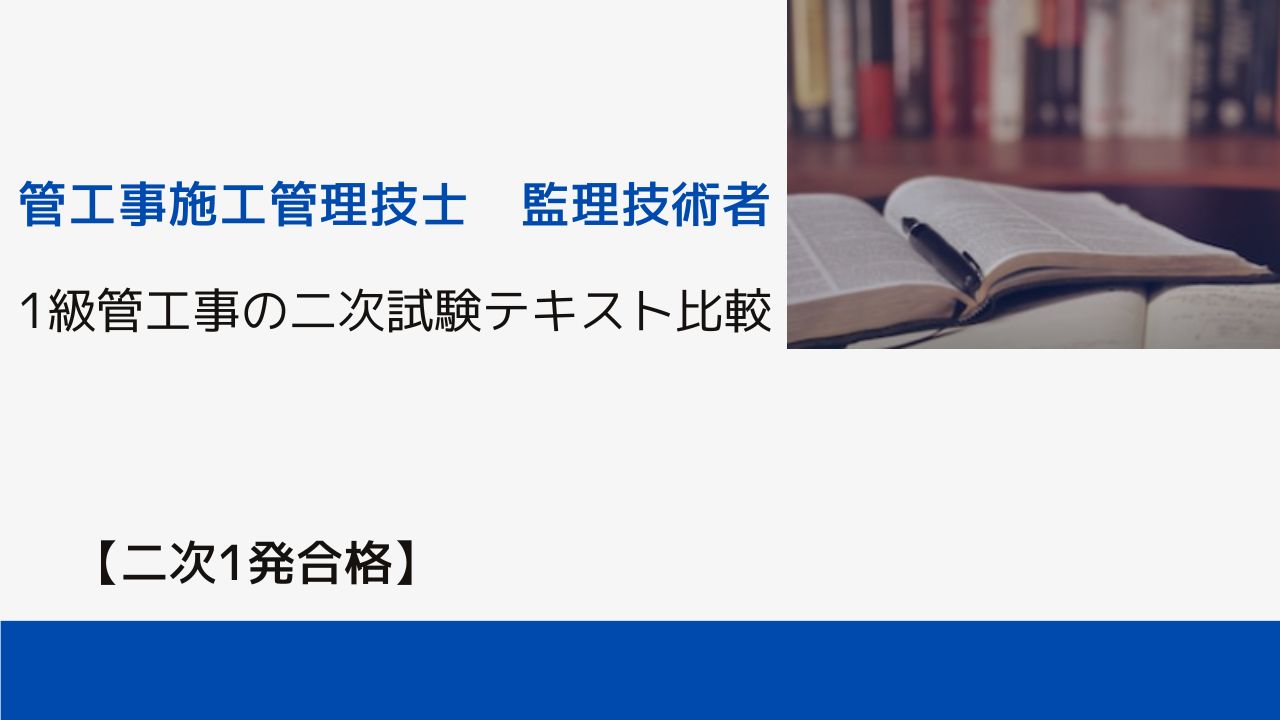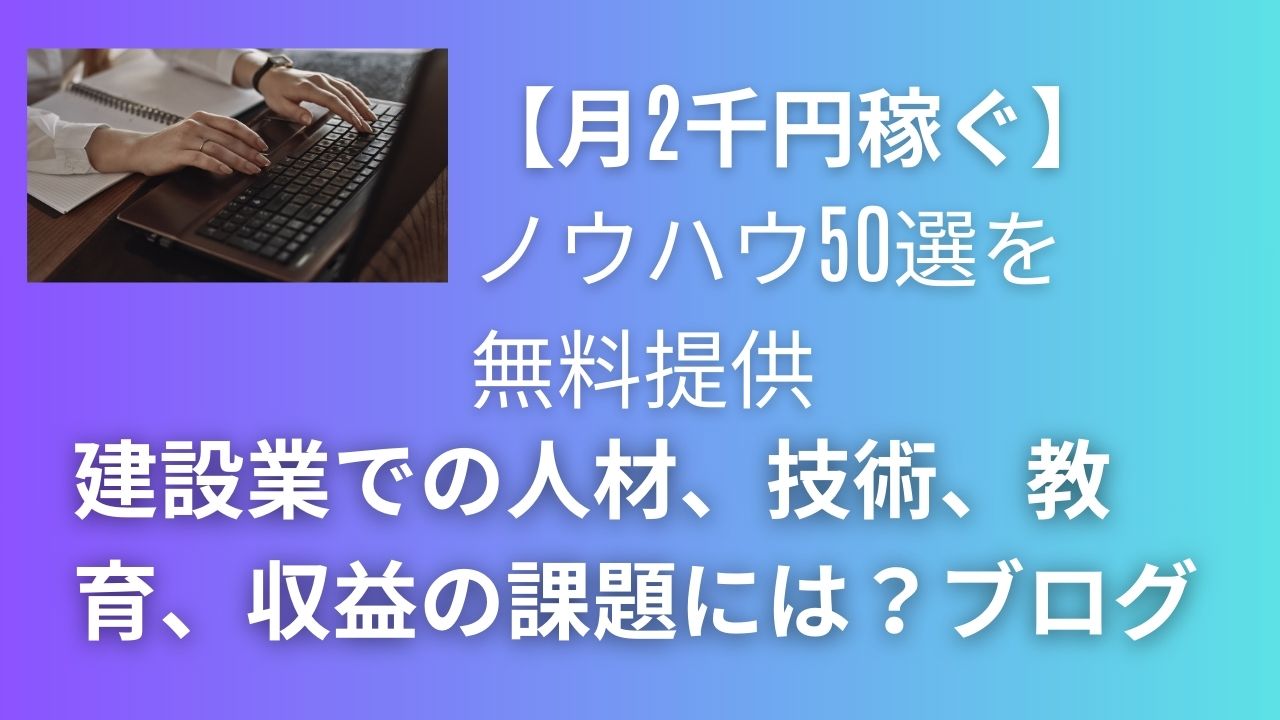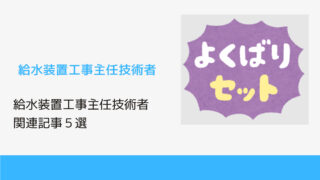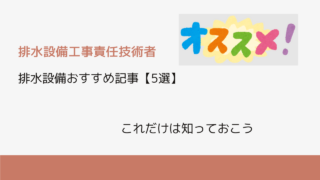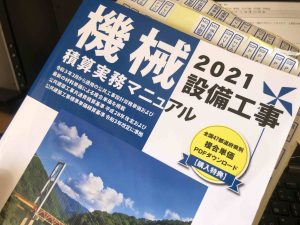
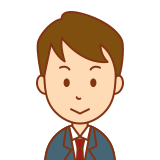
そんな方への記事となります。
この記事の内容
- 機械設備の積算の本を興味本位で買った
- 読んでみての気づき
- 積算の本での学び
機械設備の積算の本を興味本位で買った
見積もりどころか、施工もよく知らないのに意味ないかもですが一応買ってみた
結論→よくわらない!
理由→見積もりをしてないから
具体的には
他人の見積もりを見て「?」ということは
山ほどあるんですが、
いざこの本を読むと
「未来をさきよみするむつかしさ」
というのをしひしひと感じます(ええ個人で購入する金額かいなかについてもしひしひと)
公共工事見積もりする人にとってはマニュアル的な一品
という情報をインターネッツから得て、
神田まで出かけて買いました。
店員さんに「きとくなかたですね」的な(あくまで的なですよ)
感想を頂きつつ、タイマイをはたいたわけです。
取得欲以外の満足を得られることはできるのでしょうか
機械設備の積算の本での気づき
実務でやっていなので、そこまで気づきはないのですが、
参考になればというレベルで書いていきます
付箋のシールが参考になりそう。
書いたら意味がないが、それだけよく確認する人が多いのだろうと予測、
一般的な管材が多かったですが、おお、これはニーズがあるからこのシール
があるので
あたりまえ?かもしれないが、目的は「適格な利出し」にあるので、広範囲多岐にわたる機械設備の
お値段について記載されている。
毎年出ているということは
国土交通省
公共建築工事標準単価積算基準
https://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_hyoujyun_bugakari.htm
でも370ページほどあるのですが、これだとエリアごとの差がわかりません。
わからんことだらけだということ「ぶがかり」「複合単価」
メーター数が伸びるとより売り上げになるが、その分人工も多くかかり人件費もあがる
くらいの理屈レベルでは到底およばないのですが、
積算の本での学び
施工方法の簡易な図が勉強になる
そのままなのですが、小さい絵があるのですね、この部材の工法はという小さいイラストが、
これが参考になります。
とくに保温まわりは意味わかっているふりくらいしかできなかったので(今も?)理解が進みました。
数字と文字の理解だけだと限界がありますが、こういう図がとても参考になりました。
職種だけでなくエリアごとに歩掛り(ぶがかり)とは別で複合単価が違う、
作業内容によって、地域差があるということですね。
気候などの違いもあるのでしょうが、都市部は比較的割高ですが、
それ以外の側面もありそうです
配管の場所による違い
- 配管場所
- 機械室
- 屋外
- 屋内一般
かなどによる違い
管種、口径、継ぎ手、保温、それぞれの作業区分による違い
目次からはじめの40ページくらいが基礎的なことが
たくさんかかれていて勉強になります。
公共工事における、
部材指定で利益だししにくいと聞く消防や、
とにかく人員を空けてしまうことによるロス、
年度末年始開けによる工程の難しさ、
予算がきっちりしすぎているので、増減の調整などの苦労を
話には聞きますが、それいぜんの見積りも
相当大変そうですね。
消防設備士オススメテキストランキングはこちらこちら