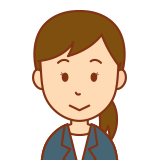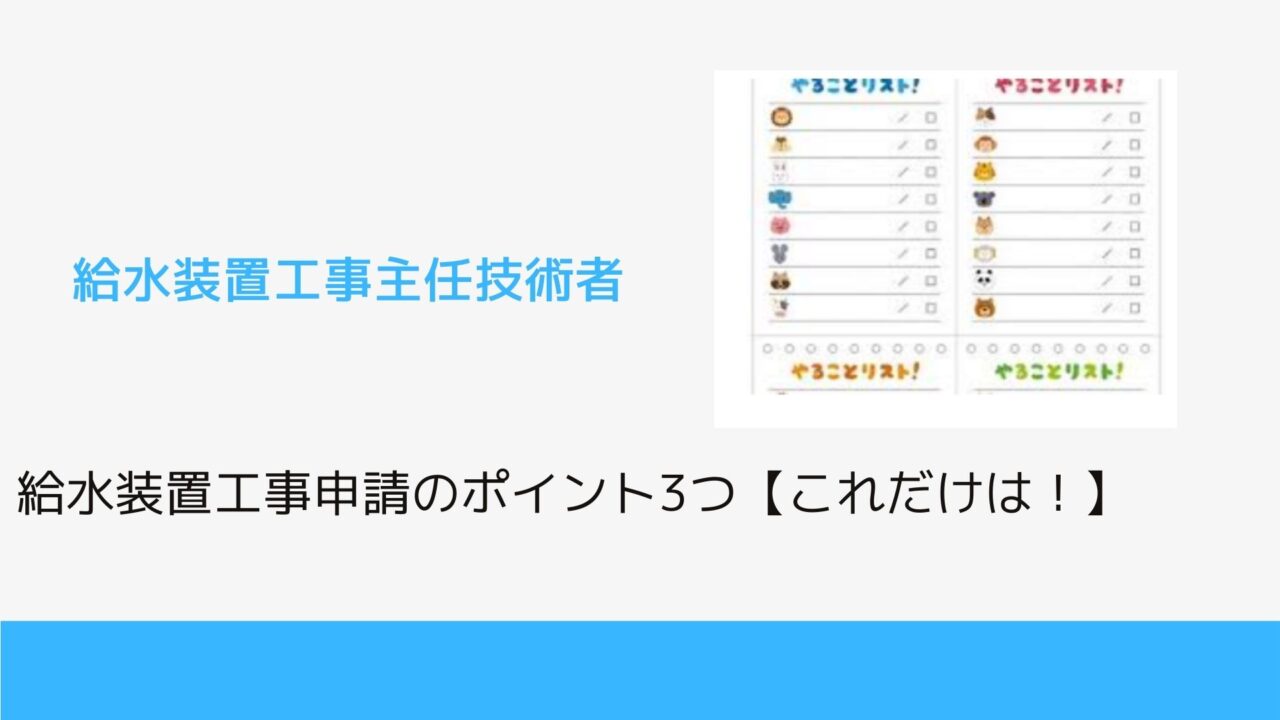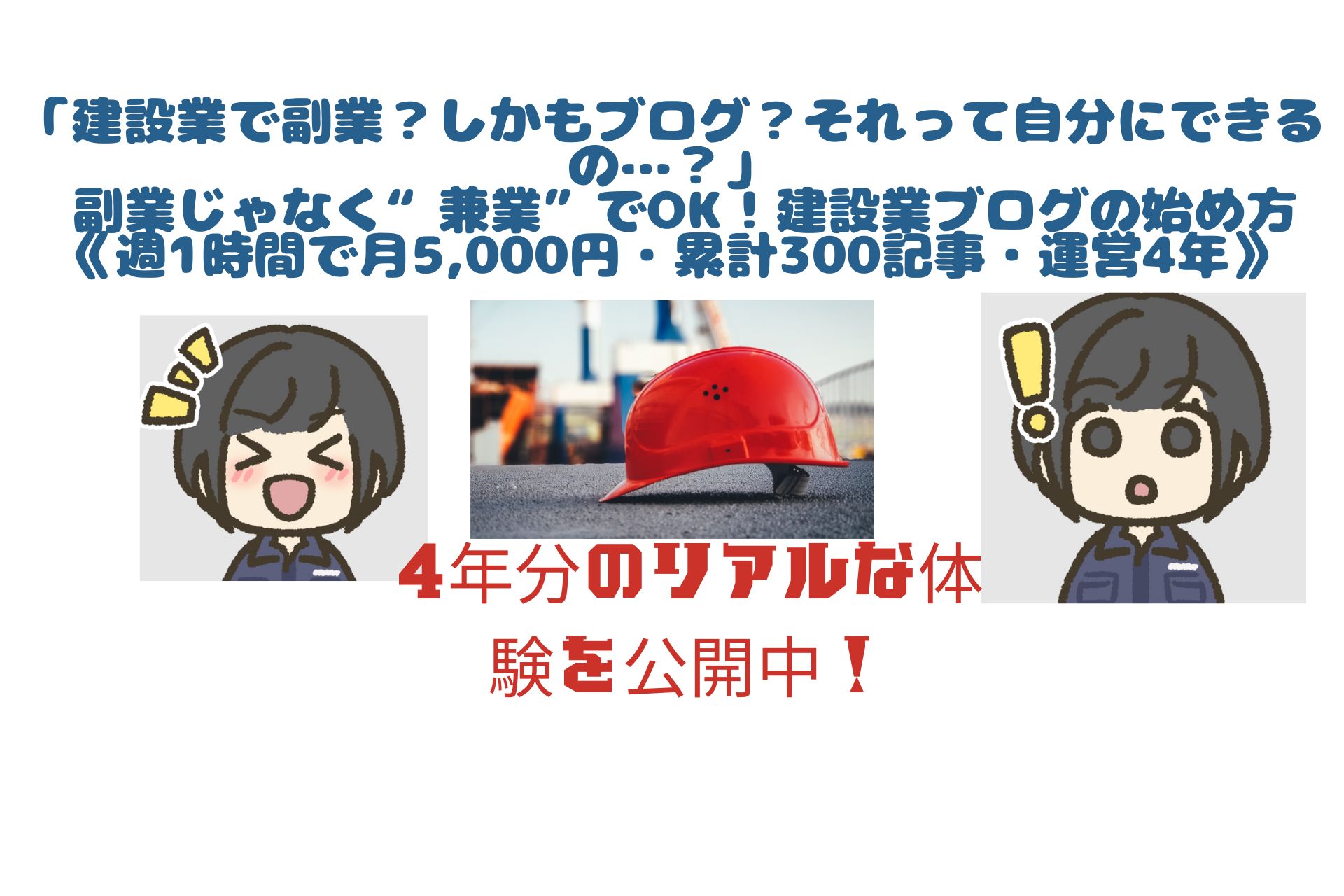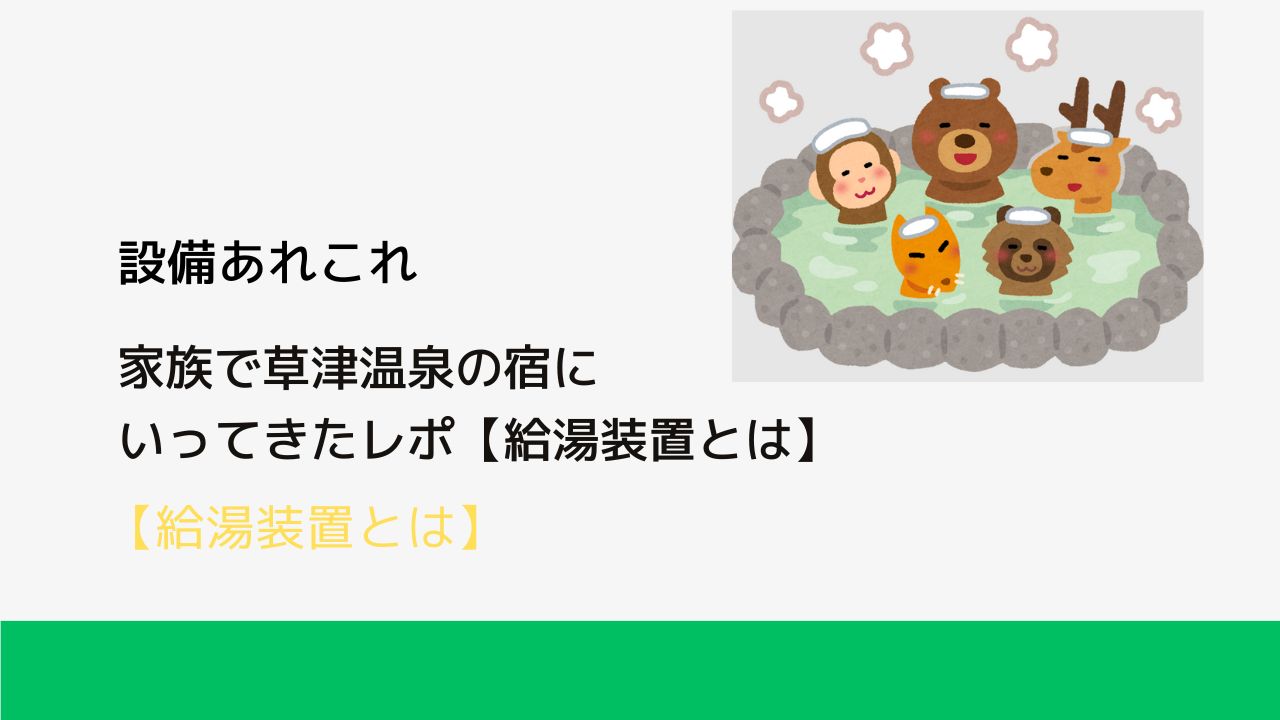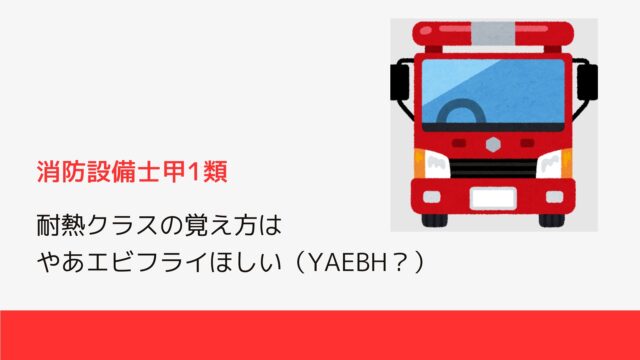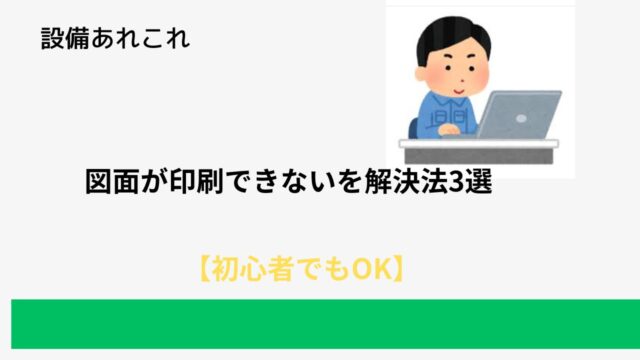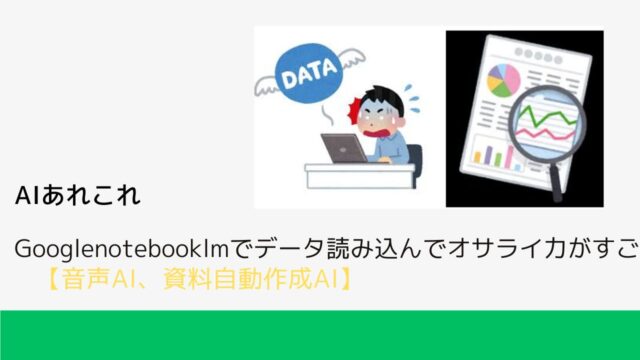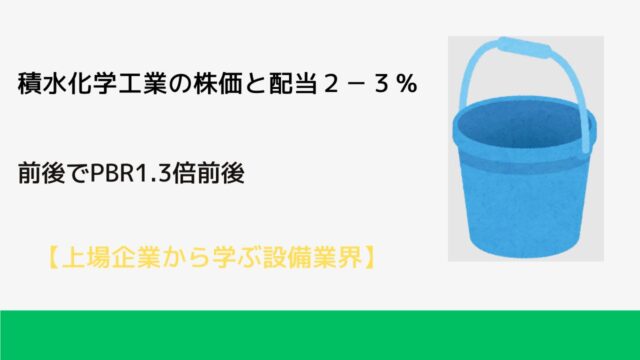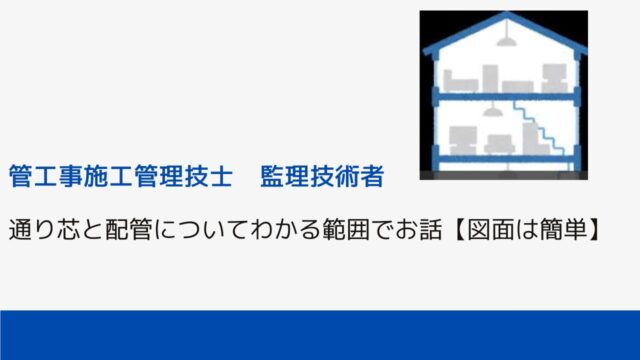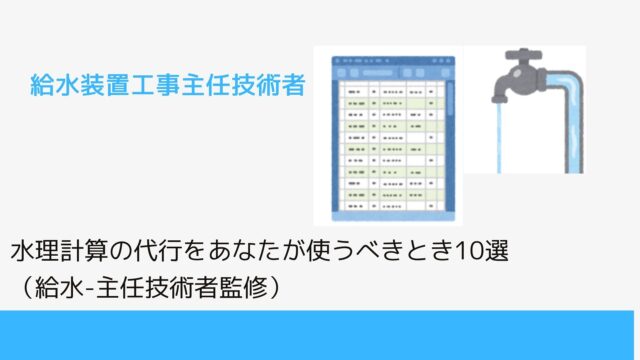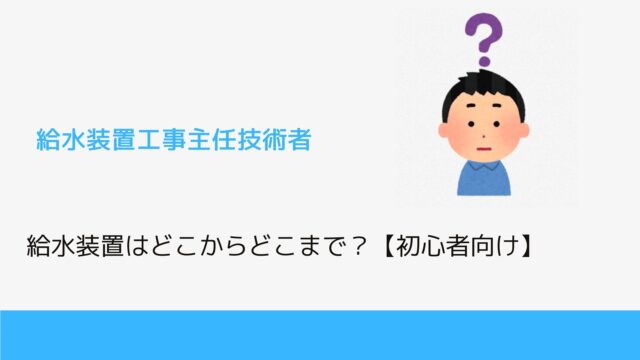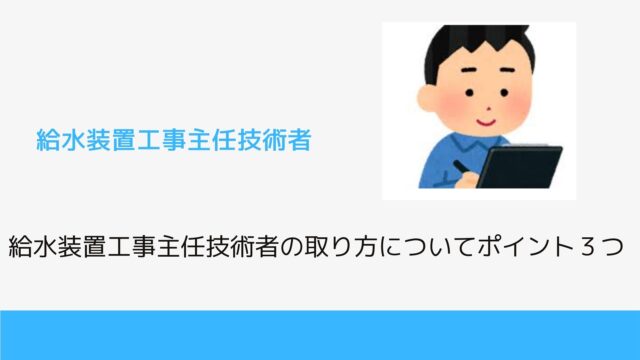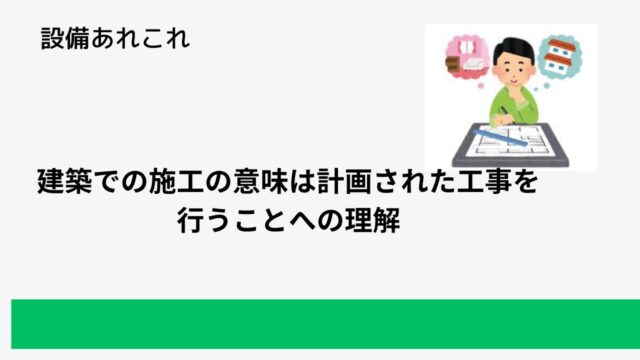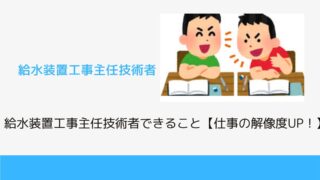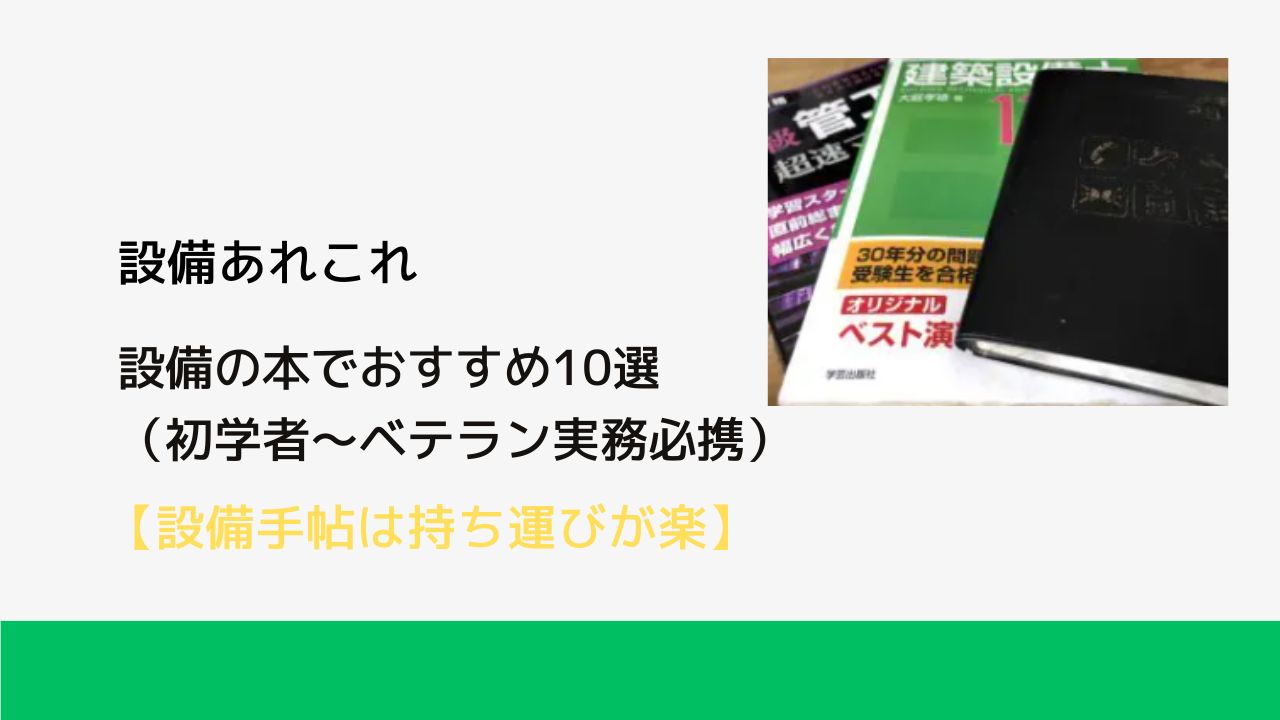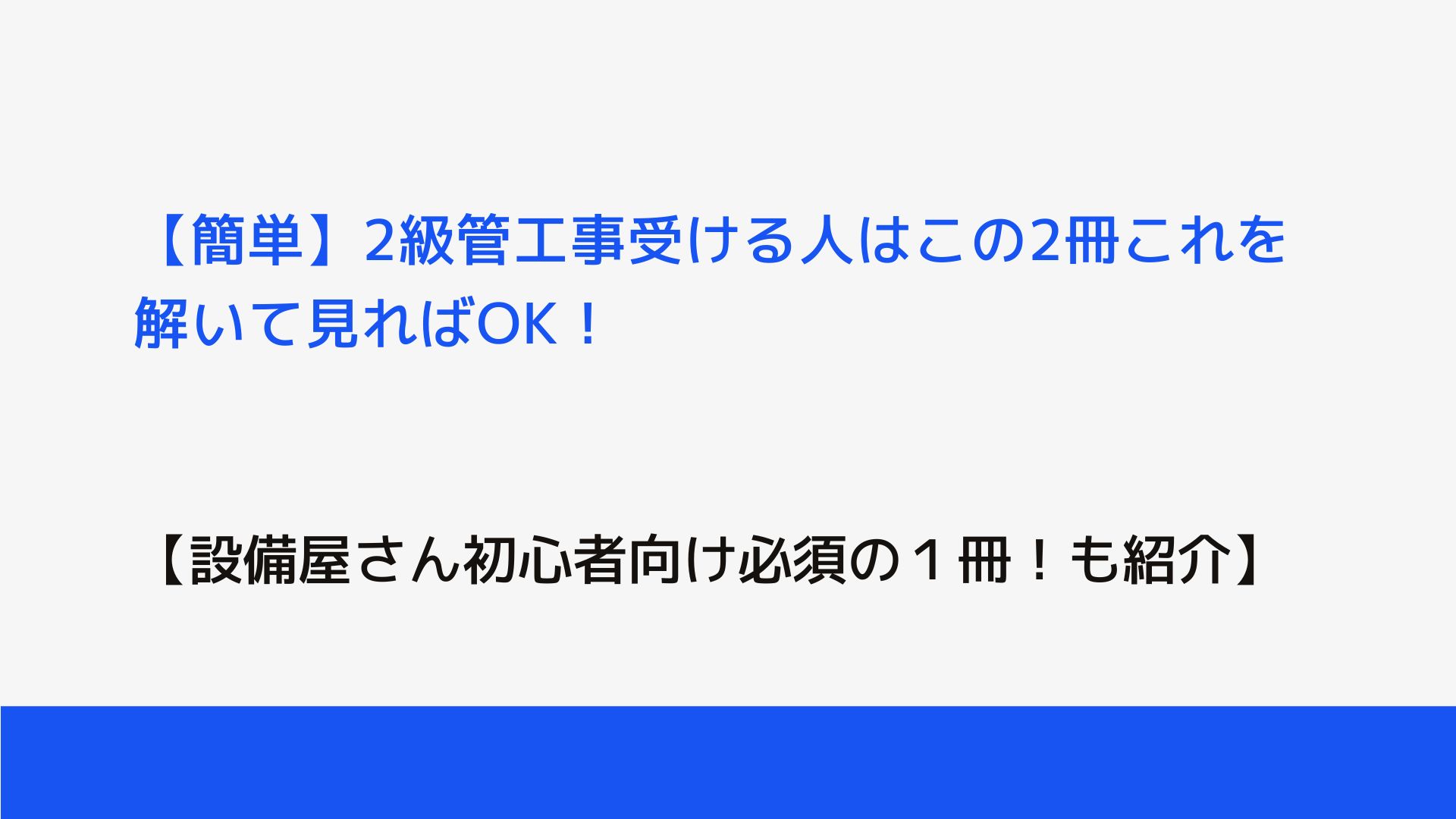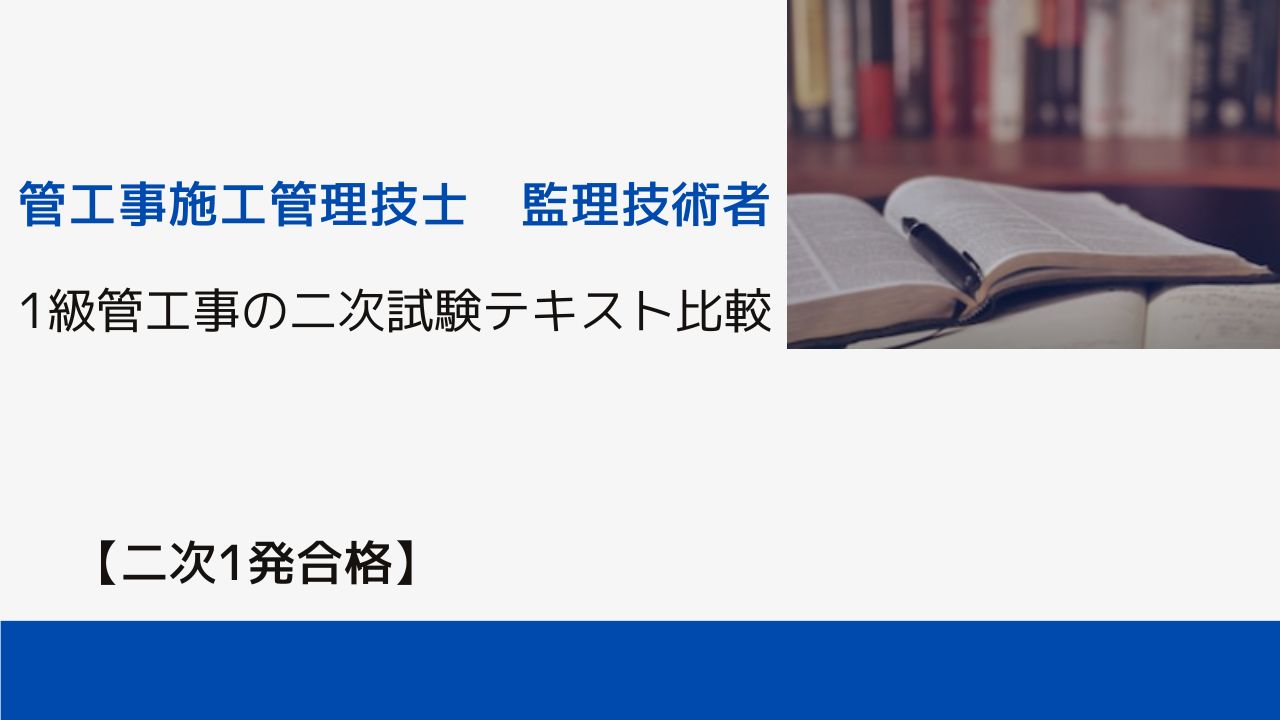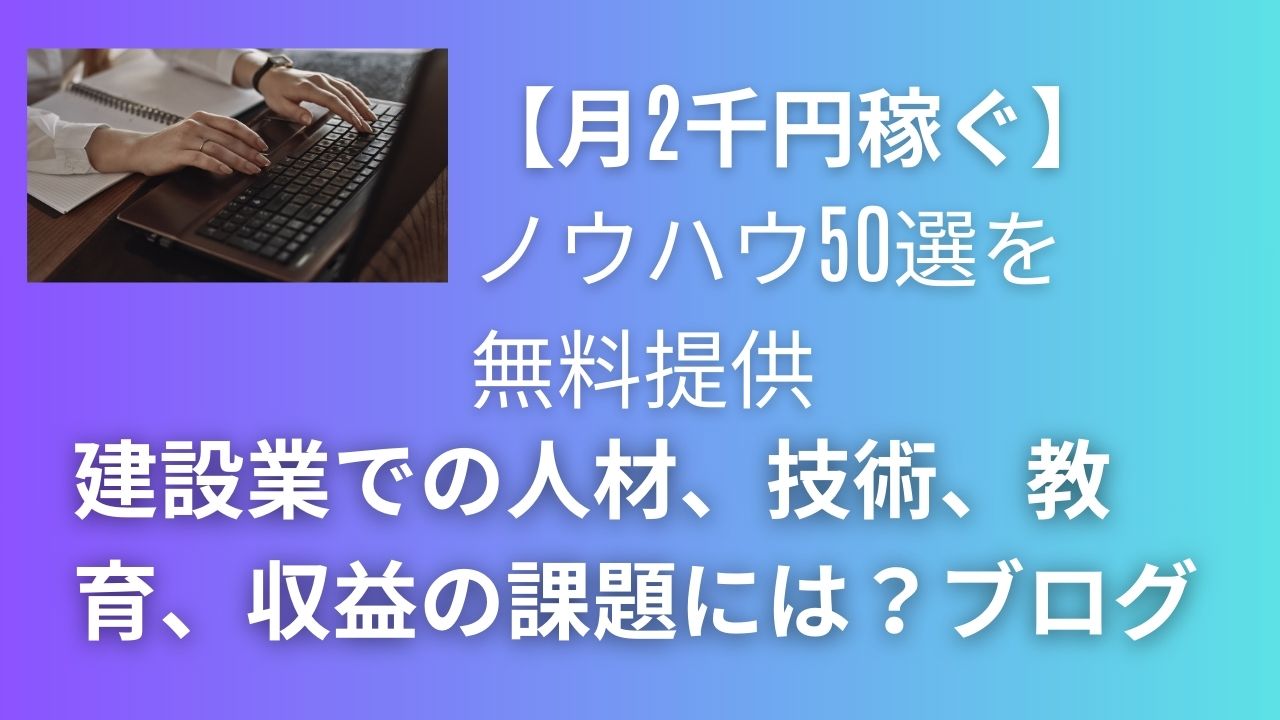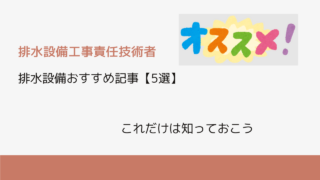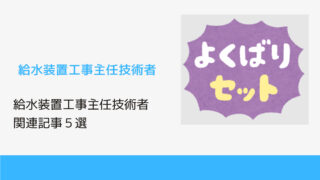という方向けへの記事となります。
☑無料で公開してます、みてみませんか?
ネットの微妙な情報だけで施工監理していませんか?
いまさら周りにきけないし、施工で失敗もしたくない
そんなあなたに基礎からベテランまで使える情報を紹介しています
>>無料紹介ページ
本記事の内容
水道屋さん?水道局?水道メータ払い出し??
書類がたくさんあるのでしょうか。
役所なので、いまいちとっつきにくいなどなど、
わからないことも多い世界と思われがちですが、
主任技術者5年生となるかたからの伝言です
- 給水の申請の流れと必要性
- 自治体によってやりかたが違うよということ
- 代行業者に依頼するのはNG?
- 書類はいろいろある→内容はコピーしておくとベター
- 何に給水の申請で気を付ければいいのかということ
などです。
それではいってみますかー
・給水の申請の流れと必要性、
結論からいいますと。
流れは
- 設計審査(書類図面持ち込み)
- 施工
- 現場調査
- あれば(分岐立ち合い)施工
- 竣工事務検査(書類図面持ち込み)、メータ払い出し
- 竣工現場検査(現場立ち合い検査)
間にはあと数十工程ありますが、割愛します。
あと、申請は「軽微な変更」以外は「必要」となります。
理由は
2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省)の水道法で決められているからです
水道事業者(水道局)の指定する指定給水装置工事事業者(水道屋)
はちゃんと申請してね。
とです。
ほんと?
給水の申請の流れと必要性は
新しい建物や、
新しいおうちの水の配り方など
のときに主に必要です。
配り方?
配り方には
(ポンプをつかう、タンクをつかう、それらは使わない→直結)
が主にあります。
なぜなら、
あたらしいおうちには水が必要で、
その水を配っている水道局から
設置されている管から引き込んで、
水道メーターをつけてお金を払って使う
必要があるからです。
具体的には、
家を建てますよという証明書や
→建築確認申請書(自治体によっては不要)
このくらいの規模です
という建築さんや設備屋さん
水道屋さんの図面とか
もちろん、
住所や申し込む人の名前などの記入された「
書類」も必要となります。
大きい建物には太い管、
小さい建物には細い管をいれますから。
そういったところを建築さんや水道屋さんと
調整していきます。
金額などが余分に発生するときもあります。
給水の申請の流れとしては
上記の基本情報から書類と
図面を作成して水道局に工事の申し込みを
するのが最初の段階です。
→いろいろ調整内容が多いときは事前の相談、
協議するのがいいですよ
(例)管が太い、全面の本管が細いけど太い管がほしいや、
多世帯でポンプなし、2世帯で細い管、
よそのお宅の管がある、メーターの位置を変えたい、
2本の管があるけど両方使える?そういうことは大丈夫?など
それから、施工、
最後に竣工という図面を書類を再度提出して、書類図面上の検査と
最後に現地での検査をして、メータをもらって(実際は図面上検査でもらえること
が多い)、使う人の登録をして
おしまいです。
長いですね。
なぜなら水は人々の口に入るものなので、国や自治体(水道事業者という)
で、そうしましょうねというルールがあるからです。
具体的には
国は2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省)という機関
自治体はこの2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省)に登録された水道事業者、
また、給水の申請を申し込めるのは、水道屋さんである
指定給水装置工事事業者、
また、その申請の責任者は、だいたい水道屋さんの社長さんなどの
給水装置工事主任技術者となっているからです。
・自治体によってやりかたが違うよということ
ということですが、
結論として、頭は国でも実ルールは水道事業者によってまちまちのところもあります。
主任技術者の資格は国レベルのものなので、だいたいは同じことですが、
施工条令なども水道事業者(水道局)に任されているからです。
地域の特性なども関係あるのかもしれません。
<
・何に給水の申請で気を付ければいいのかということ
とくにないです。
なぜなら水道屋さんがやる仕事だから。
水道屋さんはだいたい地場の水道屋さんが多いローカルな仕事なので地元の水道局での
仕事に慣れているので、かけだし水道屋さんとかでしたら。
まあ、人により時期により、場所により、案件により、
いうことが違ったり、変わったりするということでしょうか。
まあ、それを最小限にするには事前に相談しておくのも方法ですが、
それでも変わることは変わるので、その点はあきらめるしかないです。