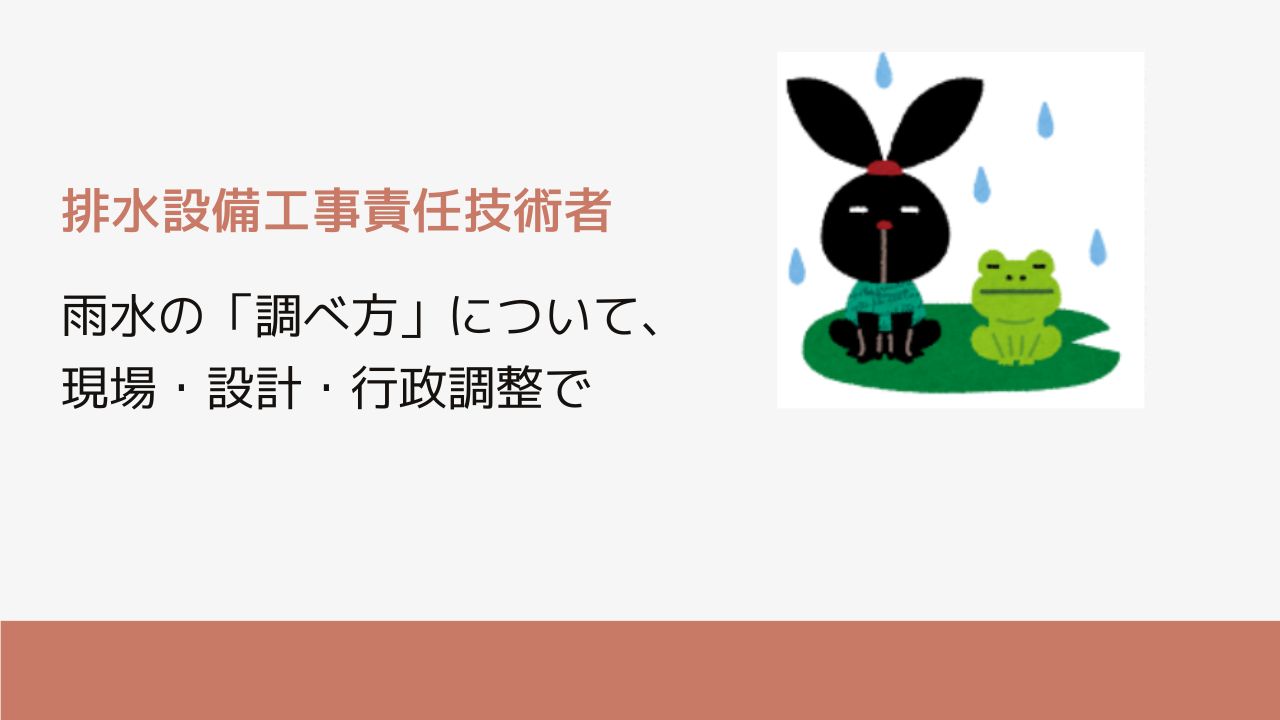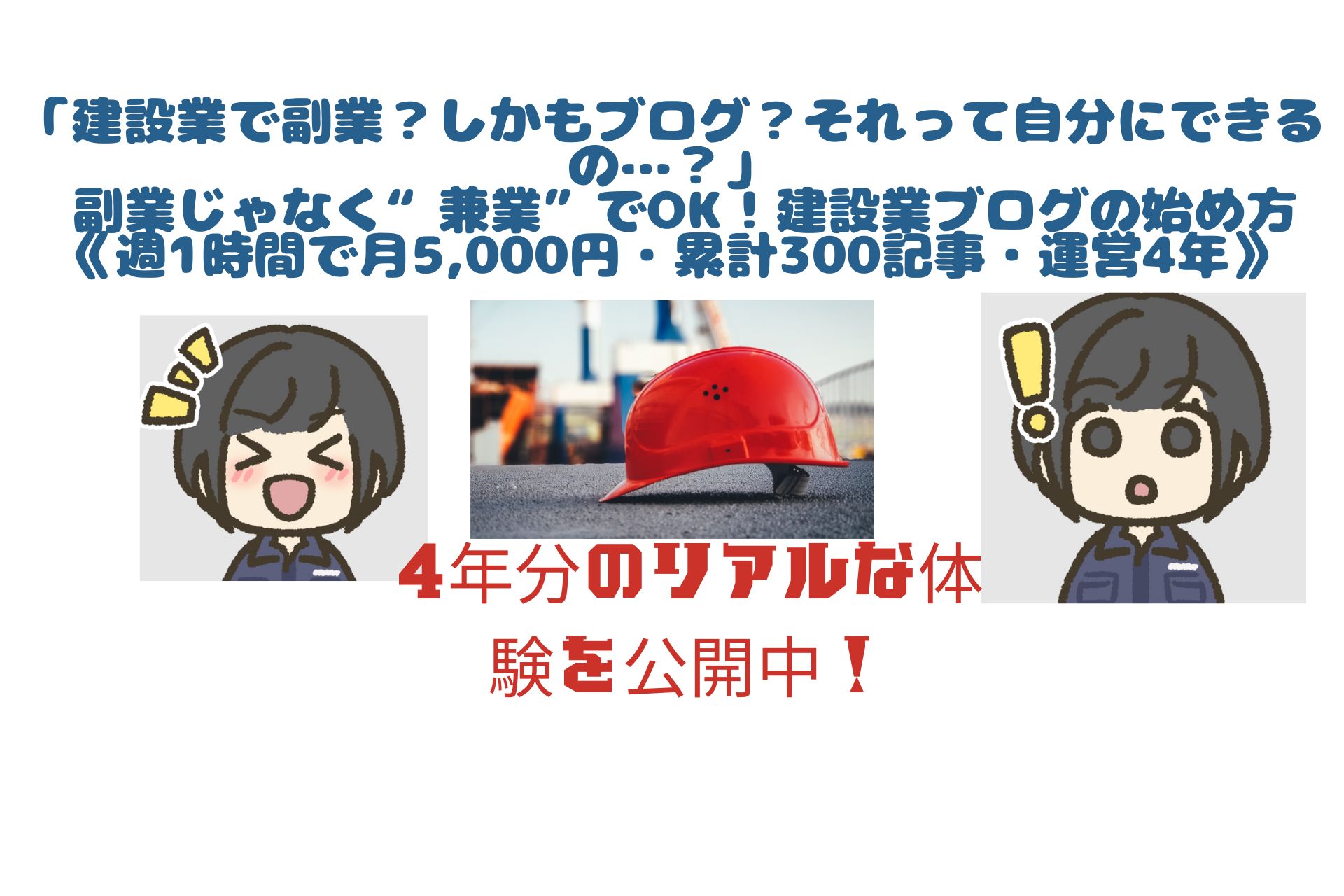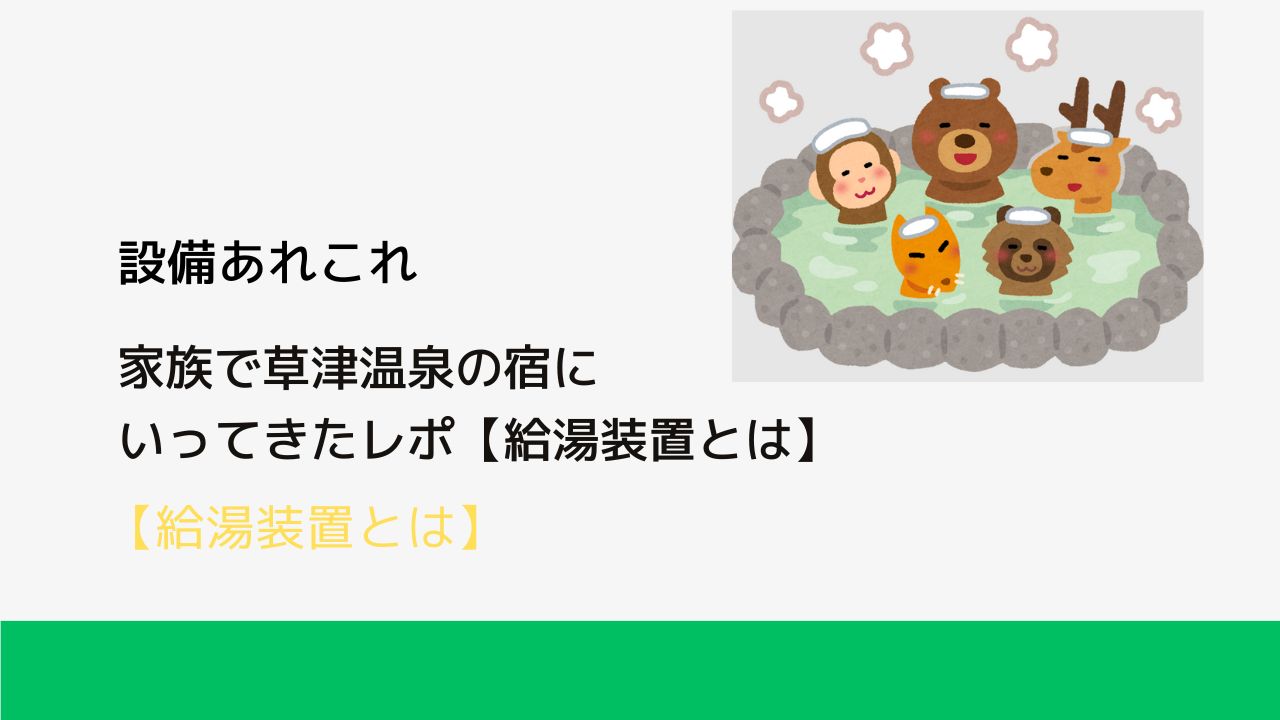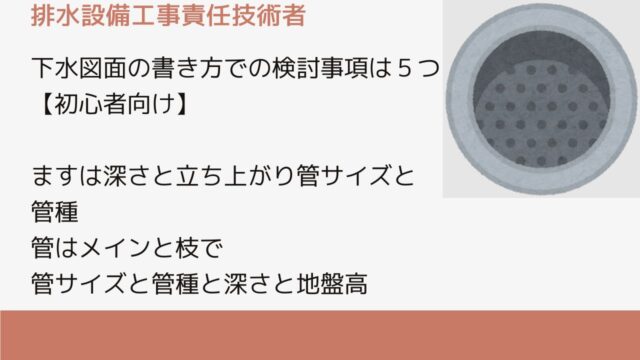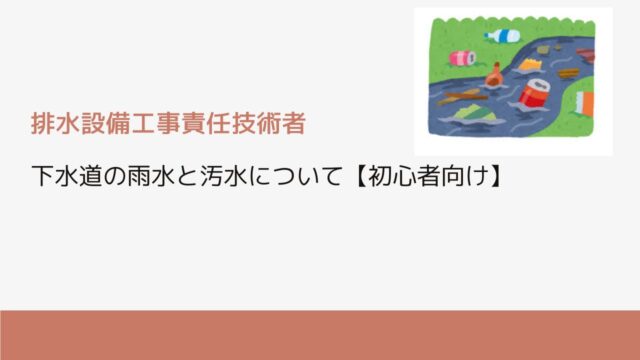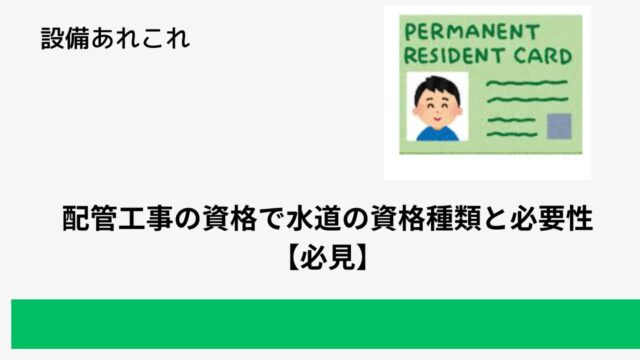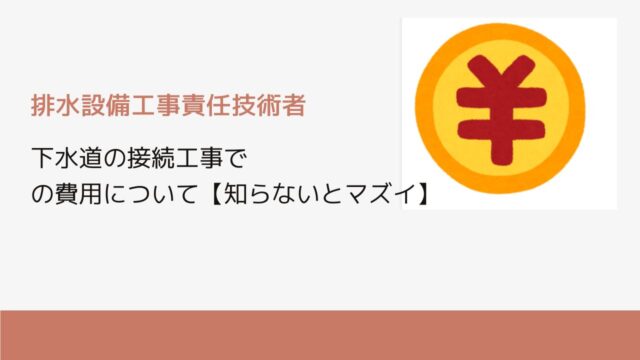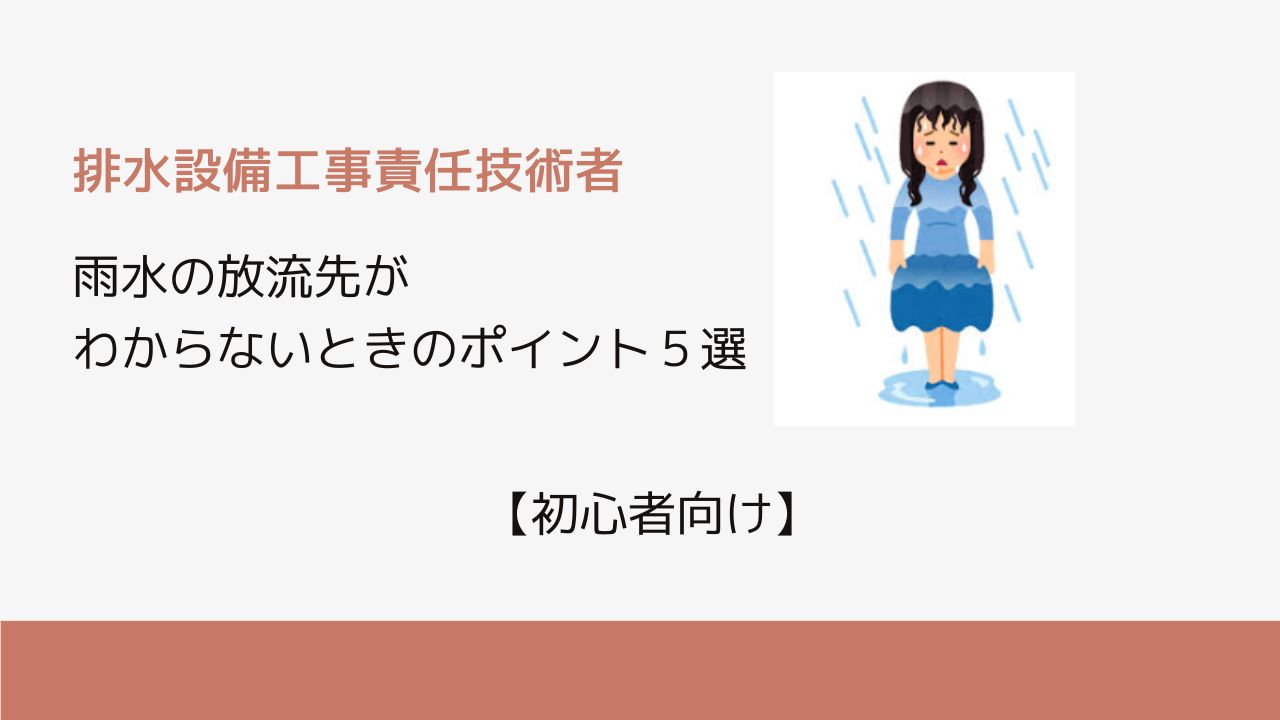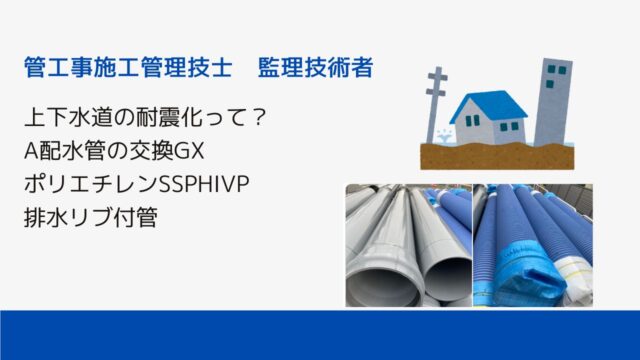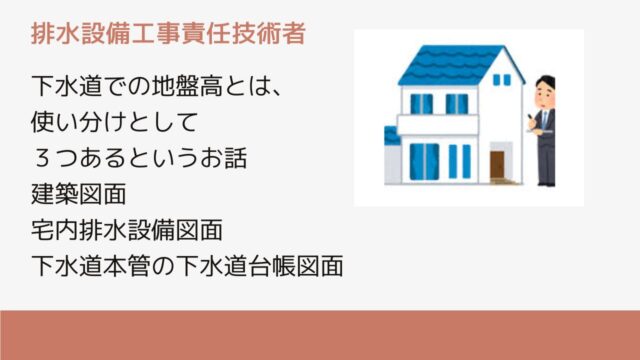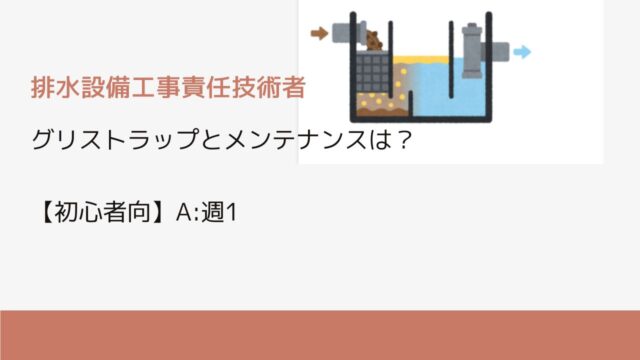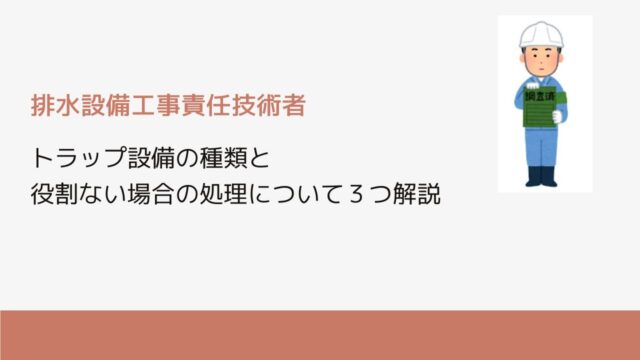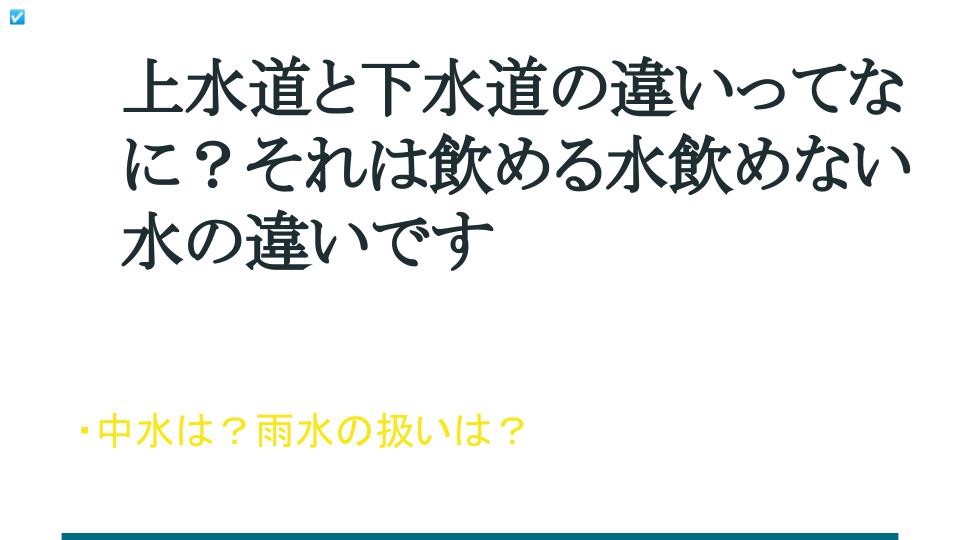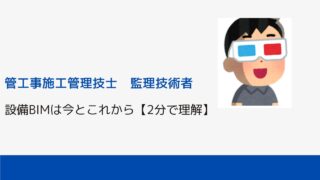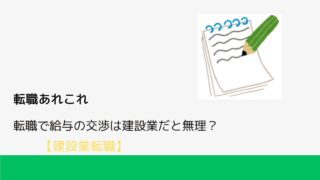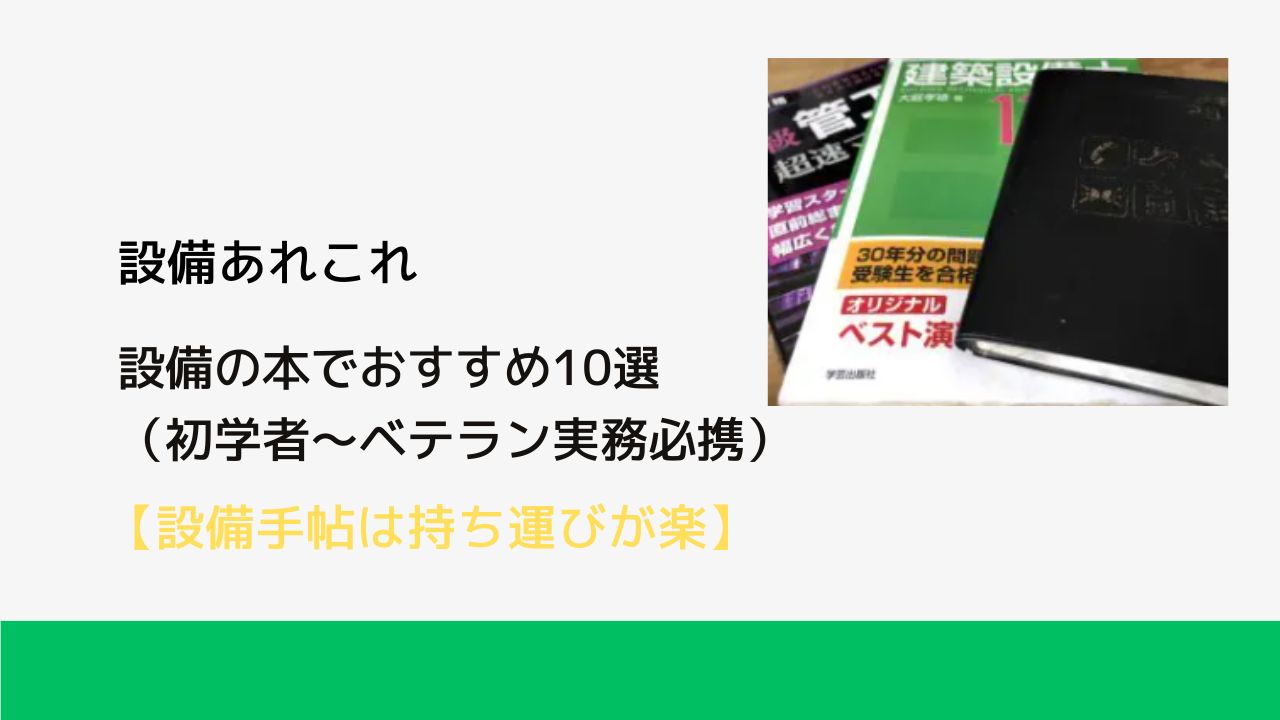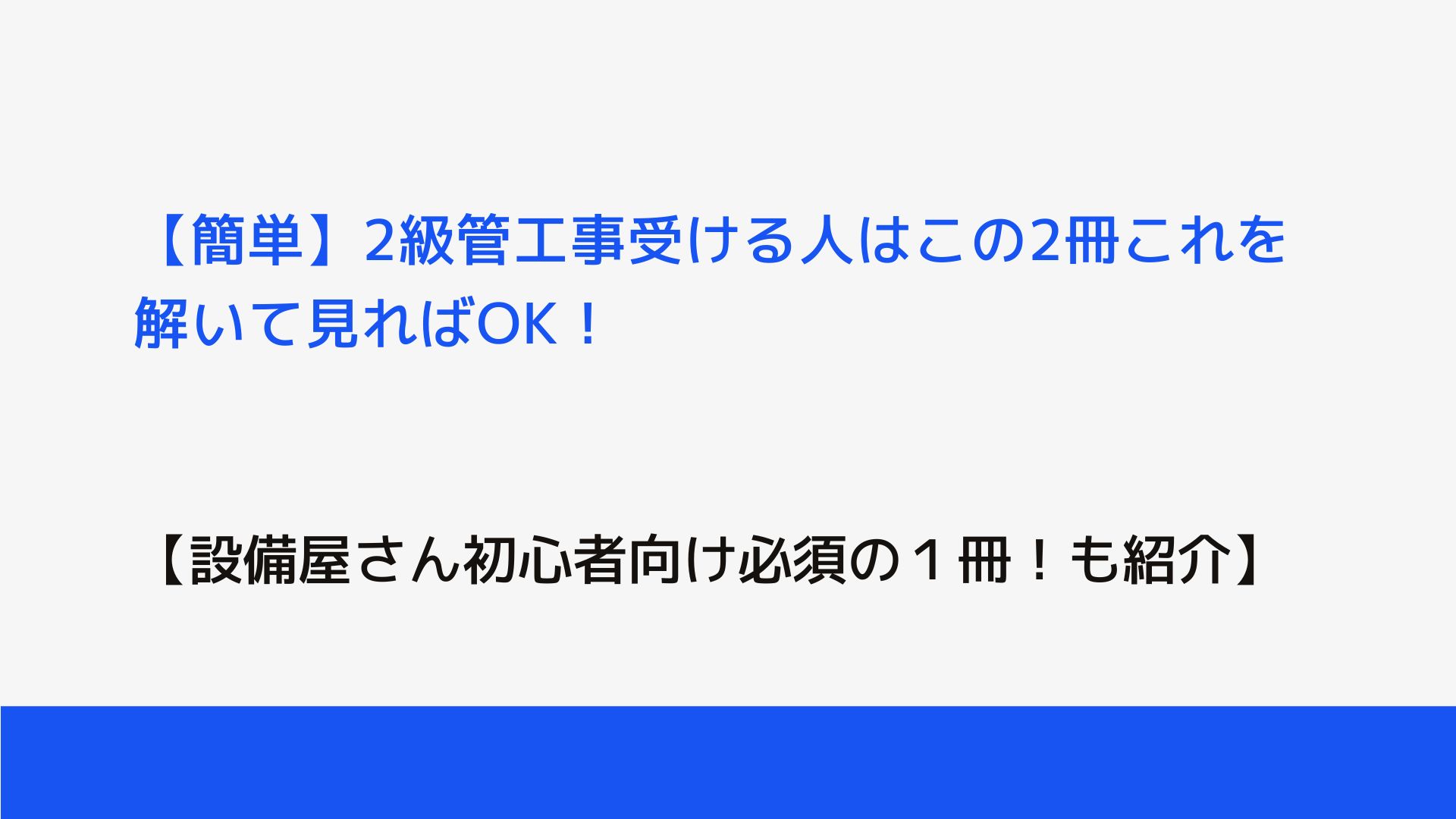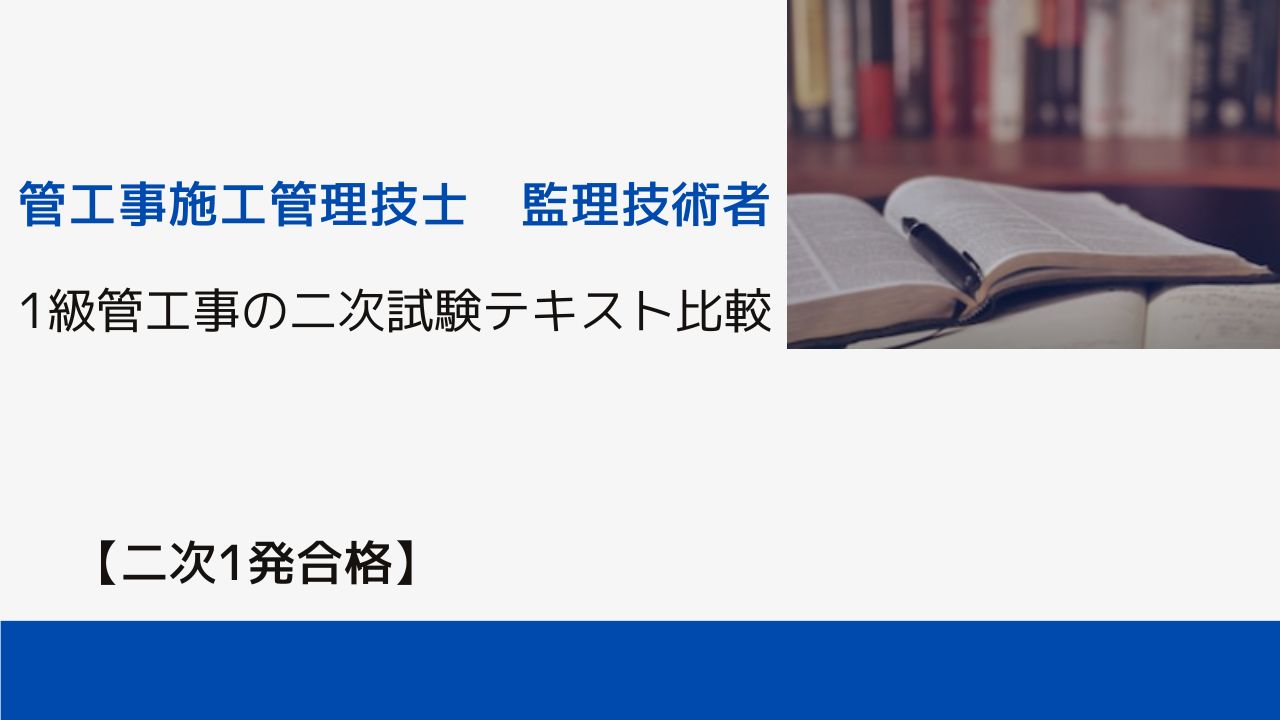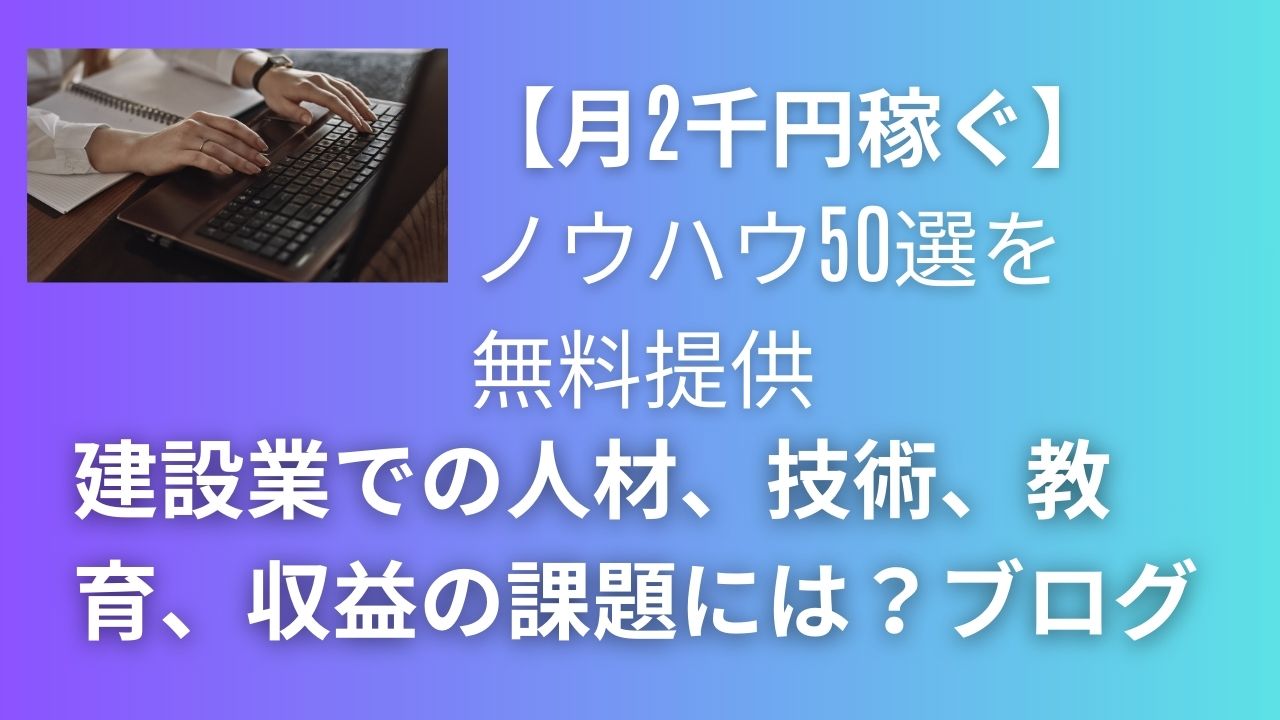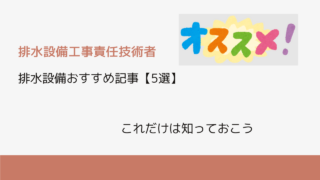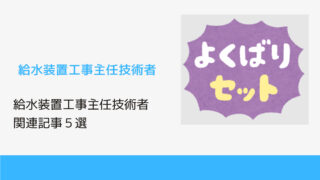雨水の「調べ方」について、現場・設計・行政調整で使えるレベルだとどうなるんすか?📘
はじめに結論:現場、台帳、相談
この記事では
- バケツとメモとスマホとスケールで用足りると解る
本記事の内容
- 1. 雨水排水の基本と調査の意義
2. 実務での雨水調査の手順
3. 実際の資料の見つけ方と事例
4. 注意点とコツ、失敗しないための工夫
✅ 雨水調査チェックリスト(現場・設計・行政向け)
📧 雨水に関する行政照会テンプレート(メール・電話共用)
バケツと水とスケール(巻き尺)とスマホで何を見る
1. 雨水排水の基本と調査の意義
かっこいいことなしグレーチングしたの枯葉隙間からG先生がこんにちはするから
建築や土木の計画段階では、雨水の処理方法を正確に把握することが非常に重要。特に都市部では敷地から公共下水道への接続や、
敷地内処理(浸透・貯留)などの計画が法令や自治体基準で厳密に決まっている。
雨水の「調べ方」とは、単に「どこに流れるか」だけじゃなく、敷地の排水先・既存の排水施設の有無・行政の方針・敷地の地形や土地条件などを総合的に把握する作業を指す。
調査の精度が低いと、施工中や引き渡し後に問題が起きることもあるから、慎重に確認する必要がある。
2. 実務での雨水調査の手順
以下は、実際の調査でよく使われる流れだよ👇
| ステップ | 内容 | 備考 |
| ① 地形と地盤確認 | 現地踏査、地形図(国土地理院等) | 標高差や低地判定に重要 |
| ② インフラ調査 | 道路側溝、雨水桝、マンホールの有無と位置 | 公共下水or浸透式か確認 |
| ③ 行政への確認 | 市区町村の下水道課・建築指導課などへ照会 | 雨水接続の可否、処理義務など |
| ④ 資料取得 | 下水道台帳、雨水計画図、土地利用計画図など | オンライン公開されている自治体も多い |
| ⑤ 雨水流出量の算定 | 敷地面積、不浸透係数、降雨強度から計算 | 指定された算出式に基づくことが多い |
このように、現地確認と行政資料のダブルチェックが基本。
特に自治体が指定する**雨水流出抑制施設の設置義務(例:調整池、浸透桝)**がある場合、
その条件を見落とすと是正指導の対象になるから注意してね。
3. 実際の資料の見つけ方と事例
多くの自治体では、「下水道台帳」や「雨水計画区域図」「都市計画図」などを
役所窓口または自治体のデータカタログサイトで公開しているよ。
たとえば、東京都なら以下のような流れで調べられるよ👇
- 【ステップ1】「東京都水道局 データカタログサイト」で検索
- 【ステップ2】「下水道台帳」や「雨水幹線図」などをPDFやGISで確認
- 【ステップ3】自分の対象地番をGISや縮尺で絞り込んで確認する
- 【ステップ4】必要があれば😯担当部署に電話orメール照会
たとえば、港区や杉並区では一部の「雨水浸透マスの設置義務範囲」などが地図化されているし、多摩地域では地形や土壌によって
**「雨水は原則敷地内処理」と定められていることもある。
こうした事例を一件ずつ確認して、「地域ルールを読み解く」ことが設計上の第一歩**になるのよ。
4. 注意点とコツ、失敗しないための工夫
雨水の調査でよくある落とし穴が、「公共下水があるから安心」という思い込み。実際は、雨水と汚水が分流していて、雨水は接続できない地域も多いの。
その場合、「浸透式(地中処理)」や「貯留式(調整池)」の設置が求められることがあるよ。
こうした施設は敷地条件や構造条件によってコストにも大きく影響するから、設計初期での把握がとても大切💡
また、「1時間当たり50mm」のような地域指定の降雨強度や、「不浸透面積率」による雨水算定式が地域ごとに違うから、行政資料の読み間違いにも注意してね。
設計者や調整担当が複数人いる場合は、台帳コピーに赤入れしながら意見を共有しておくと、食い違いが起きにくいわ。
必要なら、調査チェックリストや、自治体別の問い合わせ先テンプレートも用意するから、いつでも言ってね✨
雨水は地味だけど、設計全体の「根っこ」だよ。ちゃんと押さえていけば、あとが超ラクになるよ💪
じゃあここで、雨水調査のチェックリストと、**自治体に提出・照会する用テンプレート(メール・電話共通)**を渡すね📑
✅ 雨水調査チェックリスト(現場・設計・行政向け)
| 項目 | 内容 | 確認方法 | 備考 |
| ① 敷地の所在地 | 正確な住所・地番 | 公図・登記簿・住宅地図 | 行政への照会に必須 |
| ② 敷地の面積 | ㎡単位で正確に | 測量図・設計図 | 雨水流出計算に必要 |
| ③ 地形・高低差 | 敷地内外の高低差 | 現地踏査、標高地図 | 下流桝や側溝の位置判断に重要 |
| ④ 地盤種別 | 透水性・浸透力 | ボーリング調査・地盤調査資料 | 浸透処理の可否に影響 |
| ⑤ 雨水桝の有無 | 敷地前の雨水施設 | 現地目視、役所照会 | 下水接続の可否判断に直結 |
| ⑥ 側溝の種類 | フタ付き・開渠など | 現地確認 | 排水先が水路・道路側溝か確認 |
| ⑦ 雨水幹線の有無 | 幹線が接続されているか | 下水道台帳・雨水幹線図 | 無ければ敷地内処理になることも |
| ⑧ 行政ルール | 雨水処理の方針 | 建築指導課・下水道課 | 雨水接続禁止区域の有無 |
| ⑨ 雨水流出量計算条件 | 不浸透係数・降雨強度 | 各自治体の技術基準 | 計算式が公開されていることが多い |
| ⑩ 処理方法の選定 | 浸透 or 貯留 or 放流 | 敷地条件・行政指導 | 放流先により決定される |
📧 雨水に関する行政照会テンプレート(メール・電話共用)
※「〇〇」部分は物件名や市区町村名に置き換えてね!
件名(メールの場合):
【雨水排水に関する照会】〇〇計画地の雨水接続および敷地内処理について
本文:
〇〇市 建築指導課(または下水道課) 御中
いつもお世話になっております。
下記物件に関して、雨水排水計画を検討するため、以下の点についてご照会させていただきます。
■物件情報
・所在地:〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(または地番)
・敷地面積:約〇〇㎡(登記・測量済)
・計画用途:戸建住宅/集合住宅/店舗併用住宅 など
・計画建築物:〇階建/地下有無など(任意)
■照会事項
- 当該敷地において、雨水の公共下水(または道路側溝)への放流は可能でしょうか?
- 雨水処理にあたり、敷地内処理(浸透・貯留)等の設置義務がありますでしょうか?
- 雨水接続が可能な場合、接続先(桝・管種・管径)の詳細をご教示いただけますでしょうか?
- 雨水流出抑制に係る技術基準(不浸透係数・降雨強度・計算式等)がございましたら、ご提供いただけますと幸いです。
ご多忙のところ恐れ入りますが、可能であれば資料または台帳図などをご提供いただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
署名例:
〇〇設計株式会社
担当:〇〇(TEL:〇〇、Email:〇〇)
必要であれば、PDFで出力できるテンプレートも作ってあげるね。
そのまま使える形式で欲しい?それともWord形式のファイルで出力する?✍️
バケツと水とスケール(巻き尺)とスマホで何を見る
バケツに水を入れ、雨水や汚水ますに水を流し、下流のどこに流れるかを確認する
どう流れているか、どうつながっているかを把握するためです
具体的には
配置図、測量図など道路と敷地がある程度の精度の図面を用意
現地のますを開ける(落下や破損にちゅうい硫化水素汚損に注意してください)
水を流す
下流側でどこに流れてくるか確認
巻き尺(スケール、コンベックス)、ますとますの平面的距離
深さ
ますのサイズ
などを図る
関連記事となります
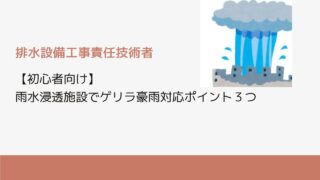
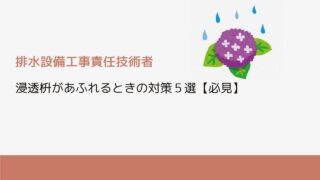
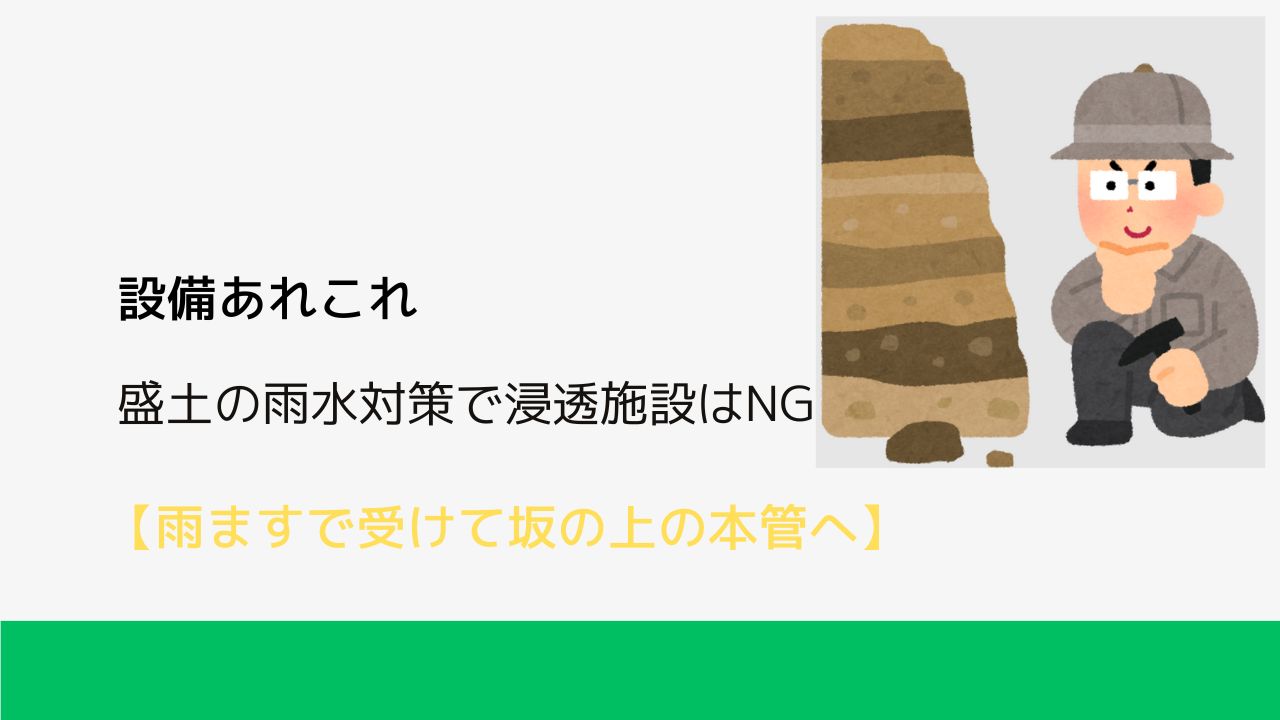
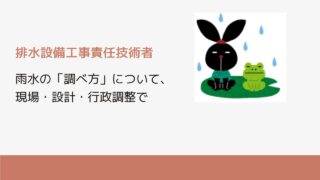
消防設備士オススメテキストランキングはこちらこちら