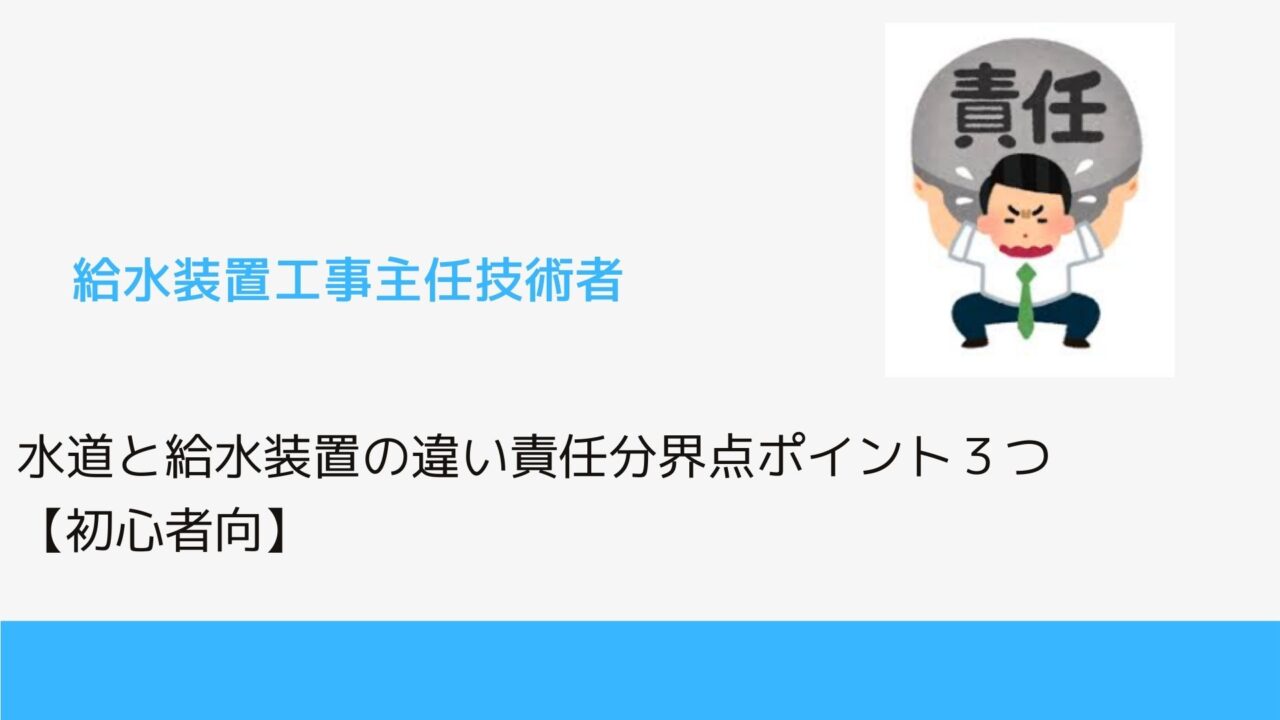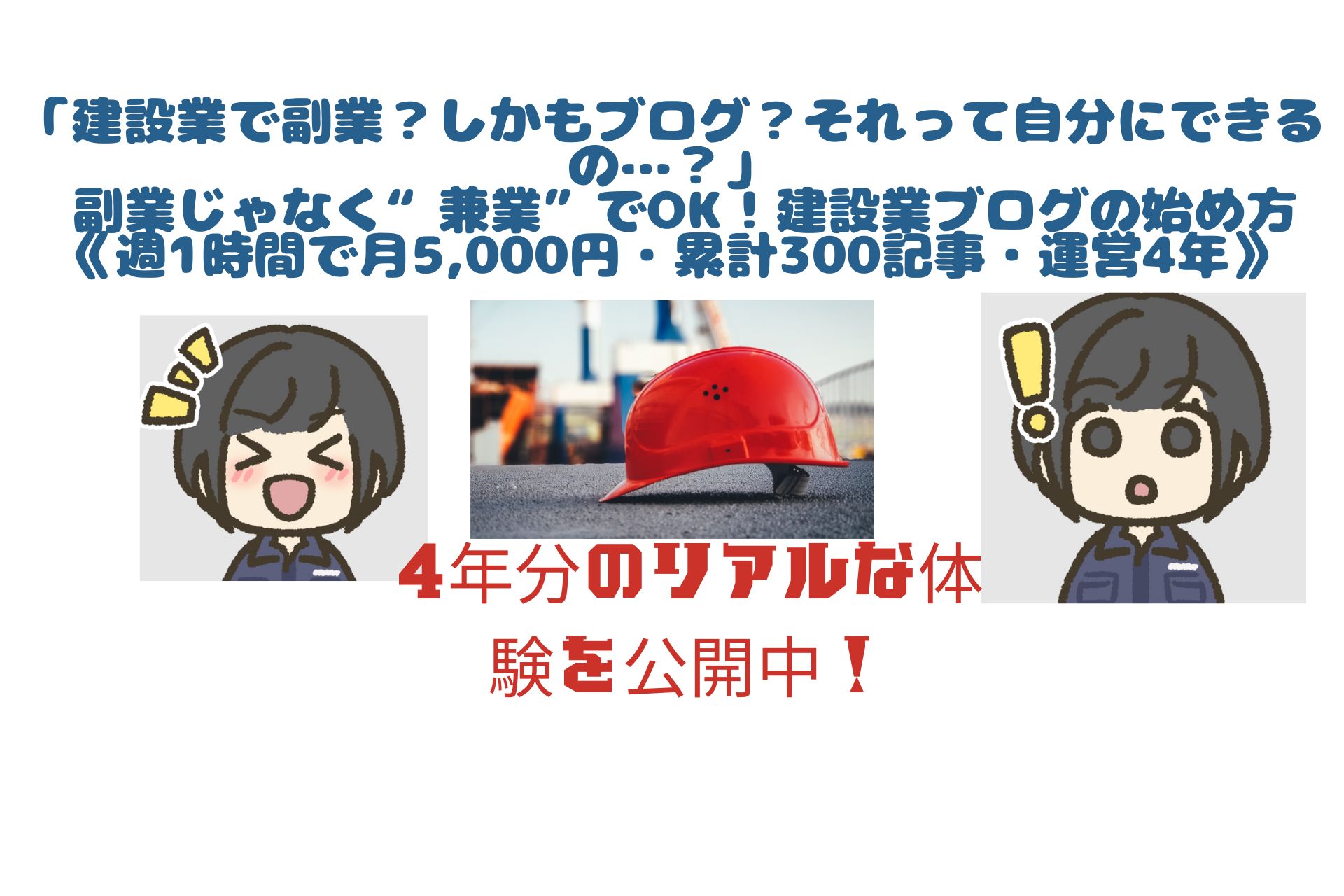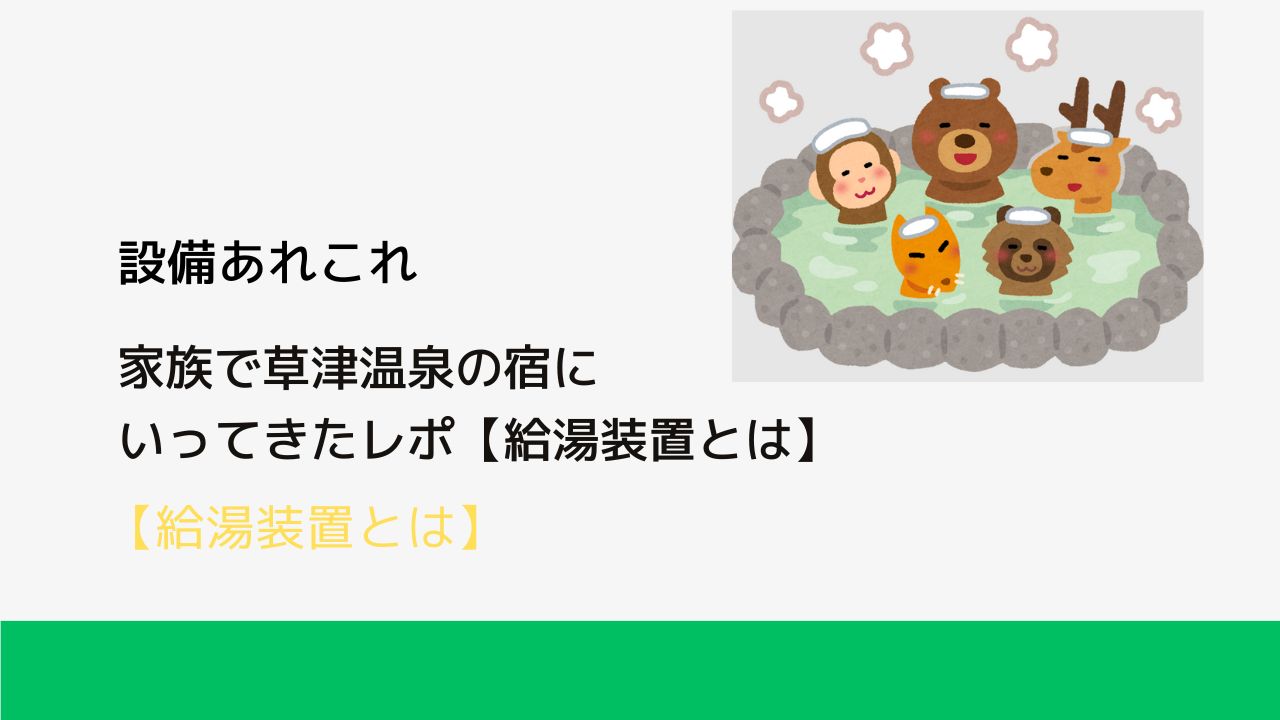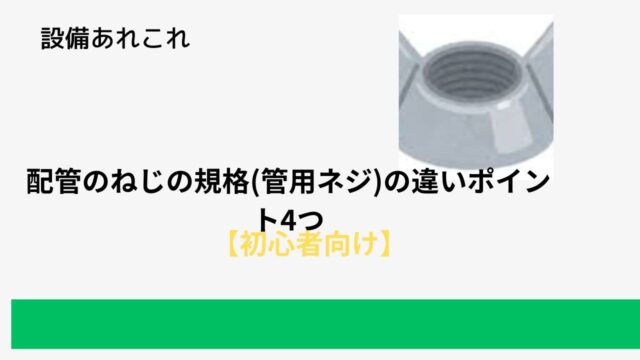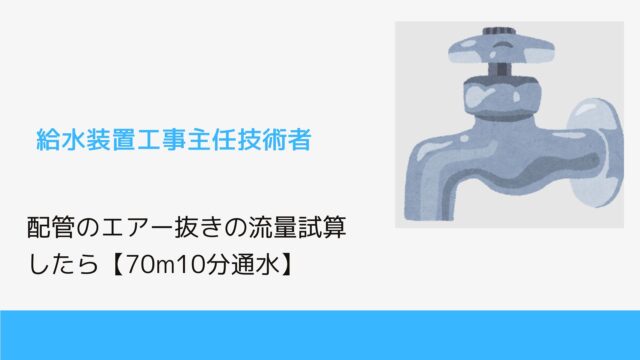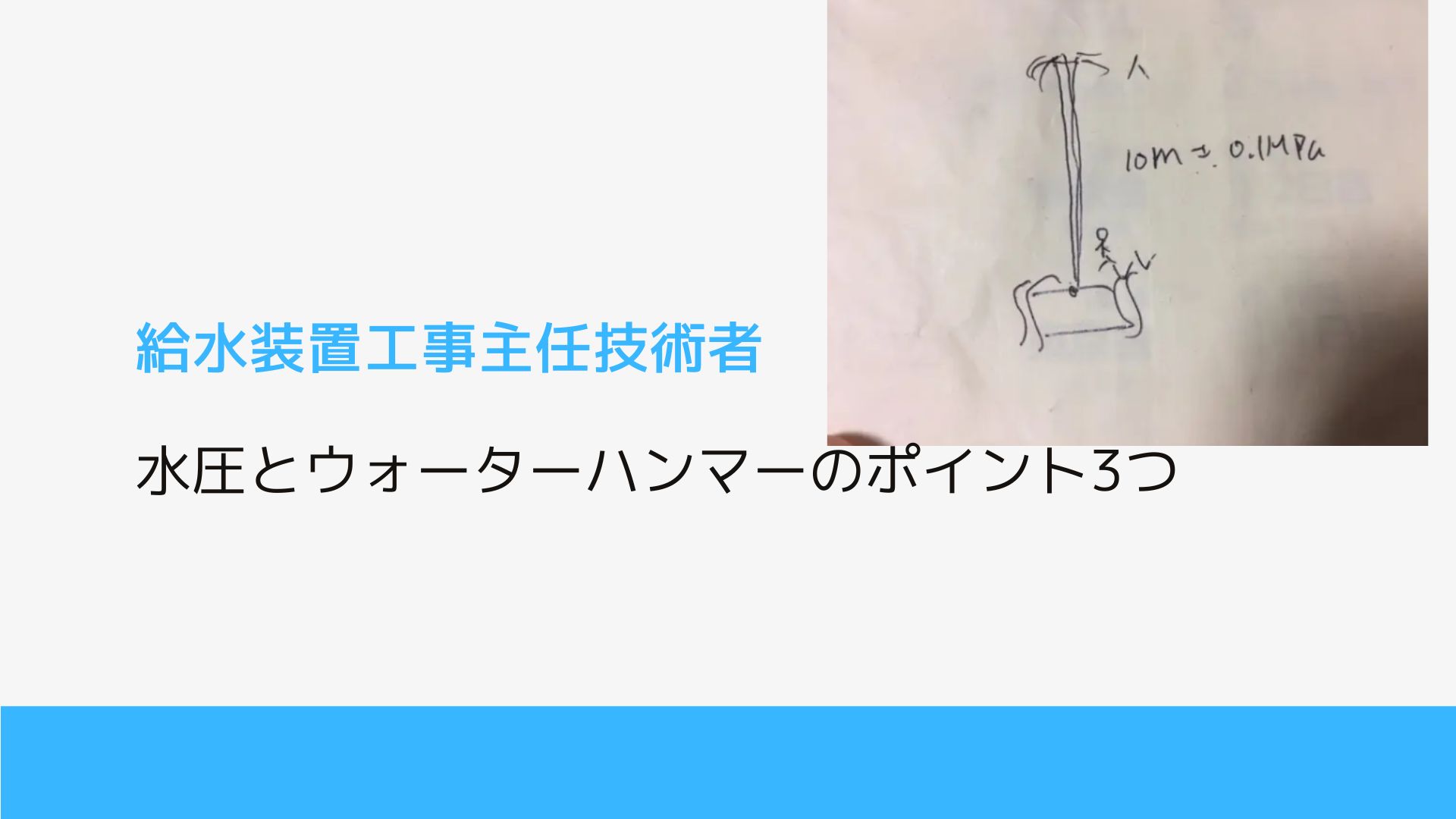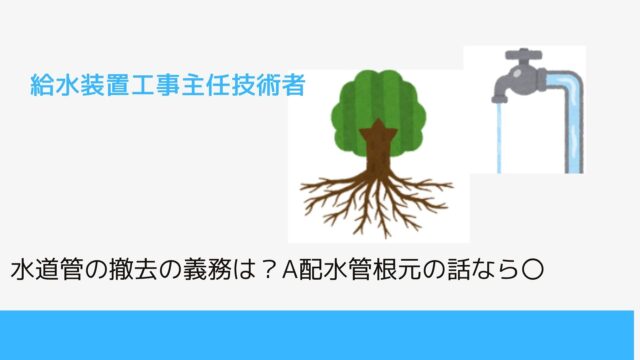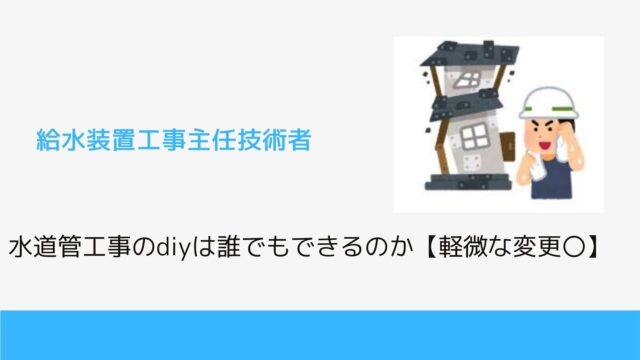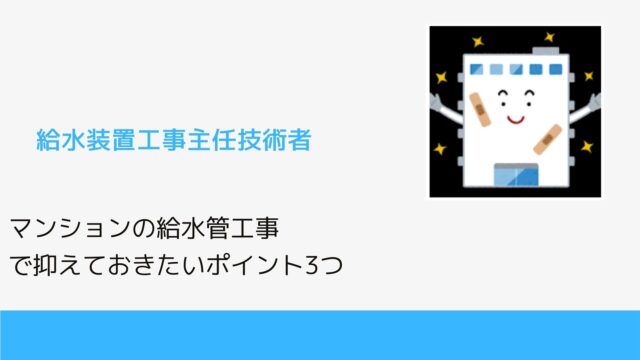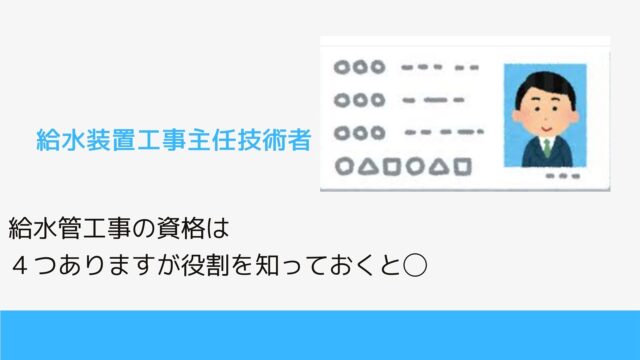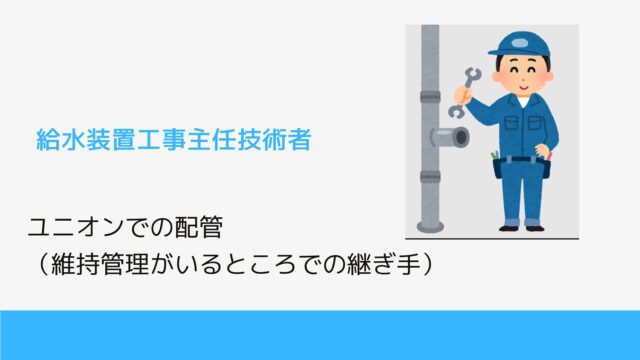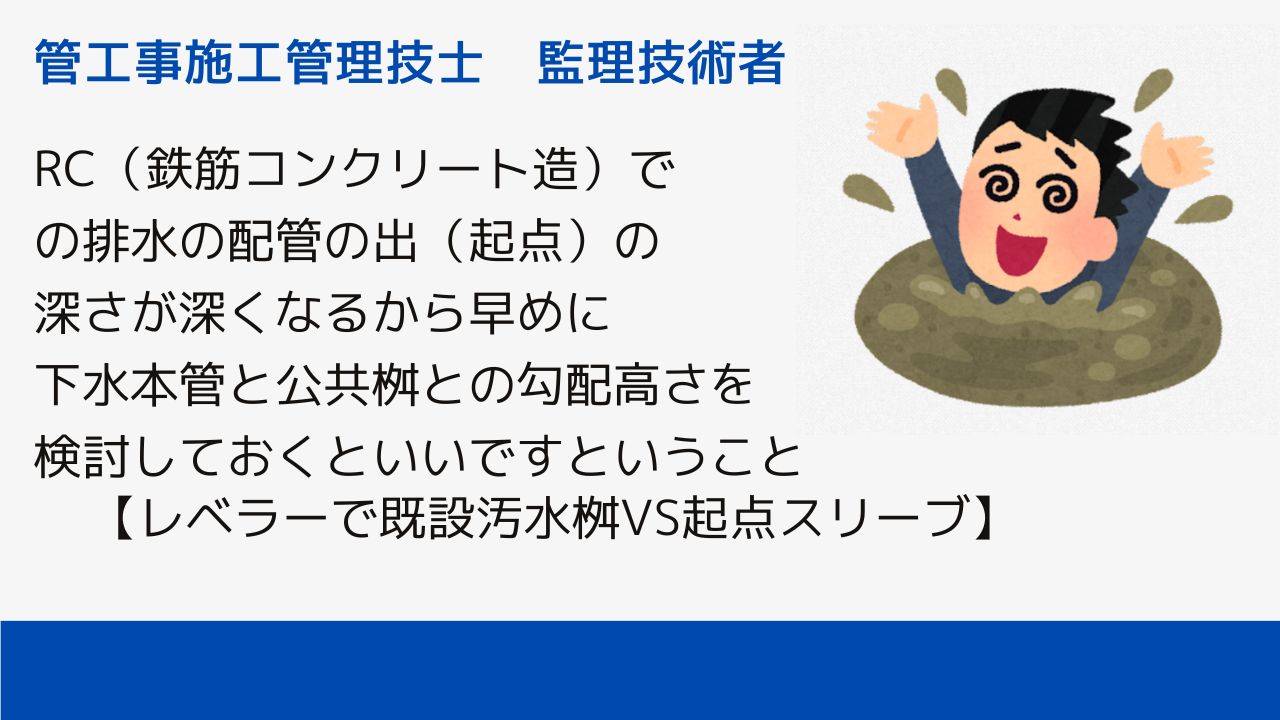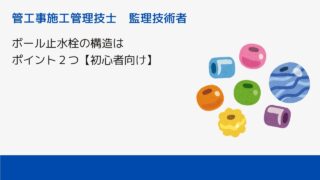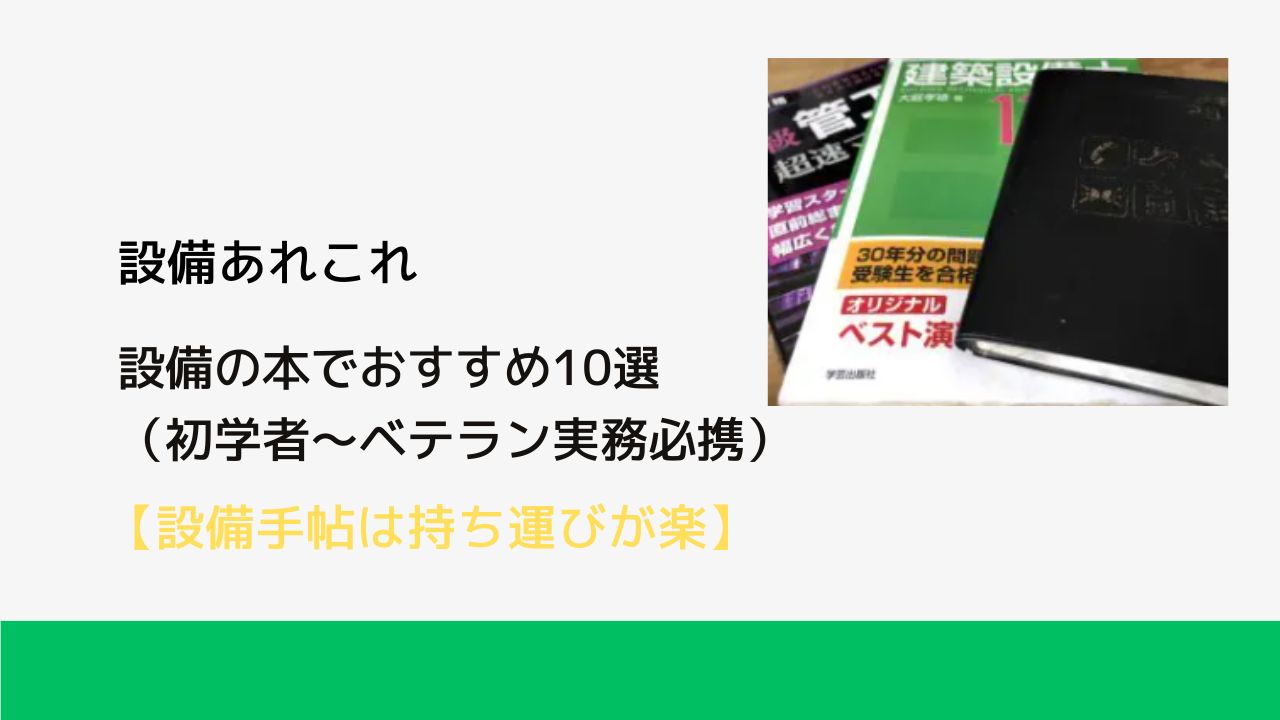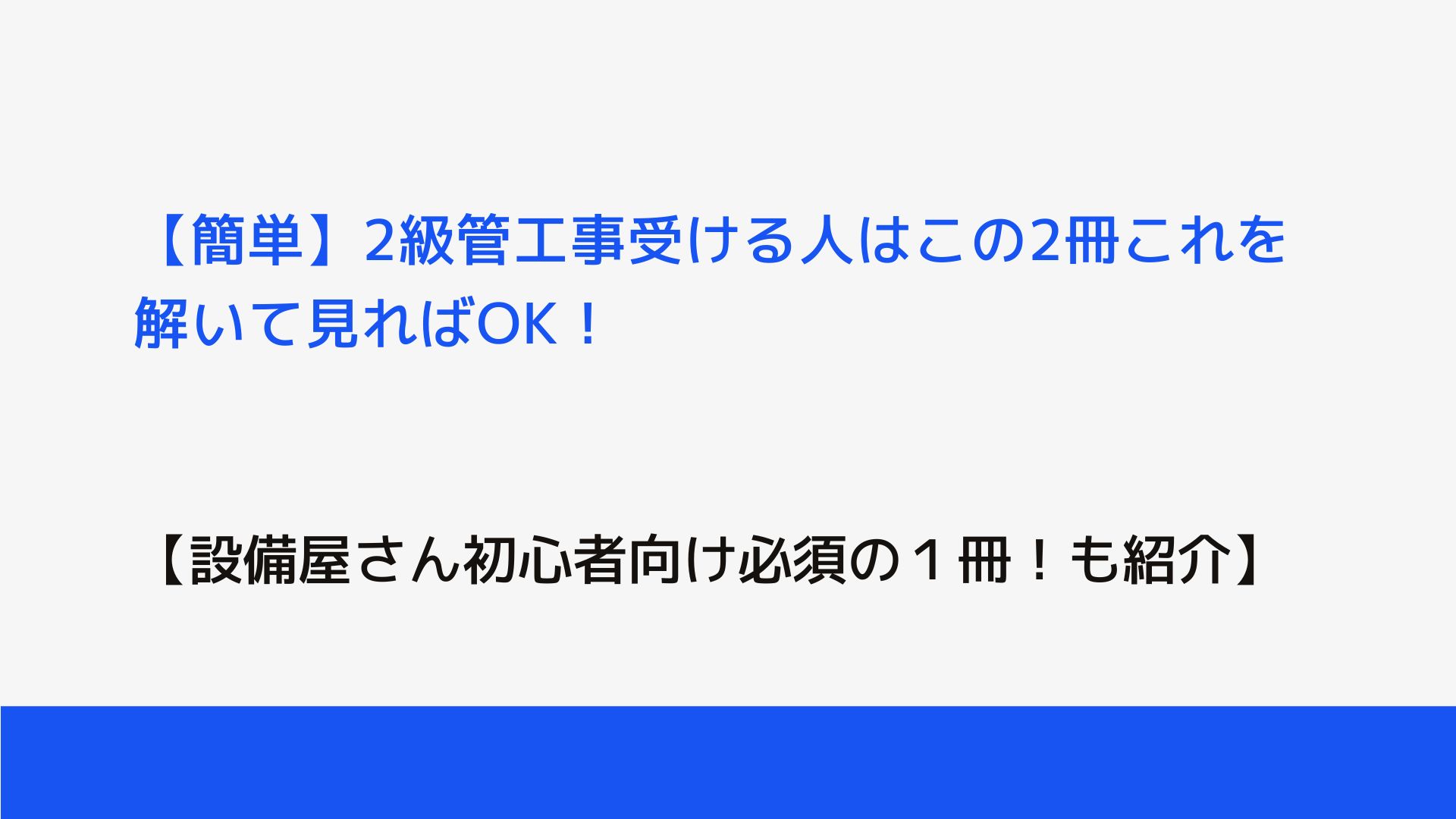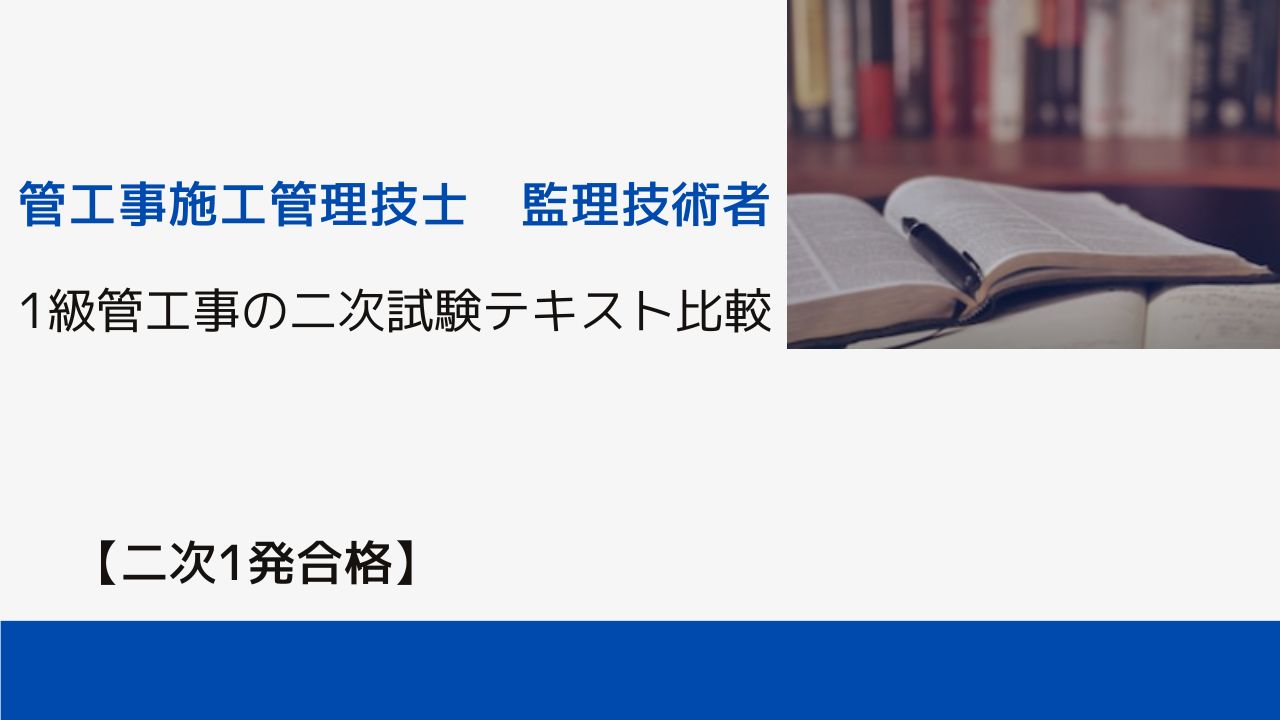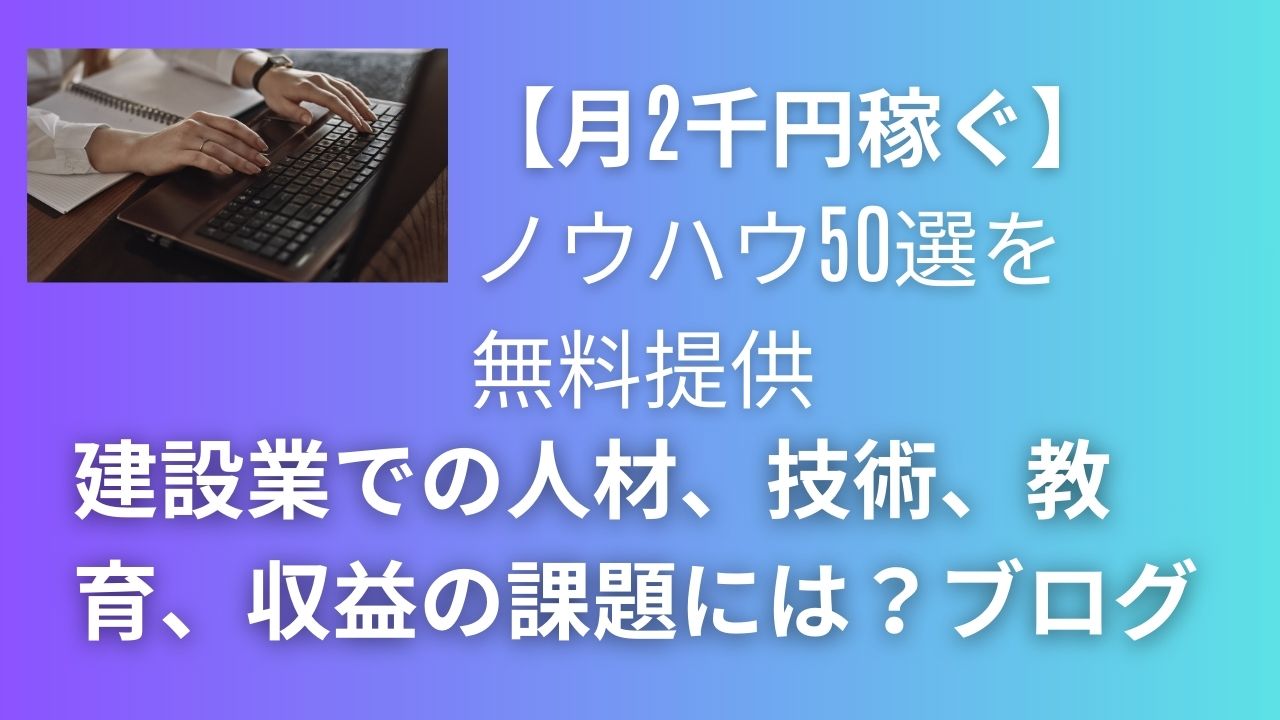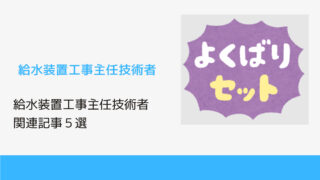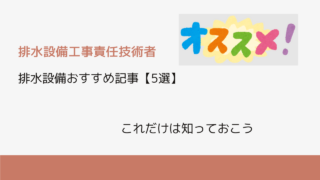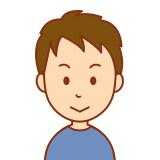
水道と給水装置
なんか違うみたいだけど、よくわかんないよね。
という方への記事となります。
A:(受水槽BTと吐水口マデが給水装置ですそれより下流(タンク)
以下が水道です(給水装置ではない))
本記事の内容
- 責任をわける部分が受水槽のBT(ボールタップ)といううきまでという話
- 直結直圧での配水管からの給水という基準
- 受水槽以下が安全でないというわけではないというはなし検査基準もある10t以上2t以上
責任をわける部分が受水槽のBT(ボールタップ)といううきまでという話
なんか大きく出ましたが、水道と給水装置は何が違うのかということです。
水道は結構一般的に通用する言葉ですが、
給水装置だと、水道屋さんでないと、
しかも、水道局とやり取りする
業者でないと、あまり理解されない言葉だと思います。
平たくいうと、水道メータ払い出しや、水道の配水管からの分岐、という穴を開けて宅地に水を引き込む施工に関わらない限りあまり縁のない話となります。
改修だけの施工業者さんですとか、施工だけの職人さんですとかは
あまり関係はあれど、接点のない言葉となります。
では、給水装置はなにかという部分ですが、
水道局が認めました水道の配管や器具などですよ、という部分です。
代表的な例ですと、受水槽方式のタンクの上流側は給水装置ですが、タンクの下流側は
水道となります。
細かく言うとボールタップまでが、
給水装置となります。
まあ、わかりにくいのが、
受水槽の下流側にも、水道局のメータもつくことがあるのですが、あくまで計量のためのメータであり、
給水装置とするメータとは物は同じでも責任分界点は
あくまでボールタップまでが給水装置となります。
それでも、ボールタップ以下の水道部分の
図面提出を設計事務審査という、いわゆる申請時に提出をもとめられることも多いです。
直結直圧での配水管からの給水という基準
なんでよ?という部分ですが
配水管からの直結での給水用具があくまで給水装置の定義の範疇なので、
受水槽以下は、管理者所有者の責任のもと、ちゃんとやってね?
というのがスタンスなのです。
いまでは増圧ポンプというものがあるので、
その緩め?な水道局はここまで、という責任ではなくなってきている体ですが、
それでも層厚ポンプ以下の責任は基本的には給水管の所有者であるという
傾向は否定できない気がします。
あくまで分岐から宅内1発目の止水栓までのラインはゆずれない雰囲気はありますね。
受水槽以下が安全でないというわけではないというはなし検査基準もある10t以上2t以上
10立米≒10t以上は2024年4月から国土交通省と環境省(以前は厚生労働省)もしくは関連機関の許可を受けた業者による
維持管理が義務であります。
(たまに泳ぐ人もいるらしいが)
受水槽は容量10立米以下は規定が緩く10立米以上の場合のような法定点検の義務の
対象外であるのが、
この区分の理由のようです。2立米では防虫網の設置義務があるくらいだったきがします。
都市部では受水槽を使わない、配水管から直接繋ぐ直結直圧式や、
増圧ポンプというポンプを使う直結増圧式、
配水管から同じく直接繋ぐ比較的多所帯、高層階向けの特例直圧給水方式
などが主流となってきています。
あくまで都市部での例ですが
昔と比べ、配水管水圧が高くなり、水量の確保がしやすくなったことが理由と思われます。
道路上の公設管私設管と水道局管理範囲については下記記事で書いています。
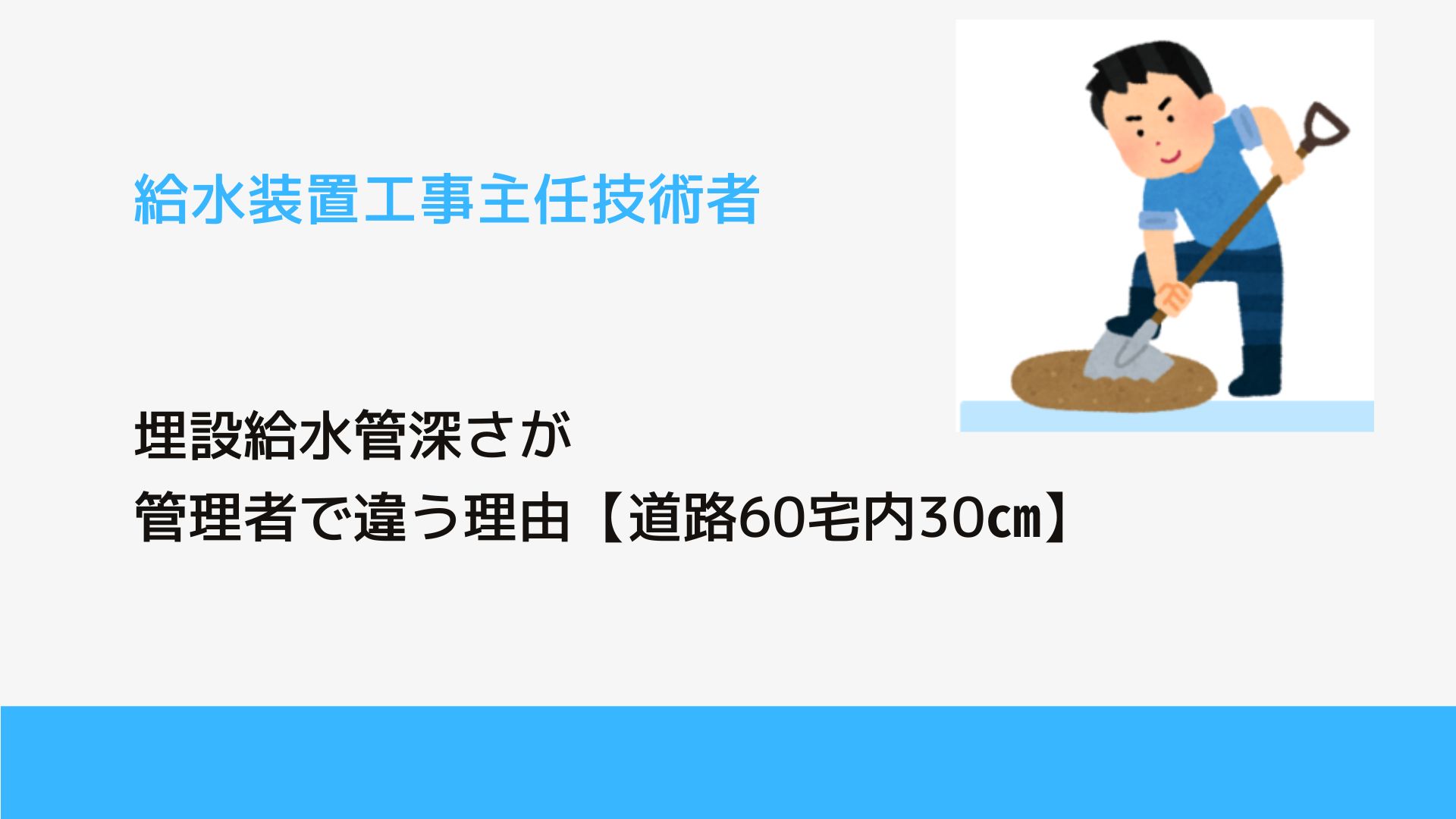
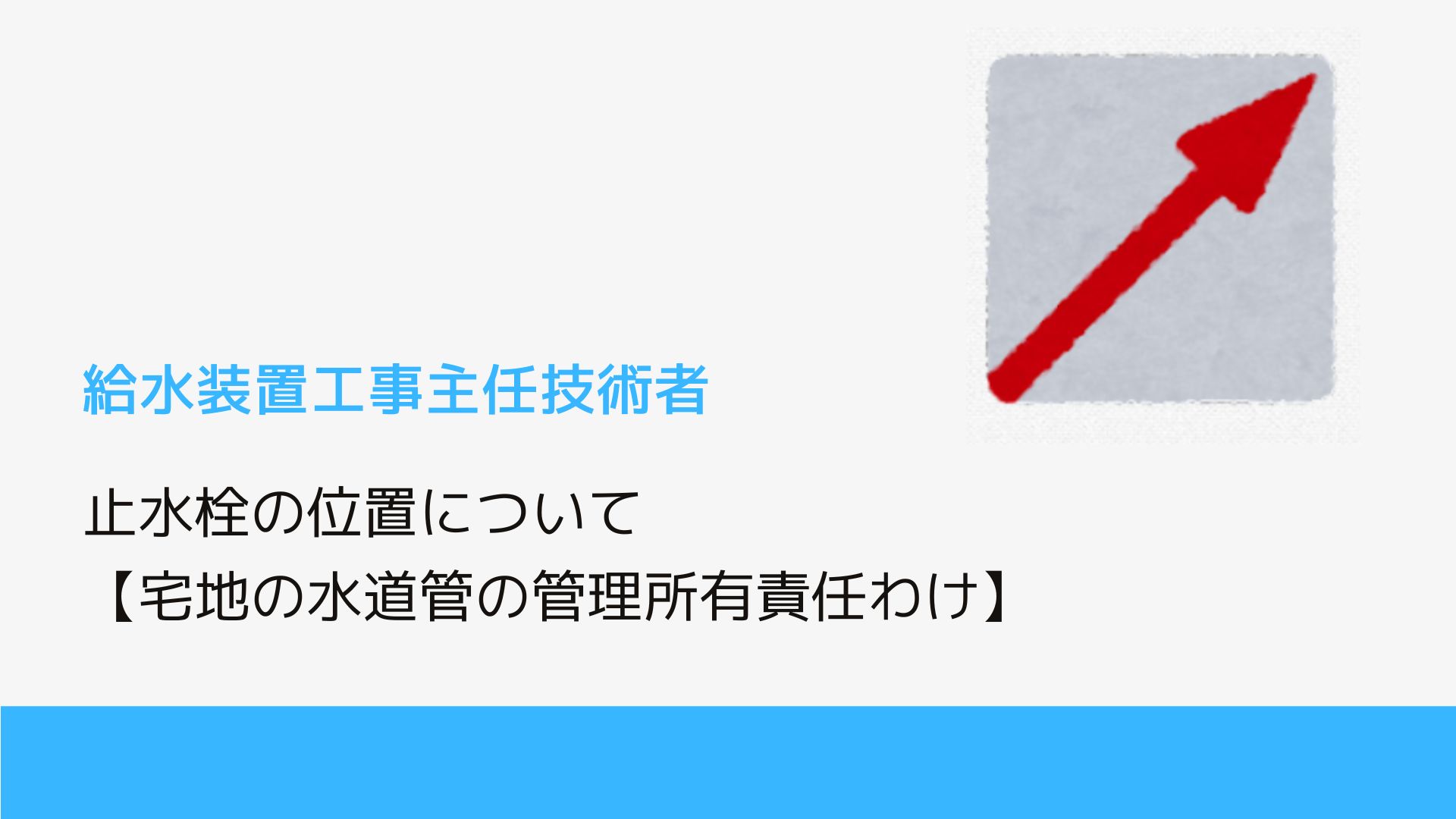
消防設備士オススメテキストランキングはこちらこちら