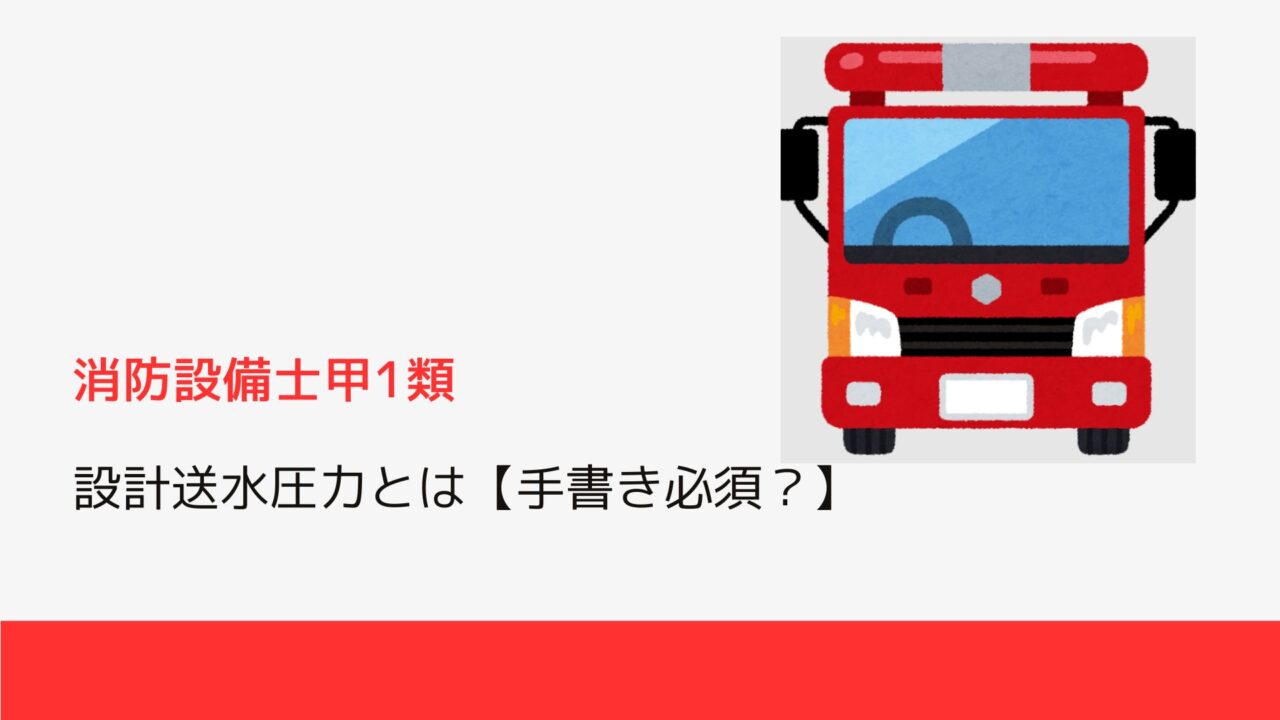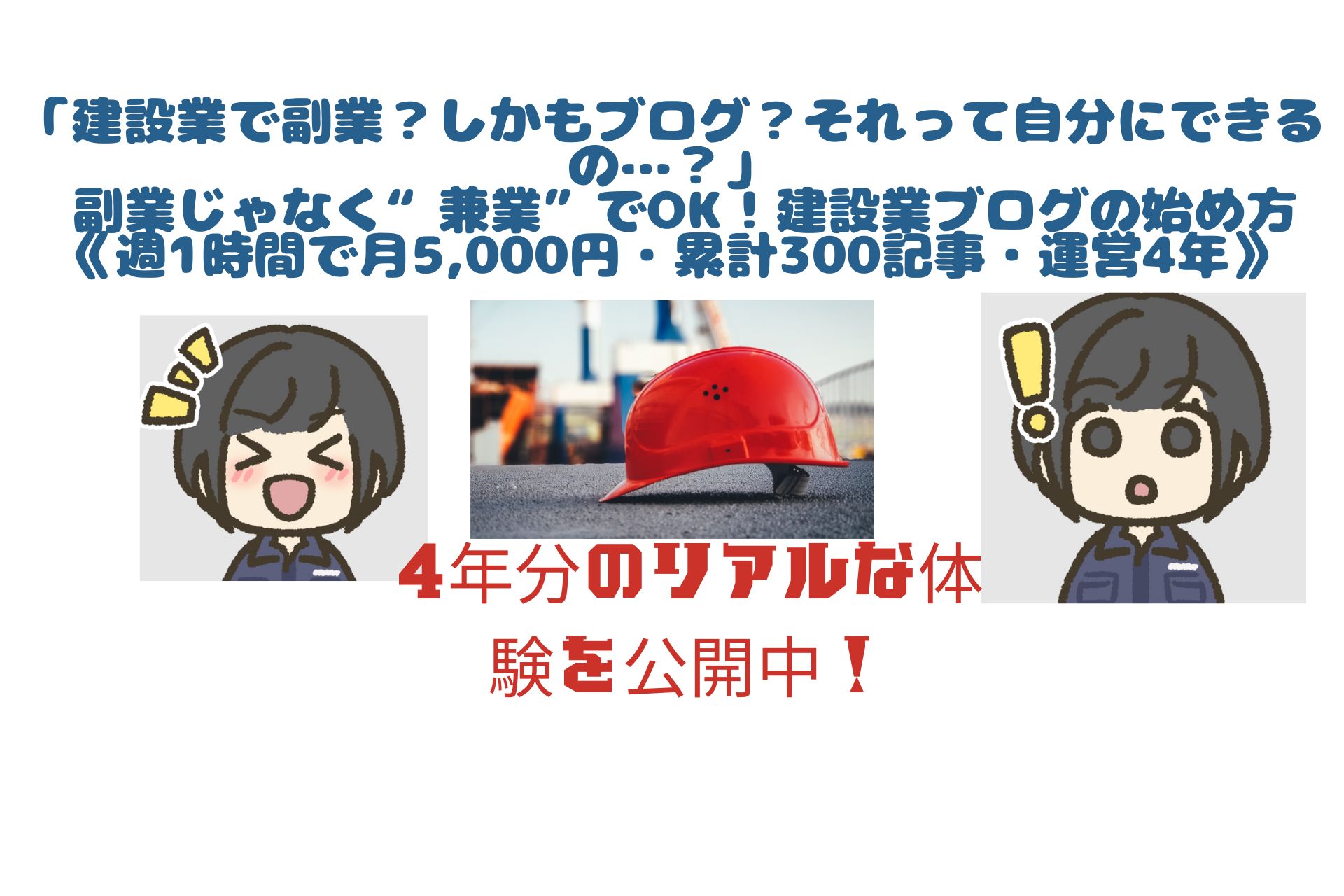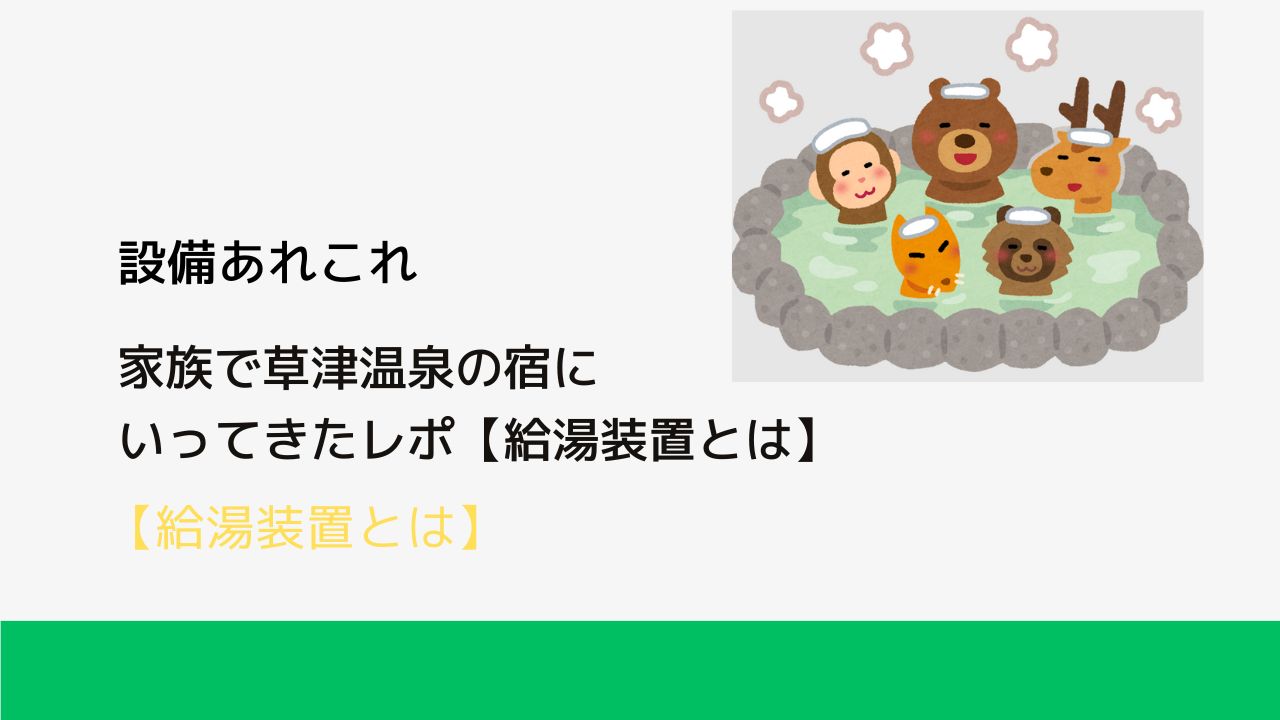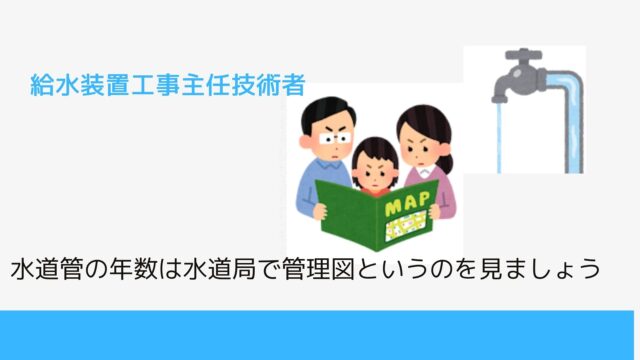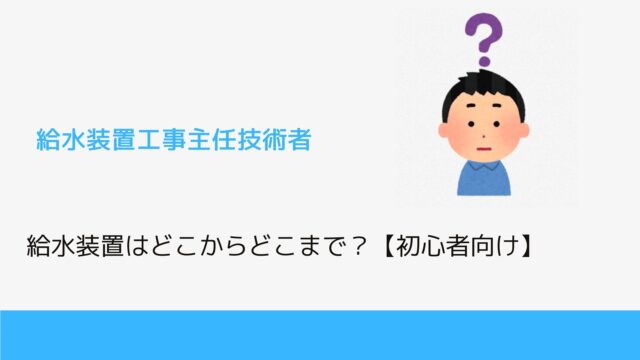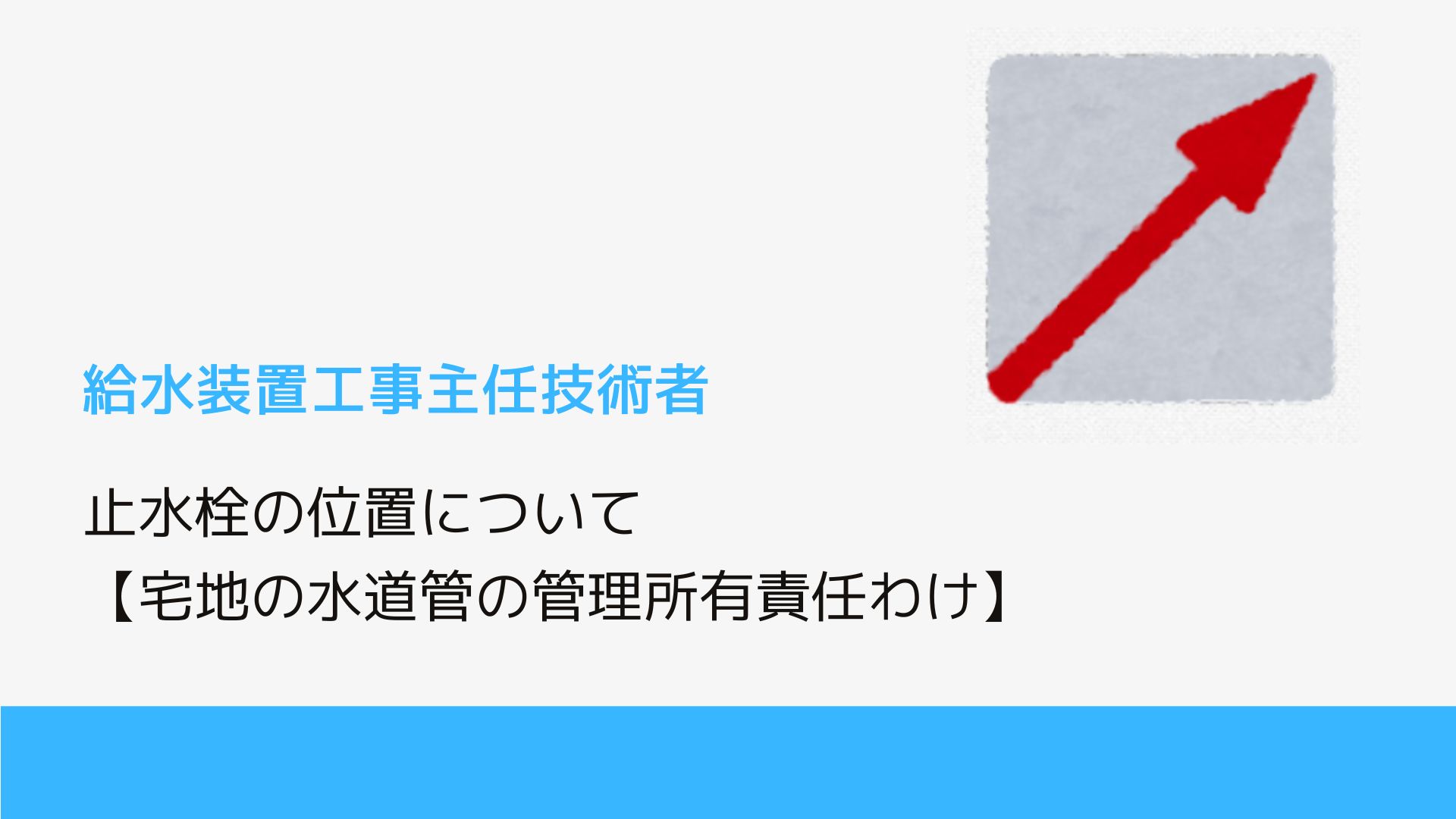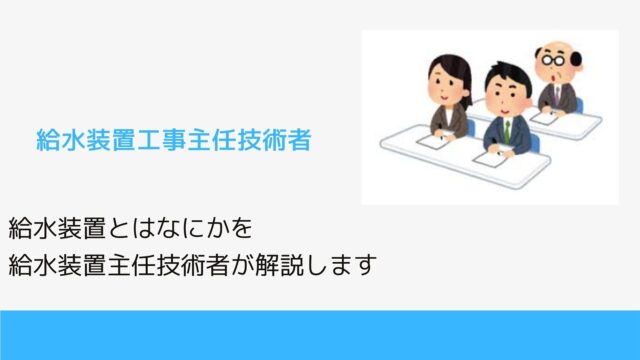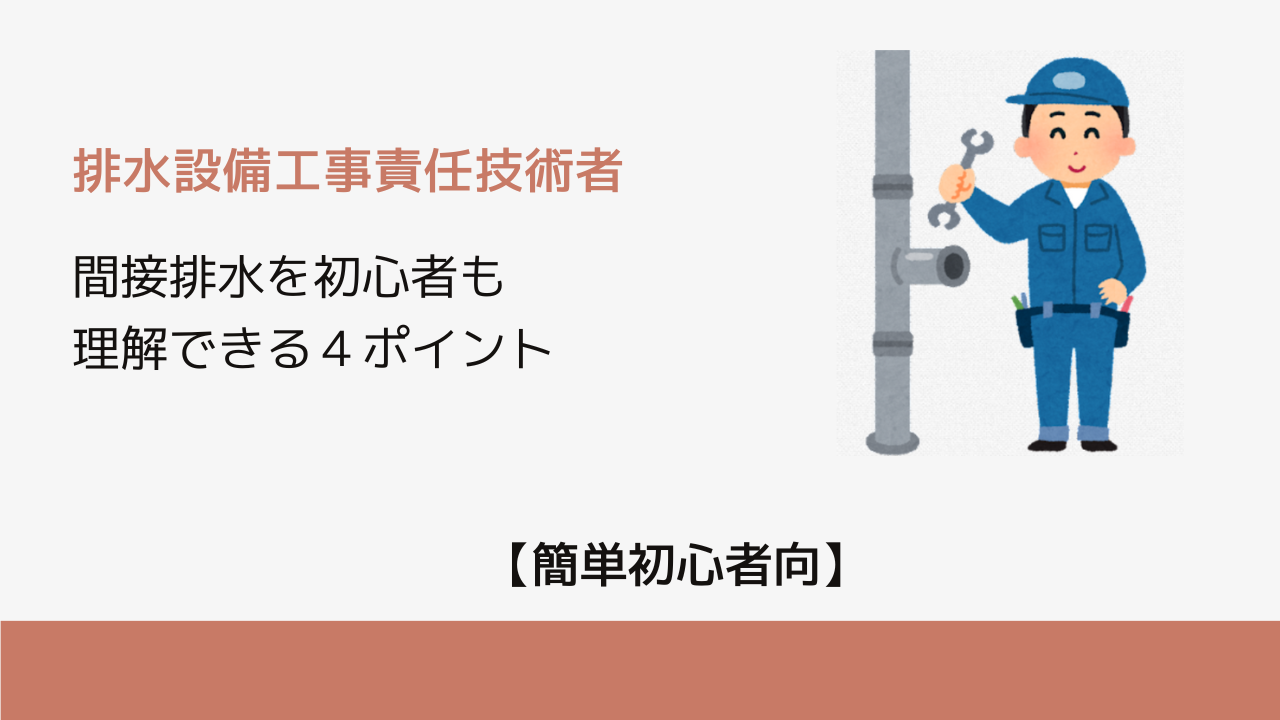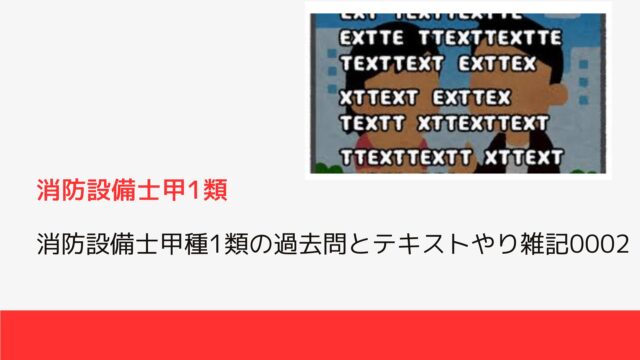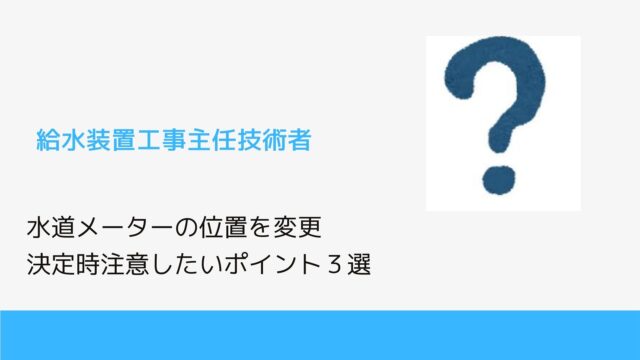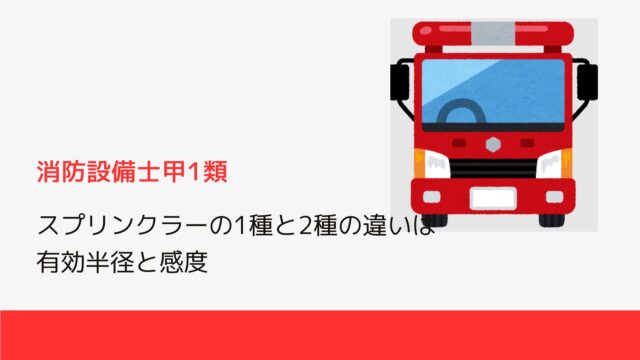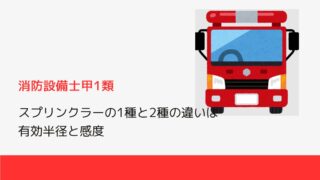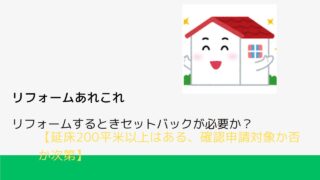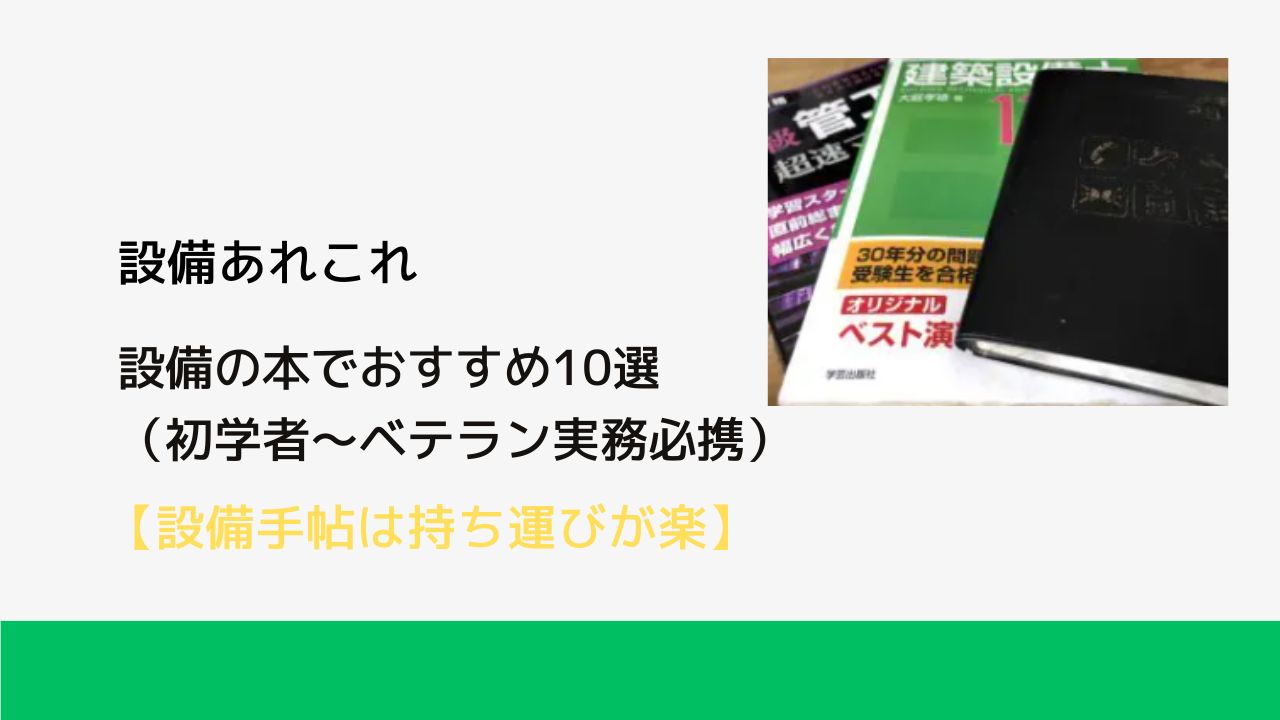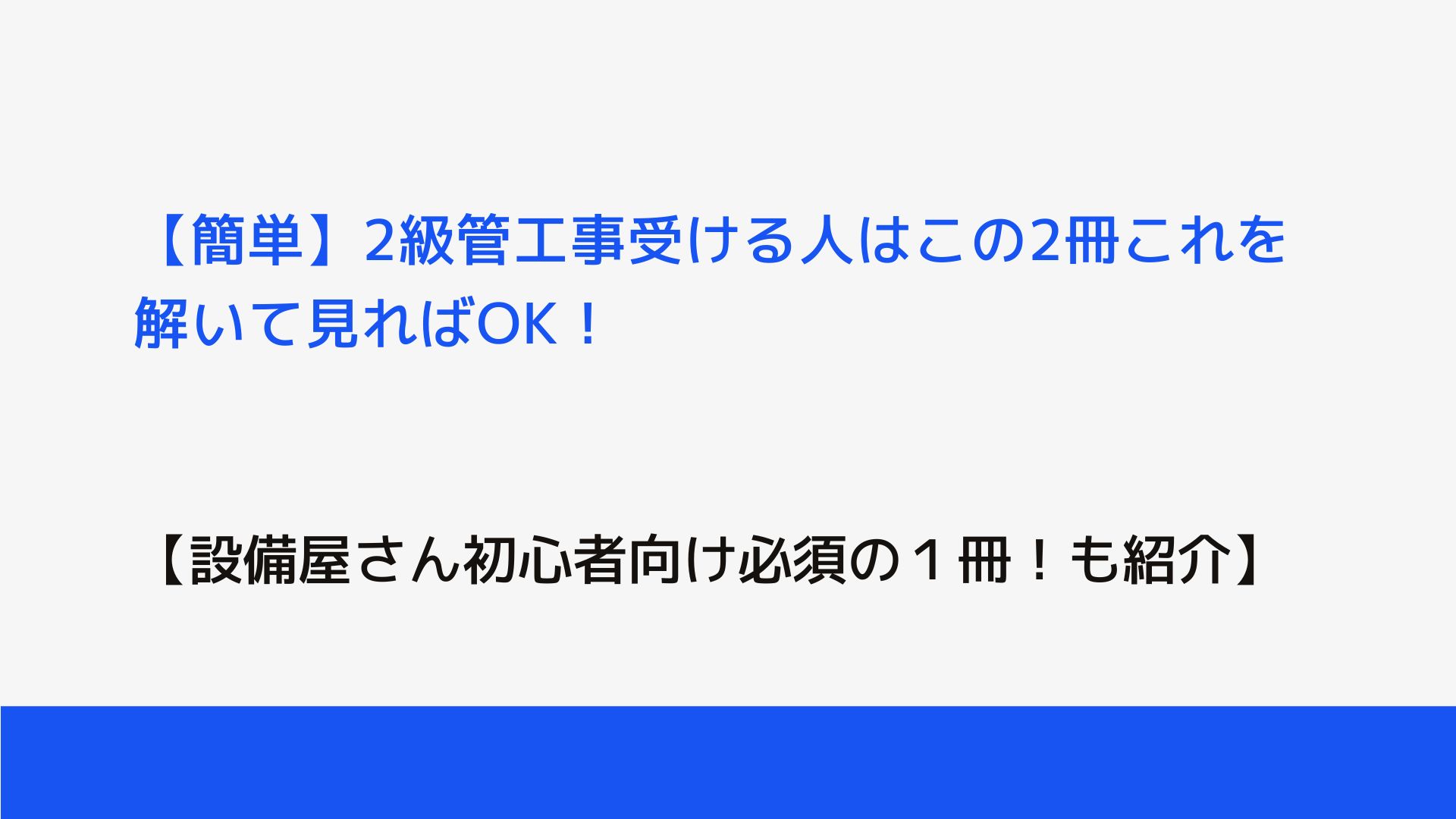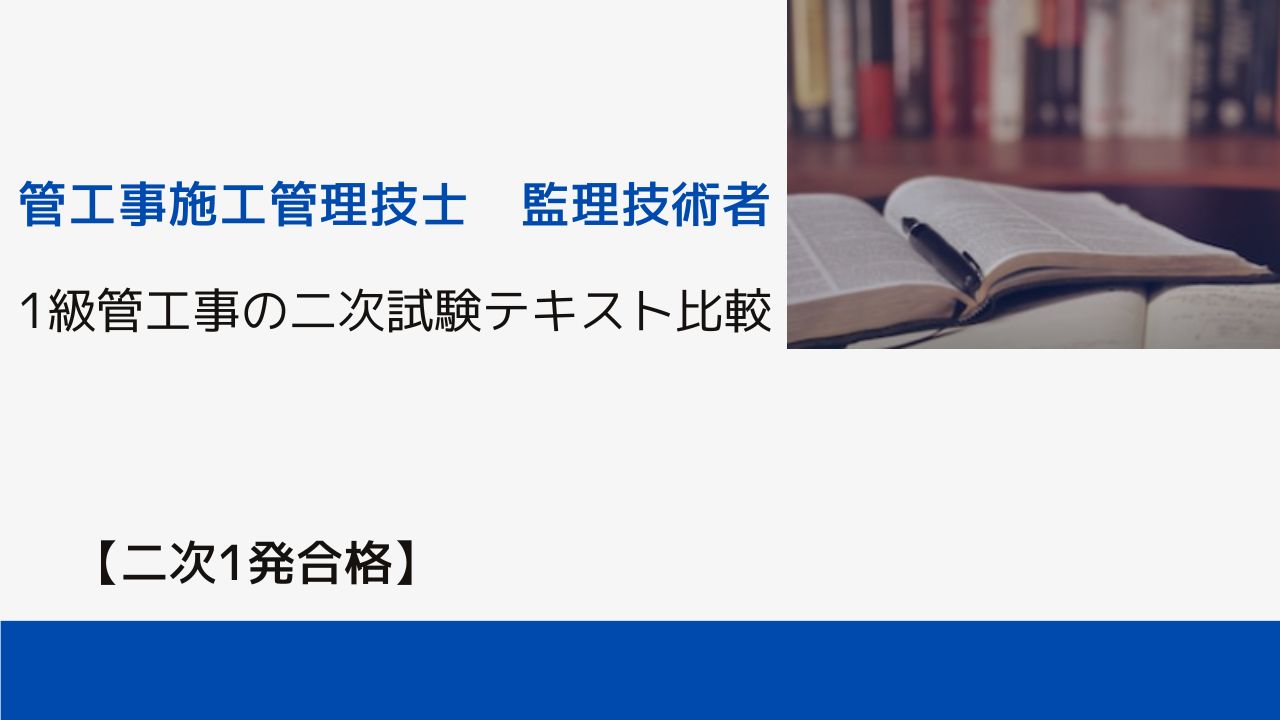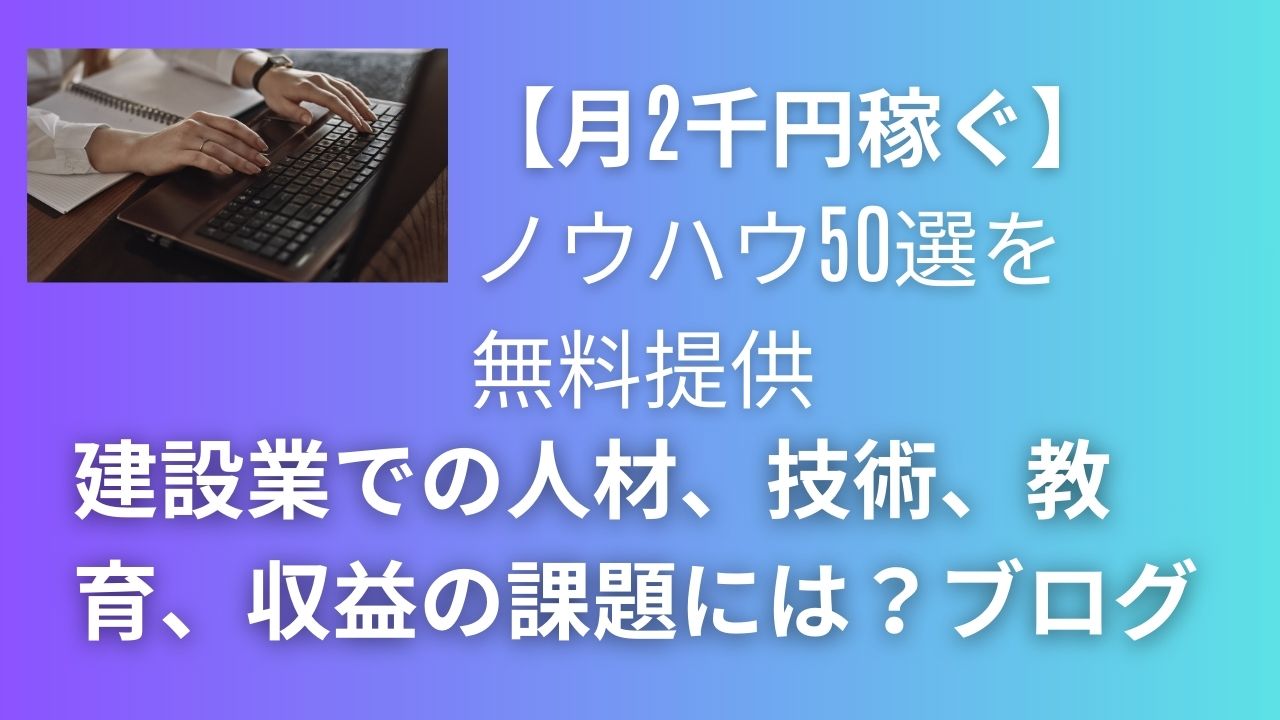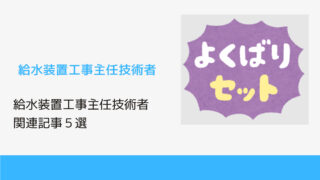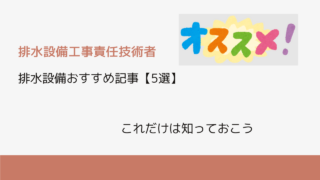という方向けへの記事となります。
はじめに結論:水つかう消防の設備で「それ水圧足りんの」「どんくらいで送れば足りるの?」と送水する場所に書かれている値
この記事では
- 消防設備の中で送水側の必要圧力が決められているものがわかる
本記事の内容
- 消防設備の中で送水側の必要圧力が決められているもの
- どういう計算高さ、管の太さ、末端での使用量
設計送水圧力は末端での規定水量水圧の確保なので建物と消防設備の要件による
- 連結送水管のみ
- 連結送水管+屋内消火栓
- 連結送水管+屋内消火栓+消防用スプリンクラー設備
それぞれ計算は違う。
大体送水口の銘板とこに書いてあります
関連記事です
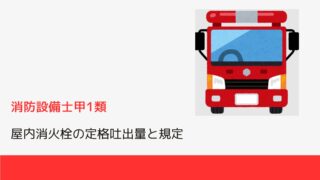
消防設備の中で送水側の必要圧力が決められているもの
消防設備士甲一類は水系なので、
水の送水圧力について学ぶ必要があります。
- 屋内消火栓
- 屋外消火栓
- スプリンクラー設備
- 屋内散水栓
などが挙げられます
水系の末端ヘッドやホースノズルでの設計上の水圧水量を確保ためする送水箇所での計算上の必要圧力をしている
系統図みたいのを建物建てるときに
消防署に事前に10日前に消防設備士が提出、工事完了後4日以内に関係者が提出
して検査を受ける、
系統図は書いたことないからわからないです。
ただ、計算は消防設備士の甲類1では行いますね連結送水管でなく2号消火栓の絵が多いですが
どういう計算かというと
屋内消火栓ははじめからポンプがついています
連結送水管はポンプがついていないで消防車のポンプから送りますので「はて?圧力はこの建物では?」
となります。
ポンプがあればいいというわけではなくポンプがあったらあったで、事前に計算済みの圧力の圧力を送ります。
試験の値はこの圧力の1.5倍を送水試験で行います
どういう計算高さ、管の太さ、末端での使用量
消防の試験だと2号消火栓ですが、
- 管の太さの摩擦損失水頭〇m
- ルート(末端で最高位)一番条件の悪いところ
- 消火栓の高さ(2号消火栓なら1.5mなど)
- 消火栓までの連結送水管の送水口からの高さ(階高3mで10階ならGLから3×9 27+ホースの高さ)
などを加味して計算します
同時使用の数
スプリンクラー設備 10個、15個
屋内消火栓2本
連結送水管1
などとありますが、同時使用よりも
末端での使用水量と水圧が確保されていること
を系統図で示す必要があります
かなりの高層になると途中にポンプが必要になる場合があります
ざっくり計算
高さ
連結送水管なら7階以上は必須ですから
7階建ての場合で階高が3m
なら6×3=18m
7階のホースの高さ1.5m
として18+1.5=19.5m
厳密には送水口の高さは0.5-1mなので
0.5mマイナスして
19m
配管の摩擦損失水頭
配管の損失水頭は仮に65A
19.5m
SGPの損失水頭
SGP 65A 損失水頭
出典:東京消防庁
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000060137.pdf
L×2
横引き2m(仮)
19.5+2=21.5m
継ぎ手バルブの直管換算長さ
SGP 65A 直管換算長さ
出典:消防庁
https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/assets/h20_kokuzi32.pdf
SGP65A 90度チーズ 1個2m ×2 4m
バタ弁65A 6m
仕切弁65A 1m
4+6+1=11m
21.5+11m 32.5mここまで
ホースは?
連結送水管のホース
2号は25mの長さ
連送のホース長さ
水平距離で50m規定ですが
そんなにホース長いかな?というのはありますねー
https://www.itachibori.co.jp/wp-content/uploads/2014/11/2019-_Part43.pdf
出典:立売掘製作所
32.5m↑まで
65Aホース
建物のサイズによりますが、
8m位ですかね(適当)
32.5+8=40.5mの水頭
130ML/分
150ML/分
設計できないのでAI頼み
ハルシレーション禁止で 連結送水管のホースの長さは
連結送水管のホースの長さについて、消防法令に基づく規定をお答えします。
連結送水管のホースの長さは、消防法施行規則および関連する技術基準により以下のように定められています:
標準的な長さ
- 一般的には 20メートル が標準とされています
技術基準での規定
- 消防法施行規則では、連結送水管設備のホースは、建物の構造や用途に応じて適切な長さを確保することが求められています
- 最上階や最遠端の防火対象物まで有効に放水できる長さである必要があります
実際の設計における考慮事項
- 建物の規模、階数、用途によって必要な長さが決まります
- 消防隊が効率的に消火活動を行えるよう、取り回しの良さも考慮されます
- 地域の消防署の運用方針によっても若干の違いがある場合があります
正確な仕様については、所轄の消防署や消防設備の設計・施工業者に確認されることをお勧めします。建物の具体的な条件によって要求される仕様が変わる場合があるためです。
si単位
| 配管抵抗計算表(連結送水管①) | ||||||||
| 管路区分 | 流量Q (ℓ/min) | 形状 | 管径 (mmφ) | 流速v (cm/sec) | f (mmAq/m) | 長さ(相当長)(m) | ΔP (mmAq) | 備考 |
連結送水管のホースの径とノズルの必要放水圧力は
連結送水管のホースの径とノズルの必要放水圧力について、消防法令に基づく規定をお答えします。
ホースの径
- 65mm が標準的な径です
- 消防法施行規則に基づき、消防隊が使用する標準的な消防ホースと同じ径が採用されています
ノズルの必要放水圧力
- 0.35MPa以上(約3.5kg/cm²以上)が一般的な基準です
- この圧力は、ノズル先端での有効な放水を確保するために必要な最低圧力として定められています
関連する技術基準
- 消防法施行規則第13条の2および関連する告示により規定されています
- 建物の高さや用途によって、より高い圧力が要求される場合があります
- 送水口から最上階や最遠端までの摩擦損失も考慮して、送水圧力を設定する必要があります
実際の設計での考慮事項
- 建物の階数が高い場合は、静水圧や摩擦損失を加味してより高い送水圧力が必要になります
- 消防ポンプ車の性能や地域の消防署の仕様との整合性も重要です
詳細な仕様については、所轄の消防署や消防設備士にご確認ください。
ハルシレーション禁止で 連結送水管のホースの径とノズルの必要放水量毎分は
連結送水管のホースの径とノズルの必要放水量について、消防法令に基づく規定をお答えします。
ホースの径
- 65mm が標準的な径です
ノズルの必要放水量(毎分)
- 350L/min以上(毎分350リットル以上)が基準です
- これは1本のノズルあたりの放水量として規定されています
技術基準での規定
- 消防法施行規則第13条の2および関連告示により定められています
- この放水量は、有効な消火活動を行うために必要な最低限の水量として設定されています
実際の運用での考慮事項
- 建物の用途や規模によって、複数のノズルを同時使用する場合があります
- 消防ポンプ車の給水能力や建物の給水設備との整合性が重要です
- 放水圧力(0.35MPa以上)と放水量(350L/min以上)の両方を満たす必要があります
設計上の注意点
- 配管の摩擦損失や高低差による圧力損失を考慮して、送水圧力を設定する必要があります
- 同時使用本数に応じた総流量の確保も重要です
具体的な設計については、所轄の消防署や消防設備士にご確認ください。
関連記事もありますのでよろしければどうぞ
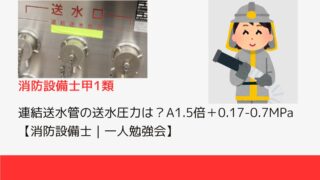
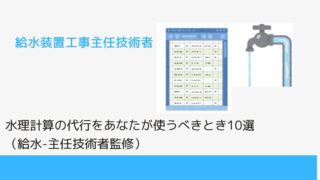
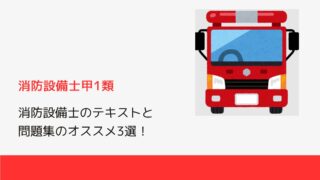
消防設備士オススメテキストランキングはこちらこちら